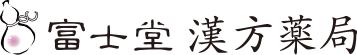2025.08.06
【症例更新】手指のしもやけと冷え性が2か月の漢方治療で改善した症例
しもやけと冷え性が2ヶ月の漢方治療で改善した症例をご紹介。しもやけの症状や原因、治療法と経過を詳しく解説します。
冷え性は多くの人にとって日常的な悩みの一つですが、その症状が進行すると「しもやけ」などの辛い症状を引き起こすことがあります。特に女性に多く見られる冷え性やしもやけは、血行不良や生活習慣の影響を大きく受けることが知られています。本記事では、冷え性としもやけに悩む50代女性の症例をもとに、漢方薬治療による改善例をご紹介します。
冷え性は、特に女性に多く見られる症状であり、日常生活に大きな影響を与えることがあります。報告によると、女性の約8割、男性の約4割が冷え性を自覚しているとされ、その原因には以下のような要因が考えられます:
冷え性は血行不良による副次的な影響を引き起こしやすく、便秘、肌荒れ、各種の痛みなどの症状が現れることがあります。さらに放置すると重篤な疾患を引き起こす可能性があるため、早めの対策が重要です。
また、冷えが慢性化すると、血流が悪化した手足の末端に「しもやけ(凍瘡)」が生じることがあります。特に冬場や寒暖差が激しい環境では、皮膚が赤く腫れてかゆみや痛みを伴うしもやけに悩まされる方も少なくありません。しもやけもまた体質に深く関係する症状であり、冷え性と同様に根本からの改善が求められます。
今回ご紹介するのは、冷え性に加え、両手のしもやけでお悩みの50代女性の症例です。
体質:不明
症候:手足冷え、あかぎれ、しもやけ
散剤:当帰芍薬散
散剤:当帰芍薬散
症状が大幅に改善したため、この診察で治療を終了。
漢方薬の服用後、患者の皮膚状態は大きく改善しました。特に、しもやけの症状が軽減し、手指のあかぎれも治癒傾向が見られたことから、漢方薬が血行促進や体質改善に効果的であることが示されました。また、皮膚のターンオーバーがスムーズに進み、落屑が見られなかった点も注目に値します。
冷え性やしもやけは、体質だけでなく、日常生活や生活習慣の影響を大きく受けます。今回の患者様は、過去に脂漏性皮膚炎の既往があるほか、冷房の影響を受けやすい体質でした。こうした背景に加え、ストレスが症状の悪化要因となっていることも確認されました。実際、ストレスが軽減されると治療効果が格段に高まることが観察され、ストレスの軽減や回避方法を考えることの重要性が改めて浮き彫りになりました。
さらに、BMIが18.5未満の瘦身型女性では、22.0以上の女性に比べて冷え感を強く感じやすいという報告があります。また、気温の変化に伴い、瘦身型女性は四肢末端部の皮膚温が低下しやすく、冷え性群では皮膚表面温度の回復が遅れる傾向があることが明らかになっています。これらの点からも、過剰なダイエットを控え、適切なエネルギー摂取や運動による代謝向上を図ることが必要です。
さらに、外食や菓子パン中心の食生活が冷え性を助長する可能性も指摘されています。食事内容を見直し、体を温める食材を取り入れることで、手指の温度が改善する可能性があります。このように、漢方薬による治療に加え、生活習慣を総合的に改善することが冷え性やしもやけの根本的な対策につながると考えられます。
冷え性やしもやけは、漢方薬による治療だけでなく、日々の生活習慣の改善が重要なポイントとなります。今回の症例では、血行を促進し体質を改善する漢方薬がしもやけの軽減に効果を発揮しましたが、患者自身の生活の見直しも症状の改善に大きく寄与しました。冷え性やしもやけでお悩みの方は、ぜひ漢方薬とともに、自分に合った食事や運動、ストレス管理を取り入れてみてはいかがでしょうか。冷えに悩まされない快適な生活を目指すための第一歩として、お気軽にご相談ください。
漢方薬を受け取るまでの流れは以下のようになります。
ご予約➤ご相談➤漢方薬の選定➤ご確認・お会計➤調剤・お渡し(発送)
詳しくはこちらをご覧くださいませ。
漢方薬は、一人ひとりの体質や体調、生活環境、そしてその方をとりまく背景によって、必要な処方が大きく異なります。そのため富士堂漢方薬局では、最初に丁寧なカウンセリングを行い、現在のお困りの症状だけでなく、これまでの経過や生活習慣、ストレス要因なども含めて総合的に把握することを大切にしています。
ご相談は予約優先制で、個室にてプライバシーに配慮した落ち着いた環境の中、ゆっくりとお話を伺います。初回のカウンセリングでは、漢方医学に基づく「四診(望診・聞診・問診・切診)」をもとに、舌の状態、脈、腹部の緊張や冷えの有無なども丁寧に確認します。
また、西洋医学的な視点も大切にしており、血液検査や画像検査の結果がある場合には、それらも参考にしながら総合的に判断します。まずはお気軽にご相談ください。
■漢方相談予約・お問合せ>>「お問い合わせ(LINE,WeChat,メールフォーム)」
■オンライン相談について詳しくはこちら>>「オンライン漢方相談|来店なしでお薬お届け」
漢方求真 許志泉著 桐書房 p.300
漢方診療医典 第5版 p.294
Yuriko Kusumi et.al. Evaluation of hiesho using a cold-water load test in adult females. J. Jpn. Acad. Midwif., Vol. 23, No.2, 241-250, 2009
K.Fujita et.al. The Relationship between Feeling Chills, Physical Characteristics, and Lifestyle Habit among Youth Females. スポーツ健康科学研究 39: 19-27, 2017.
文責:入多裕(薬剤師)
しもやけと冷え性の改善に向けた漢方治療
冷え性は多くの人にとって日常的な悩みの一つですが、その症状が進行すると「しもやけ」などの辛い症状を引き起こすことがあります。特に女性に多く見られる冷え性やしもやけは、血行不良や生活習慣の影響を大きく受けることが知られています。本記事では、冷え性としもやけに悩む50代女性の症例をもとに、漢方薬治療による改善例をご紹介します。
しもやけ・冷え性とは?|症状と原因を解説
冷え性は、特に女性に多く見られる症状であり、日常生活に大きな影響を与えることがあります。報告によると、女性の約8割、男性の約4割が冷え性を自覚しているとされ、その原因には以下のような要因が考えられます:
- 筋肉量の少なさ:筋肉は熱を作り出す役割を持つため、筋肉量が少ないと体が冷えやすくなります。
- ホルモンバランスの乱れ:特に女性はホルモンバランスの影響で自律神経が乱れ、血行不良が起こりやすくなります。
- ストレス:ストレスは交感神経を刺激し、末梢血管を収縮させるため、冷えが生じます。
- 乱れた生活習慣:睡眠不足や不規則な生活は自律神経を乱し、血行不良や体の冷えを引き起こします。
- 冷房による冷え(冷房病):エアコンの長時間使用により体温調節が崩れることも冷えの原因です。
冷え性は血行不良による副次的な影響を引き起こしやすく、便秘、肌荒れ、各種の痛みなどの症状が現れることがあります。さらに放置すると重篤な疾患を引き起こす可能性があるため、早めの対策が重要です。
また、冷えが慢性化すると、血流が悪化した手足の末端に「しもやけ(凍瘡)」が生じることがあります。特に冬場や寒暖差が激しい環境では、皮膚が赤く腫れてかゆみや痛みを伴うしもやけに悩まされる方も少なくありません。しもやけもまた体質に深く関係する症状であり、冷え性と同様に根本からの改善が求められます。
今回ご紹介するのは、冷え性に加え、両手のしもやけでお悩みの50代女性の症例です。
症例紹介:50代女性の冷え性としもやけ
患者情報
- 性別・年齢:女性、50代
- 身体情報:身長159.0cm、体重49.0kg、BMI 19.4
主訴
- 冷えと両手のしもやけ(赤く腫れ、痒みあり)
- 特に右手足が冷えやすい
- あかぎれができやすい
現病歴
- 20年前から冷えを自覚。夏の冷房で体調を崩しやすい。
- 1~2週間前からしもやけの徴候が出現。
症候
- 冷え対策:手袋、ハンドウォーマー、ショルダーウォーマーで冷えが改善。
- 増悪条件:夏のエアコンで症状が悪化。
その他の症状
- 足首のむくみ、首肩の凝り、目の疲れやすさ
- 便通:2日に1回(硬め)
- 尿:8~10回/日
- 食欲:普通~少なめ(油ものが苦手)
- 水分:1000mL/日(温かい飲み物)
- 持病:軽度のGERD(胃食道逆流症)
- 顔色:良くない、暗い黄色
- 運動:ウォーキング
既往歴・家族歴
- 既往歴:2015年に脂漏性皮膚炎
- 家族歴:
父:肺がん、呼吸器疾患
母:胆石
評価
- 脈診:脈沈2遅2細弱2緩2
- 腹診:脈沈2遅2細弱2緩2
腹壁中、腹力やや硬 - 舌診:ややドン、淡紅色、大、歯痕なし、苔中、薄白黄
裏怒張:少しあり
体質:不明
症候:手足冷え、あかぎれ、しもやけ
治療方針
- 冷えの改善と血行促進
- 浮腫みの改善
- 首への冷たい風を防ぐ(マフラーの使用推奨)
漢方薬
散剤:当帰芍薬散
治療経過
2回目
- 症状の変化:服用開始後、一時的に痒みとしもやけ症状が悪化したが、1週間ほどで改善。現在は痒みが少し残る程度。
- あかぎれ:右手中指に1か所あかぎれが見られる。
- 便通:コロコロ便から普通便に改善。
- 首肩の状態:服用開始後に一度悪化したが、1週間で改善。
- 睡眠:夢を見ることは多いが、起床後のだるさはない。
追加治療
- 外用薬:紫雲膏をあかぎれ部位に使用。衣類や布団への着色に注意するよう指導。
漢方薬
- 散剤:当帰芍薬散
- 外用薬:紫雲膏
3回目
- 症状の変化:両手指先に赤みが見られるが、あかぎれは両手とも改善。新たに右手人差し指第一関節にあかぎれができたが、傷口はふさがっている。
- 冷えの状態:四肢末端と太ももの冷えを自覚。右側の冷えが左側より強い。
- むくみ:足がむくみ、押すと皮膚が戻りにくい感覚あり。
- その他:3月9日に膀胱炎を発症し、抗生物質で治療済み。
舌診・腹診
- 舌診:苔は薄く白黄、歯痕なし。裏に血管の怒張あり。
- 腹診:全体的に柔らかい印象。胸脇苦満や心下痞鞕はなし。
漢方薬
散剤:当帰芍薬散
結果
症状が大幅に改善したため、この診察で治療を終了。
この症例から考える冷え性としもやけの漢方治療の可能性
漢方薬の服用後、患者の皮膚状態は大きく改善しました。特に、しもやけの症状が軽減し、手指のあかぎれも治癒傾向が見られたことから、漢方薬が血行促進や体質改善に効果的であることが示されました。また、皮膚のターンオーバーがスムーズに進み、落屑が見られなかった点も注目に値します。
冷え性やしもやけは、体質だけでなく、日常生活や生活習慣の影響を大きく受けます。今回の患者様は、過去に脂漏性皮膚炎の既往があるほか、冷房の影響を受けやすい体質でした。こうした背景に加え、ストレスが症状の悪化要因となっていることも確認されました。実際、ストレスが軽減されると治療効果が格段に高まることが観察され、ストレスの軽減や回避方法を考えることの重要性が改めて浮き彫りになりました。
さらに、BMIが18.5未満の瘦身型女性では、22.0以上の女性に比べて冷え感を強く感じやすいという報告があります。また、気温の変化に伴い、瘦身型女性は四肢末端部の皮膚温が低下しやすく、冷え性群では皮膚表面温度の回復が遅れる傾向があることが明らかになっています。これらの点からも、過剰なダイエットを控え、適切なエネルギー摂取や運動による代謝向上を図ることが必要です。
さらに、外食や菓子パン中心の食生活が冷え性を助長する可能性も指摘されています。食事内容を見直し、体を温める食材を取り入れることで、手指の温度が改善する可能性があります。このように、漢方薬による治療に加え、生活習慣を総合的に改善することが冷え性やしもやけの根本的な対策につながると考えられます。
まとめ|しもやけ・冷え性を体質から改善させたい方へ
冷え性やしもやけは、漢方薬による治療だけでなく、日々の生活習慣の改善が重要なポイントとなります。今回の症例では、血行を促進し体質を改善する漢方薬がしもやけの軽減に効果を発揮しましたが、患者自身の生活の見直しも症状の改善に大きく寄与しました。冷え性やしもやけでお悩みの方は、ぜひ漢方薬とともに、自分に合った食事や運動、ストレス管理を取り入れてみてはいかがでしょうか。冷えに悩まされない快適な生活を目指すための第一歩として、お気軽にご相談ください。
ご相談の流れ|ご予約はこちらから
漢方薬を受け取るまでの流れは以下のようになります。
ご予約➤ご相談➤漢方薬の選定➤ご確認・お会計➤調剤・お渡し(発送)
詳しくはこちらをご覧くださいませ。
漢方薬は、一人ひとりの体質や体調、生活環境、そしてその方をとりまく背景によって、必要な処方が大きく異なります。そのため富士堂漢方薬局では、最初に丁寧なカウンセリングを行い、現在のお困りの症状だけでなく、これまでの経過や生活習慣、ストレス要因なども含めて総合的に把握することを大切にしています。
ご相談は予約優先制で、個室にてプライバシーに配慮した落ち着いた環境の中、ゆっくりとお話を伺います。初回のカウンセリングでは、漢方医学に基づく「四診(望診・聞診・問診・切診)」をもとに、舌の状態、脈、腹部の緊張や冷えの有無なども丁寧に確認します。
また、西洋医学的な視点も大切にしており、血液検査や画像検査の結果がある場合には、それらも参考にしながら総合的に判断します。まずはお気軽にご相談ください。
■漢方相談予約・お問合せ>>「お問い合わせ(LINE,WeChat,メールフォーム)」
■オンライン相談について詳しくはこちら>>「オンライン漢方相談|来店なしでお薬お届け」
参考資料
漢方求真 許志泉著 桐書房 p.300
漢方診療医典 第5版 p.294
Yuriko Kusumi et.al. Evaluation of hiesho using a cold-water load test in adult females. J. Jpn. Acad. Midwif., Vol. 23, No.2, 241-250, 2009
K.Fujita et.al. The Relationship between Feeling Chills, Physical Characteristics, and Lifestyle Habit among Youth Females. スポーツ健康科学研究 39: 19-27, 2017.
文責:入多裕(薬剤師)