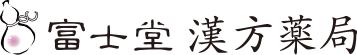更新日:2025.07.22不妊症・不育症・産後ケア
妊活に効果的な漢方と食事法【セルフ体質診断チェック付き】
「妊活を始めたけれど、なかなか思うような結果が出ない」「食事面で何か工夫できることがあれば知りたい…」そんな思いを抱えている方もいるのではないでしょうか?東洋医学の視点から見ると、妊娠しやすい体づくりには自分の体質を知り、それに合った食事を取り入れることが非常に効果的です。
この記事では、妊活中の方が自分の体質を知り、それぞれの体質に合った食事法を実践するための具体的な方法を紹介していきます。
妊活は自分の体質を知ることからスタート
妊活を成功させるためには、まず自分の体質を知ることが大切です。自分の体質タイプを知ることで、より効果的な妊活が可能になりますよ。
東洋医学における「気・血・水」の考え方
東洋医学では、人の体を構成する基本的な要素は「気・血・水」だと考えています。妊活においてはこのバランスが特に重要で、崩れてしまうと妊娠しにくい体質になりやすくなります。
| 要素 | 意味 | 役割 | 不調の症状(例) |
| 気(き) | ・体内のエネルギー
・生命活動の源 |
・体を温める
・各機能を動かす |
・疲れやすい
・基礎体温の不安定 ・冷え |
| 血(けつ) | 栄養や潤いをもたらす要素 | ・全身に栄養を運ぶ
・潤いを与える |
・生理不順
・子宮内膜が薄くなる ・顔色不良 |
| 水(すい) | ・体内の水分
・体液 |
・体内を潤す
・熱を抑える |
・むくみ
・冷え ・水分バランスの乱れ |
「気」の働きと妊活への影響
「気」は目に見えない生命エネルギーであり、全身の各機能を動かす力です。
具体的には、以下の5つの働きがあります。
- 推動作用(血や水を全身に巡らせる)
- 温煦作用(体を温める)
- 防御作用(外敵から身を守る)
- 固摂作用(体液の漏出を防ぐ)
- 気化作用(食べ物をエネルギーに変える)
妊活においては、この「気」が卵巣内の卵胞を育て、良質な卵子を作るために不可欠です。気が不足すると、卵巣機能の低下やホルモンバランスの乱れを引き起こし、排卵障害や基礎体温の不安定にもつながります。
「血」の役割と妊娠力への影響
「血(けつ)」は単なる血液だけでなく、全身に栄養や潤いをもたらす要素。全身を巡って各部位に栄養を与え、精神を安定させる働きがあります。
妊活では、特に「血」の質と流れが重要です。良質な「血」は子宮内膜を厚く健康に保ち、受精卵の着床環境を整える重要な要素となります。
血の巡りが悪い「瘀血(おけつ)」の状態になると、子宮内膜の状態が悪化し、着床障害や不妊の原因となります。また、血が不足すると生理不順や子宮内膜が薄くなるなどの問題も生じやすくなります。
「水」の機能と妊娠環境への影響
「水」は血以外の汗や唾液、リンパ液、胃液といったすべての体液を指します。体内を潤す、関節をスムーズに動かす、体内の熱や興奮を抑える、水分のバランスを調整するなどの働きがあります。
妊活においては、適切な水分バランスが卵胞の発育や子宮環境の整備に重要な役割を果たします。
水の巡りが悪くなると、むくみや冷えの原因となり、生殖機能にも悪影響を及ぼします。特に「水滞(すいたい)」の状態では、体内に余分な水分が滞ることで、子宮や卵巣の機能に負担がかかる可能性があります。
妊活に関わる6つの体質|セルフ体質診断
東洋医学では、妊活に関わる体質を以下の6つに分類しています。それぞれ3つ以上当てはまる場合は、そのタイプの傾向が高いと考えられます。複数のタイプに当てはまる場合は、複合タイプの可能性もあります。
気虚タイプ
- 朝起きるのがつらい
- 少し動くだけで疲れる
- 声が小さく、息切れしやすい
- 風邪をひきやすい
- 食欲がない時がある
- 手足が冷たいことが多い(冷え症の症状)
気虚(ききょ)とは、体内のエネルギーである「気」が不足している状態です。現代社会では、ストレスや不規則な生活、過労などによってこのタイプの方が増えています。
3つ以上当てはまった人は…
気虚状態では体全体の機能が低下し、ホルモンバランスにも影響が出やすくなります。
妊活においては、排卵機能や子宮内膜の状態にも悪影響を及ぼすことがあります。また、気虚が進行すると冷え症(陽虚)を引き起こしやすくなります。
冷えは妊活の大敵であり、血行不良により子宮や卵巣への血流が減少しやすくなり、妊娠力に直接影響します。
血虚(けっきょ)タイプ
- 疲れやすく、顔色が悪い
- 爪が薄くて割れやすい
- 髪にツヤがなく、抜け毛が多い
- 目が乾燥しやすい
- 生理の量が少なく色が薄い
血虚とは、体を潤し栄養を運ぶ「血」が不足している状態のこと。現代女性に多く見られるタイプで、無理なダイエットや偏った食生活が原因となることもあります。
3つ以上当てはまった人は…
血虚状態では子宮内膜が十分に育たず、着床に不利な要素となりやすいです。
血は子宮内膜を形成する重要な要素であり、血が不足すると子宮内膜が十分に育たず、受精卵が着床しにくくなります。また、卵巣機能にも影響し、良質な卵子の生成を妨げる可能性もあります。
気滞(きたい)タイプ
- イライラしやすい
- 胸やわき腹が張った感じがする
- ため息が多い
- 気分の浮き沈みが激しい
- ストレスを感じることが多い
気滞とは、体内の「気」の流れが滞っている状態です。ストレスや感情の抑圧が主な原因となります。
3つ以上当てはまった人は…
気滞状態ではホルモンバランスが乱れやすく、排卵障害や生理不順につながりやすくなります。
気の流れが滞ることで、子宮や卵巣の機能にも悪影響を及ぼし、妊娠しにくい体質になってしまう可能性があります。
瘀血(おけつ)タイプ
- 生理痛がひどい
- 経血に血の塊が多い
- 肌に紫色のシミやクモ状静脈がある
- 唇や舌の色が暗い
- 目の下にクマができやすい
瘀血とは、血液の流れが滞り、古い血が体内に停滞している状態です。冷えや運動不足、ストレスなどが原因となります。
3つ以上当てはまった人は…
瘀血状態では、子宮内の血液循環が悪くなり、子宮内膜の状態が悪化しやすくなります。これにより、受精卵の着床環境が整わず、妊娠しにくくなる可能性があります。
また、子宮筋腫や子宮内膜症などの婦人科疾患を引き起こすリスクも高まります。
陰虚(いんきょ)タイプ
- のぼせやほてりがある
- 手のひらや足の裏が熱く感じる
- 口や喉が乾きやすい
- 寝汗をかきやすい
- 便が硬く、排便困難がある
陰虚とは、体内の潤いやクールダウン機能が不足している状態です。過労やストレス、加齢などが原因となります。
3つ以上当てはまった人は…
陰虚状態では、体内の潤いが不足し、子宮内膜の状態が悪化しやすくなります。
また、ホルモンバランスも乱れやすく、排卵障害や生理不順を引き起こすことがあります。体内の熱が高まりすぎることで、卵子や精子の質にも悪影響を及ぼす可能性があります。
水滞(すいたい)タイプ
- むくみやすい
- 体が重だるい
- おりものが多い
- 痰がからみやすい
- 体重の変動が大きい
水滞とは、体内の水分代謝が悪く、水分が停滞している状態です。冷えや運動不足、過度の塩分摂取などが原因となります。
3つ以上当てはまった人は…
水滞状態では、体内の水分バランスが崩れ、子宮周辺の環境が悪化しやすくなります。過剰な水分が停滞することで、子宮や卵巣の機能が低下し、妊娠しにくい体質となる可能性があります。
また、ホルモンバランスにも影響を及ぼし、排卵障害や生理不順を引き起こすことがあります。
気虚タイプにおすすめの食材と食事の取り方
気虚タイプの方は、体内のエネルギーが不足している状態です。消化機能が低下していることが多いため、温かく消化しやすい食事を心がけましょう。体を温め、胃腸に負担をかけず、「気」を効率的に補給できる食材選びが重要です。
気虚タイプにおすすめの食材カテゴリ一覧|温かく消化しやすいもの
| 食材カテゴリー | 具体例 | 効果・特徴 |
| 穀物類 | うるち米、雑穀類 | ・カラダのエネルギー源となる
・やわらかく炊いたりおかゆにすると良い |
| いも類 | じゃがいも、さつまいも、山芋、かぼちゃ | ・消化が良く持続的なエネルギーを供給
・優しい甘みが気を補う |
| 豆類・キノコ類 | 大豆、枝豆、えんどう豆、椎茸、舞茸 | ・消化の良い形で食べると良い(細かく刻むなど)
・良質なタンパク質源となる |
| 肉類 | 鶏肉、豚肉 | ・体を温める性質を持つ
・良質なタンパク質で体力を回復 ・消化の良い形で食べるとよい(ひき肉など) |
| 魚介類 | タラ、鮭、ヒラメ、イワシ、タコ、ホタテなど | ・タンパク質が豊富
・消化しやすい |
| 野菜類 | キャベツ、アスパラガス、かぶ、にんじん | ・消化しやすく栄養価が高い
・温野菜、スープがおすすめ |
| 香味野菜 | ニラ、ニンニク、ネギ、玉ねぎ、ショウガ | ・体を温める作用がある
・消化を助ける |
| 果物・甘味料 | りんご、ぶどう、パイナップル、なつめ、はちみつ | ・疲労回復を促進 |
| 飲み物 | 紅茶、甘酒 | ・体を温める作用がある
・紅茶にレーズンを入れると薬膳茶になる |
気虚タイプが避けるべき食材カテゴリー一覧|胃腸に負担をかけるもの
| 食材カテゴリー | 具体例 | 理由 |
| 生、冷たい食べ物 | 冷たい飲み物、アイスクリーム、冷奴、生野菜 | ・胃腸の機能を低下させる
・消化吸収を妨げる ・体の中心温度を下げる |
| 消化の悪い食べ物 | 脂っこい揚げ物、生肉 | ・限られたエネルギーを消化に使う
・体力回復を遅らせる ・胃腸に負担をかける |
| 過度に辛い食べ物 | 唐辛子、山椒、わさび | ・胃腸に負担をかける
・体内のエネルギーを消耗させる |
| 刺激物 | コーヒー、アルコール | ・利尿作用で体を冷やす
・胃腸を刺激する |
気虚タイプの食事の取り方・ポイント
気虚タイプの方は、温かく消化しやすい料理を中心に摂りましょう。おかゆ、スープ、蒸し物、煮物などがおすすめです。
冷たい食べ物や生ものは避け、よく噛んで食べることで消化を助けます。一度に大量の食事は胃腸に負担をかけるので、少量ずつ頻繁に食べるのが良いでしょう。
早朝の食事は特に重要で、朝食をしっかり摂ることで一日のエネルギーを確保できます。また、寝る前3時間は食事を避け、十分な睡眠と休息を取ることも大切です。
血虚タイプにおすすめの食材と食事の取り方
血虚タイプの方は、体を潤し栄養を運ぶ「血」が不足している状態。
色の濃い食材、特に赤色や黒色の食材を積極的に取り入れ、良質なタンパク質や鉄分を含む食事を心がけましょう。血を補い、体に潤いと栄養を与える食材選びが重要です。
血虚タイプにおすすめの食材カテゴリー一覧|色の濃い食材を積極的に
| 食材カテゴリー | 具体例 | 効果・特徴 |
| 黒・赤色の食材 | 黒豆、黒ごま、黒きくらげ、黒砂糖、黒米、にんじん | ・造血作用がある
・ミネラルやポリフェノールを多く含む |
| 動物性タンパク質 | レバー、赤身肉、牡蠣、うずら卵 | ・鉄分やビタミンB12が豊富
・貧血改善と血の質を高める ・ヘモグロビンの材料となる |
| 緑黄色野菜 | ほうれん草、小松菜、パセリ、よもぎ | ・鉄分や葉酸が豊富
・血の質を高める ・ビタミンも豊富 |
| ドライフルーツ | なつめ、クコの実、プルーン、レーズン、ブルーベリー | ・鉄分や食物繊維が豊富
・血の巡りを良くする ・自然の甘味や酸味がある |
| 海藻類 | ひじき、わかめ、のり | ・鉄分やミネラルが豊富
・血を補う効果がある |
| 魚介類 | あさり、穴子、イワシ、うなぎ、カツオ、鮭、サバ、ブリ、マグロ | ・良質なタンパク質を含む
・血を補う効果がある ・消化しやすい |
| ビタミンC食品 | レモン、イチゴ、キウイ、みかん | ・鉄の吸収を高める
・抗酸化作用がある ・動物性タンパク質と一緒に摂ると効果的 |
| その他の食材 | 松の実、カシス、ぶどう、ライチ、さくらんぼ | ・血を補う効果がある
・抗酸化物質が豊富 ・体温を上げる効果もある |
血虚タイプが避けるべき食材カテゴリー一覧|消化に負担がかかるもの
| 食材カテゴリー | 具体例 | 理由 |
| 辛すぎる食材 | 唐辛子、わさび、からし | ・発散する性質があり血虚を悪化させる
・血の消耗を促進する ・体内の熱を高める |
| 消化に悪い食材 | 小麦製品、脂っこい食品、乳製品 | ・胃腸に負担をかける
・栄養吸収を妨げる ・血の生成を阻害する |
| 冷たい食べ物 | 冷たい飲み物、アイスクリーム、冷奴 | ・体を冷やし血行を悪くする
・消化機能を低下させる ・血の生成を妨げる |
| 生野菜のみの食事 | 生サラダ、生野菜ジュース | ・体を冷やす
・消化に負担がかかる ・血の生成に必要なエネルギーを消費する |
血虚タイプの食事の取り方・ポイント
血虚タイプの方は、温かく消化しやすい料理を中心に、色の濃い食材を積極的に取り入れましょう。おかゆ、スープ、蒸し物、煮物などがおすすめです。
特に黒い食材(黒豆、黒ごま)や赤い食材(タコの実、赤身肉)は、血を補う効果があります。鉄分の吸収を高めるために、ビタミンCを含む食材と一緒に摂ることも大切です。
漢方では血は夜に作られるとされているので、早めに就寝し、十分な睡眠時間を確保することも重要です。サウナや岩盤浴で過度に汗をかくことは避け、体の潤いを保つようにしましょう。
気滞タイプにおすすめの食材と食事の取り方
気滞タイプの方は、体内の「気」の流れが滞っている状態です。
ストレスや感情の抑圧が主な原因となるため、気の巡りを良くする香りの高い食材や、ストレスを発散させる効果のある食材を取り入れましょう。体を温め、気の流れをスムーズにする食事が重要です。
気滞タイプにおすすめの食材カテゴリ一ー覧|香りの高いもの
| 食材カテゴリー | 具体例 | 効果・特徴 |
| 香り野菜 | 春菊、三つ葉、せり、セロリ、パセリ、バジル、ピーマン、みょうが | ・精油成分が気の流れを良くする
・ストレスを解消する働きがある |
| 柑橘類・酸味食品 | 金柑、グレープフルーツ、すだち、文旦、みかん、柚子の皮、梅干し | ・肝の働きを高める
・酸味が気の流れを整える |
| 香辛料・ハーブ | フェンネル、オレガノ、シソ、タイム、ローリエ | ・香りが気の巡りを良くする
・消化を助ける |
| スパイス | カルダモン、ターメリック、みかんの皮、ナツメグ、八角 | ・体を温め気の巡りを促進する
・消化を助ける |
| ハーブティー | カモミール、ジャスミン、ミント | ・リラックス効果がある
・ストレスを緩和する |
| 果物 | ライチ、ぶどう | ・自然な甘みでリラックス効果がある
・栄養価が高い |
| 飲み物 | 醸造酒(日本酒や紹興酒)、ワイン | ・気の巡りを良くする
・リラックス効果がある |
気滞タイプが避けるべき食材カテゴリー一覧|体を冷やすもの
| 食材カテゴリー | 具体例 | 理由 |
| 過度に辛い食材 | 唐辛子、わさび、からし | ・一時的に気の巡りを良くするが長期的には悪化
・体内の熱を高めすぎる |
| 冷たい食べ物 | 冷たい飲み物、アイスクリーム | ・体を冷やし気の流れを滞らせる
・消化機能を低下させる |
| 過度の脂肪分 | 揚げ物、脂身の多い肉 | ・消化に負担をかける
・胃腸の働きを弱める |
| 過度のアルコール | 蒸留酒、大量の飲酒 | ・適量を超えると気の流れを乱す
・肝機能に負担をかける |
気滞タイプの食事の取り方・ポイント
気滞タイプの方は、香りの高い食材を取り入れた温かい料理を中心に摂りましょう。炒め物、焼き物、おかゆ、スープなどがおすすめです。特に香味野菜は気の巡りを良くする効果があるので、調理の最後に加えて香りを逃さないようにするのがポイント。
食事の際はリラックスした環境で、ゆっくりと時間をかけて食べることも大切です。ストレスを感じたときは、ハーブティーなどでリラックスする時間を作りましょう。
体が冷えると気の巡りが悪くなるので、温かい食事を心がけ、規則正しい食生活を送ることも重要です。
瘀血タイプにおすすめの食材と食事の取り方
瘀血タイプの方は、血液の流れが滞り、古い血が体内に停滞している状態です。血行を促進し、血液をサラサラにする食材を積極的に取り入れましょう。
体を温め、血の巡りを良くする食事が重要。特に辛味のある食材や青魚は効果的です。
瘀血タイプにおすすめの食材カテゴリ一ー覧|血行を促進するもの
| 食材カテゴリー | 具体例 | 効果・特徴 |
| 辛味野菜 | 玉ねぎ、ねぎ、しょうが、ニラ、ニンニク | ・体を温める
・血行を促進する ・発汗、利尿、解毒を促進 |
| 青背の魚 | イワシ、サンマ、アジ、サバ、ニシン | ・EPAやDHAが豊富
・血液をサラサラにする ・血の流れを良くする |
| 温熱性スパイス | シナモン、山椒 | ・体を温める
・血行促進効果がある |
| 活血作用のある食材 | 玉ねぎ、ラッキョウ、桃、アプリコット、さくらんぼ、生姜 | ・血行を促進する
・血液の質を改善する ・冷えによる血行不良を改善 |
| 薬膳食材 | 紅花、サフラン、ウコン、ローズ | ・血の巡りを促進する
・血液をサラサラにする ・瘀血の改善に効果的 |
| 肉類 | 羊肉、ウナギ | ・体を温める
・新陳代謝を改善する ・血行を促進する |
| 酸味食品 | 黒酢、梅干し | ・血液をサラサラにする
・血行を促進する ・代謝を高める |
瘀血タイプが避けるべき食材カテゴリー一覧|体を冷やすもの
| 食材カテゴリー | 具体例 | 理由 |
| 冷たい食べ物 | 冷たい飲み物、アイスクリーム | ・体を冷やし血行を悪化させる
・血液の流れを鈍らせる ・瘀血を悪化させる |
| 糖分の多い食品 | ケーキ、チョコレート、白砂糖 | ・血液をドロドロにする
・血行を悪くする ・炎症を促進する |
| 脂肪分の多い食品 | 揚げ物、脂身の多い肉 | ・血液の質を悪化させる
・血行を鈍らせる ・瘀血を悪化させる |
| 刺激物 | アルコール(大量)、カフェイン | ・一時的に血行が良くなるが長期的には悪化
・体を冷やす ・血液の質を悪化させる |
瘀血タイプの食事の取り方・ポイント
瘀血タイプの方は、血行を促進する食材を取り入れた温かい料理を中心に摂りましょう。特に辛味のある食材(生姜、ニンニク、ねぎなど)は血行を促進する効果があります。
青魚に含まれるEPAやDHAは血液をサラサラにする効果があるので、週に2〜3回は摂るのがおすすめです。
また、体を冷やす食べ物や飲み物は避け、適度な運動で血行を促進することも大切。食事の際は、ゆっくりと時間をかけて食べ、食後すぐに横にならないようにしましょう。水分をしっかり摂ることも血液の質を改善するのに役立ちます。
陰虚タイプにおすすめの食材と食事の取り方
陰虚タイプの方は、体内の潤いやクールダウン機能が不足している状態です。
体を潤す食材や熱を冷ます効果のある食材を積極的に取り入れましょう。特にネバネバした食材や白色の食材は体に潤いを与える効果があります。
辛い食べ物は控え、体の潤いを保つ食事が重要です。
陰虚タイプにおすすめの食材カテゴリ一ー覧|体を潤すもの
| 食材カテゴリー | 具体例 | 効果・特徴 |
| ネバネバ食材 | 山芋、オクラ、白きくらげ | ・体の潤いを補う効果がある
・生に近い状態で食べるのがおすすめ ・みずみずしい状態で摂取すると効果的 |
| 白色の食材 | 山芋、蓮根、白きくらげ、ゆり根 | ・肺系の働きをサポート
・体の潤いを補う効果が高い肺系の働きをサポート |
| ナッツ類 | アーモンド、松の実、落花生、白ごま、黒ごま | ・体を潤す
・乾燥トラブルを和らげる ・腸の乾燥による便秘に効果的 |
| 涼性・寒性食材 | キュウリ、トマト | ・熱を冷ます
・体に潤いを与える ・余分な熱を取り除く |
| 甘味と酸味の食材 | トマト、梨、レモン、メロン | ・「甘酸化陰」の効果
・自然の甘味と酸味が効果的 |
| 動物性タンパク質 | イカ、豚肉、豆乳、チーズ、ヨーグルト、牡蠣、鶏卵 | ・体に潤いを与える
・良質なタンパク質を含む ・消化しやすい形で摂取すると良い |
| 野菜・果物 | ほうれん草、アスパラガス、にんじん、レンコン、セロリ、アボカド、バナナ、苺、柿、メロン | ・体を潤す効果がある
・ビタミンやミネラルが豊富 ・抗酸化作用がある |
| 甘味料 | はちみつ | 体を潤す
– 自然な甘みで体に優しい – 抗菌作用もある |
陰虚タイプが避けるべき食材カテゴリー一覧|辛い食べ物や熱性の食材
| 食材カテゴリー | 具体例 | 理由 |
| 辛い食材 | 唐辛子、胡椒、山椒、生姜 | ・発汗を促して体を乾燥させる
・体内の熱を高める |
| 熱性の食材 | シナモン、スパイシーな食品 | ・体に熱を生む
・体の潤いを奪う |
| 乾燥した食材 | 乾燥した肉、乾燥した穀物 | ・体の水分を奪う
・消化に水分を使う ・体の乾燥を促進する |
| 刺激物 | アルコール、カフェイン | ・利尿作用で体の水分を排出する
・体を乾燥させる |
陰虚タイプ食事の取り方・ポイント
陰虚タイプの方は、体を潤す食材を中心に、熱を冷ます効果のある食材を取り入れましょう。特にネバネバした食材(山芋、オクラなど)や白色の食材(白きくらげ、ゆり根など)は体に潤いを与える効果があります。
水分補給も重要で、一度にたくさん飲むのではなく、少量ずつこまめに飲むようにしましょう。辛い食べ物や熱性の食材は発汗を促して体を乾燥させるため控えめにします。
また、就寝前の水分補給も大切ですが、寝る直前の大量の水分摂取は避け、就寝1時間前までに適量を摂るようにしましょう。
水滞タイプにおすすめの食材と食事の取り方
水滞タイプの方は、体内の水分代謝が悪く、水分が停滞している状態です。
利尿作用のある食材や水分の巡りを良くする食材を積極的に取り入れましょう。特に豆類や海藻類は水の巡りをサポートする効果が期待できます。
過剰な水分摂取は避け、体内の水分バランスを整える食事が重要です。
水滞タイプにおすすめの食材カテゴリ一ー覧|利尿作用のあるもの
| 食材カテゴリー | 具体例 | 効果・特徴 |
| 豆類 | 黒豆、小豆、緑豆 | ・体内の水分の巡りを良くする
・茹で汁をお茶として飲むと効果的 |
| 瓜類 | 冬瓜、きゅうり、ズッキーニ | ・水分の巡りを整える
・寒性のため温める食材と一緒に調理すると良い ・加熱して食べると冷やす作用を和らげられる |
| 海藻類 | 昆布、わかめ、海苔、あおさ、もずく | ・水の巡りをサポートする
・むくみの予防に効果的 ・温かいスープにして食べると良い |
| 野菜類 | もやし、とうもろこし、白菜、大根、トマト | 余分な水分を排出する
・利尿作用がある ・水分代謝を促進する |
| 果物類 | スイカ、メロン、梨 | ・水分代謝を促進する
・自然な利尿作用がある ・水分と一緒に摂りすぎに注意 |
| 貝類 | あさり、しじみ、はまぐり | ・水分代謝を促進する
・ミネラルが豊富 ・余分な水分を排出する |
| 飲み物 | ハトムギ茶、ハブ茶、烏龍茶、プーアール茶、とうもろこしのひげ茶 | ・利尿作用がある
・水分代謝を促進する ・むくみの改善に効果的 |
| 香辛料 | 生姜、シナモン、クローブ | ・体を温め水分代謝を促進する
・発汗作用がある ・水の巡りを良くする |
水滞タイプが避けるべき食材カテゴリー一覧|塩分が多いもの
| 食材カテゴリー | 具体例 | 理由 |
| 塩分の多い食品 | 塩辛い加工食品、漬物、スナック菓子 | ・体内に水分を溜め込む
・むくみを悪化させる |
| 冷たい食べ物 | 冷たい飲み物、アイスクリーム | ・体を冷やし水分代謝を悪化させる
・消化機能を低下させる ・水の巡りを滞らせる |
| 過剰な水分 | 大量の水、ジュース | ・体内の水分バランスを崩す
・腎臓や胃腸に負担をかける |
| 脂肪分の多い食品 | 揚げ物、脂身の多い肉 | ・水分代謝を悪化させる
・消化に負担をかける |
水滞タイプ食事の取り方・ポイント
水滞タイプの方は、利尿作用のある食材を取り入れた温かい料理を中心にとるのがおすすめです。特に豆類(小豆、黒豆など)や海藻類は水の巡りをサポートする効果が期待できます。塩分の摂り過ぎには注意して、薄味を心がけましょう。
水分は少量ずつこまめに摂り、一度に大量に飲むことは避けます。冷たい飲み物や食べ物は体を冷やし水分代謝を悪化させるため、温かい飲み物や食べ物を選びましょう。
また、体を温めるために適度な運動を取り入れ、汗をかくことも大切。就寝前の過剰な水分摂取は避け、夕食は早めに済ませるようにしましょう。
忙しい女性のための妊活食事スケジュール
仕事で忙しい女性でも実践できる、一日の妊活食事プランを紹介します。以下のスケジュールは、体質に関わらず基本的な栄養バランスを整えるためのものです。自分の体質に合わせて、食材を調整してみてくださいね。
朝食(7:00-8:00)
- 温かいお味噌汁
- 雑穀入りごはん
- 納豆または卵料理
- 小松菜のお浸し
朝食は一日の代謝を高めるために重要です。温かい食事を中心に、タンパク質と野菜をバランスよく摂りましょう。特に味噌汁は発酵食品であり、腸内環境を整える効果も期待できます。
昼食(12:00-13:00)
- 雑穀入りおにぎり
- 温野菜サラダ
- 鶏肉または魚の煮物
- 生姜入り温かいスープ
昼食は外食になることも多いと思いますが、できるだけ温かい食事を選びましょう。お弁当を持参する場合は、雑穀入りおにぎりと温野菜サラダ、タンパク質源を組み合わせると栄養バランスが良くなりますよ。
おやつ(15:00頃)
- ナッツ類(アーモンド、くるみなど)
- ドライフルーツ
- 温かいハーブティー
午後のおやつは、血糖値の急激な上昇を防ぎ、夕食までのエネルギー補給として重要です。ナッツ類やドライフルーツは手軽に摂取でき、栄養価も高いのでおすすめです。
夕食(18:00-19:00)
- 雑穀入りごはん
- 根菜の煮物
- 魚または豆腐料理
- 温かいスープ
夕食は消化に良い食材を中心に、早めの時間に摂ることが大切です。特に根菜類は体を温め、血行を促進する効果があるので、積極的に取り入れましょう。
就寝前(22:00頃)
- 温かい豆乳または漢方茶
就寝前の軽い飲み物は、リラックス効果があり、質の良い睡眠をサポートします。特に豆乳に含まれるイソフラボンは、女性ホルモンのバランスを整える効果が期待できます。
妊活の食事に関するよくある質問
妊活中の食事に関するよくある質問に関して、解説していきます。
Q1:妊活で妊娠しやすい食べ物は?
個々の体質によって合う食材は変わってきますが、妊娠力を高める代表的な食べ物には以下があります。
・鉄分が豊富な食品
レバー、赤身肉、ひじきなどは血を補うことで子宮内膜への栄養となり、着床環境を整える効果が期待できます。
・良質なタンパク質
肉、魚、卵、大豆製品をはじめとした良質なタンパク質は、質の良い卵子を育む栄養源となります。特に大豆イソフラボンはホルモンバランスを整える効果が期待できます。
・体を温める食品
生姜、根菜類、発酵食品は血行を促進し、子宮や卵巣の機能を高める効果が期待できます。
これらをバランスよく摂ることで、妊娠しやすい体づくりをサポートできます。
Q2:着床率を上げる食べ物は?
着床率を高めるには、子宮内膜環境を整える食材を意識するのがおすすめです。以下は、着床しやすい体づくりに役立つ食品の例です。
・ビタミンE
アーモンド、アボカドには血流改善効果があり、子宮内膜の状態を良好に保つサポートします。
・ビタミンC
キウイ、いちご、柑橘類は抗酸化作用で卵子を保護し、コラーゲン生成をサポートすることが報告されています。
・タンパク質
赤身肉、青魚は子宮内膜の質を高め、着床に必要な栄養素を提供します。
・オメガ3脂肪酸
サーモン、亜麻仁油は炎症を抑え、着床環境を整えます。
これらの食材を日々の食事に取り入れることで、着床率アップが期待できますよ。
Q3:妊活中に避けるべき食べ物は?
妊活中は以下の食品を控えることで、妊娠しやすい体づくりをサポートできます。
・生肉・生卵
食中毒リスクがあり、妊娠している場合は流産の可能性も高まります
・過剰な加工食品
添加物や塩分が多く、ホルモンバランスを乱す可能性があります
・アルコール・カフェイン
卵子や精子の質に悪影響を与える可能性があるため、適量を心がけましょう
・冷たい食品
体を冷やし血行不良の原因になり、子宮や卵巣の機能低下につながります
妊活中は、できるだけ自然な食品を選び、温かい食事を心がけることが大切です。
Q4:妊活中に納豆はだめ?
納豆は、妊活中の優れた栄養源のため積極的に摂りたい食品の一つです。
・栄養素が豊富。
葉酸・カルシウム・亜鉛が含まれており、妊娠前から必要な栄養素を補給できます。
・血流改善効果
ナットウキナーゼが子宮や卵巣への血流を促進します。
・ホルモンバランス調整
イソフラボンが排卵や生理周期の安定につながります。
1日の適切な量は、納豆1パック程度。ただし、血液をサラサラにする薬を服用している方は医師に相談をしてくださいね。
妊活に効果的な漢方と食事のアドバイスは富士堂漢方薬局にお任せ
妊活において、自分の体質に合った食事法を取り入れることは、妊娠力を高める重要なステップです。ですが、自分の体質を正確に把握し、それに合った食事法を実践することは、専門的な知識がないと難しい場合もあります。
富士堂漢方薬局では、36年以上の臨床経験を持つ専門家が、一人ひとりの体質や症状に合わせた漢方処方や具体的なアドバイスを提供しています。妊活は焦らず、体と心の健康を大切にしながら、一歩一歩進んでいきましょう。
Category
Archive
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年11月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年10月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年6月
- 2015年3月
- 2014年7月
- 2014年3月
- 2013年12月
- 2013年8月
- 2012年12月
- 2012年10月