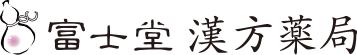2018.12.16>気管支喘息
気管支喘息(ぜんそく)解説と漢方治療
気管支喘息とは
気管支喘息とは、発作的に咳、痰が出たり、喘鳴(ゼイゼイ、ヒューヒューといった音がする)、息苦しさがあり、発作が治まると元に戻る疾患です。
咳は出るが喘鳴や息苦しさがなく、気管支を拡張させる薬が効くものを 咳喘息 といいます。
喘鳴や息苦しさがなく、喉のイガイガ感を伴った乾いた咳があり、気管支を拡張させる薬や咳止め薬が効かずにアレルギーの薬やステロイド薬が効くものを アトピー咳嗽(がいそう) といいます。
喘息の症状
喘息は、咳や痰、息苦しさや「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という喘鳴など、さまざまな症状があります。最近では咳だけの喘息(咳喘息)も増加しています。また、胸の痛みやのどに感じる違和感なども喘息の症状のひとつです。
夜間~早朝に発作性の呼吸困難、喘鳴、咳嗽が反復して起こります。
喘息の人の気道は、症状がないときでも常に炎症をおこしており、健康な人に比べて気道が狭くなって空気が通りにくくなっています。
炎症がおこっている気道はとても敏感になっていて、正常な気道なら何ともないホコリやタバコ、ストレスなどのわずかな刺激でも狭くなり、発作が起こります。 喘息の治療は、発作を起こさないための気道炎症の治療が中心となります。
日本では、喘息の患者さんは増えており、最近の調査では子どもで約10~15%、成人で約6~7%となっています。家屋の構造の変化によるアレルギー原因物質の増加、排気ガスや工場排煙などによる大気汚染、食品や住宅建材などの化学物質、長時間勤務による過労やストレスが増えたこと、清潔すぎる環境などが喘息を発症させる要因と考えられます。
喘息の方の気道は炎症により敏感になっているため、わずかな刺激でも発作が起こります。
発症のメカニズム
1.アレルギーの原因物質が体内に侵入すると、免疫反応に関わる細胞がこれを捕まえて食べます。
この物質が有害であるということを他の細胞たちに知らせ、いくつかの段階を経て免疫反応を起こすたんぱく質(抗体)が作られるようになります。
2.再びアレルギー原因物質が侵入した時に、この抗体が素早く反応し、この物質とくっつきます。
すると炎症反応に関わる細胞が刺激され、この細胞から炎症を起こす様々な物質が出てきます。その結果、喘息発作が起こります。
※また、これまでの定説とは異なったタンパク質が関わることによって、気管支喘息が発症するということも新たに分かってきました。
発作が起こる要因
□その人個人の要因
1. 遺伝子素因
2. アトピー素因
3. 気道過敏性
4. 肥満
5. 疲労、ストレス
□ 環境要因
1. 喫煙、線香の煙、強い臭いなど
2. アレルギーのもととなる物質
3. 呼吸器感染症
4. 大気汚染
5. 食物
6. 鼻炎
7. 天気、気温、気圧の変化
8. 時間帯(夜間や明け方)
病因による分類
1.アトピー型
ほとんど小児期に発症
春秋に増悪
小児喘息患者の90%以上を占める。
男児に多い。
アレルゲンに対するⅠ型アレルギーが関与
2.非アトピー型
多くは成人(40歳以上)に発症
冬に増悪しやすい
年齢上昇とともに割合は増加する(成人喘息患者の40%程度)
喫煙と肥満が関与している。気道感染に引き続いて発症することがある。
また、アレルギー性鼻炎と気管支喘息の合併例では、アレルギー性鼻炎が原因となって喘息発作が誘発されることも多いですが、漢方治療を行うことによってこれを抑制しうることがあります。
女性の気管支喘息では、月経異常や冷え症が原因となって喘息発作が誘発されることがありますが、このような病態に対しても漢方治療は有効です。
喘息でお悩みの方はぜひ一度、漢方治療をお試しください。

■漢方相談予約・お問合せ>>「お問い合わせ(LINE,WeChat,Skype,メールフォーム」
■オンライン相談もご利用ください>>「オンライン漢方相談|来店なしでお薬お届け」
□関連ブログ
>>喘息における漢方医学の診断と治療
>>病院で治らなかった喘息が漢方で改善しました|体験談
>>ストレスが原因と考えられる咳症状、2ヵ月の漢方治療で改善
Category
Archive
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年11月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年10月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年6月
- 2015年3月
- 2014年7月
- 2014年3月
- 2013年12月
- 2013年8月
- 2012年12月
- 2012年10月