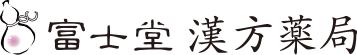更新日:2025.09.25>気管支喘息
喘息に効く漢方薬|体質に合わせた最新アプローチを専門家が解説

喘息は日本において約800万人の患者が罹患している国民病の一つで、現在治療を受けている患者数は約91.8万人(2023年調査)とされています。気管支の慢性炎症により、喘鳴(ゼイゼイ、ヒューヒュー音)、呼吸困難、咳嗽、胸部圧迫感などの症状を呈し、生活の質を大きく低下させる疾患です。この記事では「喘息の原因」「西洋医学と漢方医学での治療方法」「富士堂独自のSCI方証医学による根本治療アプローチ」について、専門家が詳しく解説します。
1.喘息とは|症状と自己チェックリスト
喘息(気管支喘息)は、気道に慢性的な炎症が生じる疾患で、一時的に気道が狭くなる発作を繰り返すことを特徴とします。炎症によって気道が敏感になり、さまざまな刺激に過剰に反応するため、咳や喘鳴(ゼーゼー・ヒューヒューという呼吸音)、呼吸困難などの症状を引き起こします。日本における総患者数は109万人(H17年厚生労働省患者調査)、そのうち男性55万人、女性54万人にのぼります。
喘息は、重症度にかかわらず、気道の慢性炎症性疾患で、主な症状は以下の通りです:
- 喘鳴:呼吸時の「ゼイゼイ」「ヒューヒュー」音(85%の患者で認められる)
- 呼吸困難:特に夜間から明け方にかけて悪化(78%の患者)
- 咳嗽:乾性または湿性の持続性咳嗽(92%の患者)
- 胸部圧迫感:胸が締め付けられるような感覚(68%の患者)
喘息かどうかわからない方は、下の表を参考にしてください。5点以上なら喘息の可能性が高いと考えられます。
☑喘息の簡易自己診断表 引用元:インフォームドコンセントのための図説シリーズ 喘息(監修:足立満)、気管支喘息の診断と重症度判定(佐野靖之)
| 3点 | ゼーゼー、ヒューヒューしていたと言われたことがある |
| 3点 | 昼間より夜間や明け方に咳き込む |
| 3点 | 息苦しくて横になれないことがある |
| 2点 | 走った時に咳き込む |
| 2点 | 疲れやストレスが溜まっている時に息苦しくなる |
| 2点 | 風邪を引くたびに2週間以上咳き込む |
| 2点 | タバコの煙で息苦しくなる |
| 2点 | 古い雑誌や新聞を片付けていると咳き込む |
| 1点 | アレルギー性鼻炎や花粉症がある |
| 1点 | 強い香水や匂いで息苦しくなる |
| 1点 | 家族にアレルギー体質の人がいる |
| 合計 | 点 |
2.喘息の原因
喘息は単一の原因で起こるものではなく、遺伝的素因(アトピー体質や免疫系の反応性の高さ) に加えて、さまざまな外部の要因が複雑に関与して発症・悪化すると考えられています。特に、アレルギー反応やウイルス感染、環境因子、心理的ストレスなどが代表的な誘因として知られています。
遺伝的素因
- 家族歴(喘息、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎など)
- アトピー体質(IgE抗体を作りやすい傾向)
アレルギー因子(アトピー型喘息)
- ダニ(患者の約70%が陽性反応を示す)
- 花粉(スギ、ヒノキ、ブタクサなど)
- カビ・真菌
- 動物の毛・フケ
- 食物アレルゲン
非アレルギー因子(非アトピー型喘息)
- ウイルス感染:発作の主な誘因で、小児の約80%、成人でも多くが感染を契機に発症
- 大気汚染物質・タバコの煙
- 薬物(アスピリンなど):成人喘息の5〜10%
- 職業性アレルゲン(化学物質、粉塵など)
- 運動誘発:小児喘息で約90%、成人喘息で約50%にみられる
環境・生活因子
- 気候変動(寒暖差、湿度の変化)
- 精神的ストレス:発作の誘因として40〜60%
- 睡眠不足・過労
- 月経周期(女性の20〜40%で関連が報告)
3.喘息の鑑別診断
下記の疾患については注意深く鑑別する必要があります。
A.上気道疾患:喉頭炎、咽頭蓋炎
B.中枢気道疾患:気道内腫瘍、気道異物、気管軟化症、気管支結核
C.肺胞領域の疾患:慢性閉塞性肺疾患(COPD)、びまん性汎細気管支炎、肺線維症、過敏性肺炎
D.循環器疾患:うっ血性心不全、肺血栓塞栓症
E.薬物による咳:アスピリン製剤やほかの薬剤
F.その他の原因:自然気胸、迷走神経刺激症状、過換気症候群、心因性咳嗽
G.アレルギー性呼吸器疾患:アレルギー性気管支症、アレルギー性肉芽腫性血管炎、好酸球性肺炎など
4.喘息の治し方|西洋薬と漢方薬
西洋薬での治療
喘息の西洋薬治療は、普段の症状をコントロールする薬と発作時に使う薬に分かれます。日常的には吸入ステロイド薬で気道の炎症を抑え、必要に応じて長時間作用する気管支拡張薬やアレルギーを抑える薬を組み合わせて使用します。発作が起きた時は、短時間作用の気管支拡張薬で素早く症状を和らげ、重症の場合は飲み薬のステロイドで対処します。
これらの薬を適切に使い分けることで、喘息症状の管理と急性発作への対応を行います。
漢方薬での治療
漢方医学では、喘息を単なる気管支の炎症としてではなく、体全体のバランスの乱れとして捉えるのが特徴です。古典的な中医学では「哮喘」と呼ばれ、たとえば以下のような体質パターンに分けて考えます。
肺腎気虚(はいじんききょ)
体力や呼吸の基盤が弱く、動くとすぐに息切れしやすいタイプ
→代表的な処方:補中益気湯、六君子湯、六味丸、八味丸
痰湿阻肺(たんしつそはい)
体内に余分な水分がたまりやすく、痰が多くてゼーゼーしやすいタイプ
→代表的な処方:二陳湯、苓甘姜味辛夏仁湯、蘇子降気湯、神秘湯
肝火犯肺(かんかはんはい)
自律神経のバランスが乱れ、特に交感神経が高ぶることで気道が刺激され、咳や喘鳴を起こしやすいタイプ
→代表的な処方:柴胡加竜骨牡蛎湯、黄連解毒湯、加味逍遥散、柴胡清肝湯
腎不納気(じんふのうき)
息を深く吸い込みにくく、呼吸が浅く不安定になりやすいタイプ
→代表的な処方:八味地黄丸、蘇子降気湯
風寒束肺(ふうかんそくはい)
風邪をひいたあとに発作が悪化しやすく、透明な痰を伴う咳が出やすいタイプ
→代表的な処方:小青竜湯、麻黄湯、麻杏甘石湯
漢方薬の飲み方や注意点
漢方薬は通常1日2~3回にわけて服用します。煎じ薬の場合は温かい状態で、エキス顆粒の場合はぬるま湯で服用するのが基本です。効果の実感には個人差がありますが、一般的に3ヶ月程度の継続服用が目安となります。
副作用は比較的少ないとされていますが、体質に合わない処方では胃腸障害や皮疹などが現れることがあります。また、他の薬剤との相互作用もあるため、必ず専門家の指導のもとで服用することが重要です。妊娠の可能性がある場合や、他疾患の治療中の方は、事前に医師や薬剤師にご相談ください。
富士堂での喘息治療
前項では、漢方医学における一般的な喘息の体質分類についてご紹介しましたが、実際の臨床においては、こうした分類のみでは治療方針を決定するうえでの情報として不十分である場合が少なくありません。
許志泉先生(富士堂漢方医学研究所・富士堂漢方薬局代表)が長年の研究及び臨床経験に基づいて提唱したSCI方証医学の視点から、より詳細な体質チェックを行っています。SCI方証医学とは、従来の中医学・漢方医学を西洋医学の概念と結合させて、「症候・体質・病」から客観的に分析するメソッドです。
この理論を活用することで、一人ひとりの体質に的確かつ精密に適合する漢方薬を選び出すことが可能となり、より効果的な漢方治療を実現しています。
SCI(証候分類)を活用した喘息タイプ分析
例えばSCI方証医学では、喘息症状に関する証を以下のようなタイプから鑑別し、それぞれに適合する生薬や傾向を判断していきます:
麻黄証:気管支の閉塞による急性期の呼吸困難や喘鳴に適応するタイプ
杏仁証:胸部の満悶・痞塞感のある喘息のタイプ
人参証:胃腸虚弱や免疫力低下による易感冒性を伴う喘息のタイプ
五味子証:冒を伴う咳・喘のタイプ
茯苓証:水液停滞による眩・悸・尿不利などを伴う咳・喘のタイプ
半夏証:心下鞕満を伴い、咽喉や気道に痰がつまるような喘息のタイプ
甘草証:鎮咳・鎮痙作用をもち、発作時の気道攣縮をやわらげるタイプ
麦門冬証:津液不足があり、痰が切れにくい咳嗽・咳込みのタイプ
柴胡証:胸から季肋下の張り・圧迫感を伴い、ストレスなどで症状が変動しやすいタイプ
上記はあくまでも具体例の一部であり、また「麻黄+半夏」などの複数の特徴が合わさった複合タイプも多く見受けられます。
喘息に使われるSCI方証医学による処方例
富士堂のSCI方証医学を活用して、例えば以下のような処方を選択します:
小青竜湯:麻黄証、乾姜証、半夏証、桂枝証などの複合による寒気・水様痰を伴う喘息に
麻杏甘石湯:咳が強く、胸に熱がこもって痰が粘りやすいタイプに
麦門冬湯:麦門冬証+半夏証による乾燥傾向・少量の痰を伴う咳に適応
半夏厚朴湯:咽喉につかえ感があり、咳や呼吸困難が不安や緊張で悪化しやすいタイプに
味麦地黄丸:地黄証があり、かつ息が浅く、呼吸が長引きがちな慢性のタイプに
六君子湯合二陳湯:胃腸が弱く、痰が多く出やすい体質に
二陳湯合麻杏甘石湯:痰が多く、さらに熱がこもって苦しくなるタイプに
玉屏風散:風邪や感染にかかりやすく、繰り返し発作を起こしやすい体質に
滋陰降火湯:のどや気道が乾燥し、空咳が出やすいタイプに
滋陰至宝湯:体力が落ち、のどや気道の乾燥・咳が長引きやすい虚弱体質の喘息に
清肺湯:黄色く粘った痰が多く、咳が激しく胸苦しさを伴うときに
血府逐瘀湯:柴胡証があり、かつ血流が滞り症状が長引きやすい慢性の喘息に
蘇子降気湯:痰が多く、胸がつかえて息苦しさを感じるタイプに 足の冷えを伴うことが多い
上記処方は、あくまでも一例となります。体質と証に合わない処方では、逆効果になることもあるため、SCI方証医学に精通した専門家のアドバイスのもとでの服用が大切です。
Q&A:よくあるご質問
Q1:漢方薬だけで喘息治療は可能ですか?
A: 軽度から中等度の喘息では漢方治療による改善が期待できますが、重篤な発作時は西洋薬による救急治療が必要です。富士堂では西洋医学との連携による統合的治療を推奨し、患者様の安全を最優先に考えていきます。
Q2:夜間に喘息が悪化するのはなぜですか?
A:夜間から明け方にかけては、副交感神経が優位になり気管支が収縮しやすく、また炎症を引き起こす物質の分泌リズムも関与しています。
漢方では、これを「陽気不足」と捉えます。陽気とは、体を温めたり呼吸を支えたりするエネルギーのことです。夜になるとこの力が弱まりやすく、体を守る力が不足することで、気道が開きにくくなり咳や息苦しさが出やすくなります。
Q3:喘息に効果的な代表的な漢方薬は何ですか?
A: 小青竜湯、麻杏甘石湯湯、麦門冬湯などが代表的ですが、個人の体質により適応が大きく異なります。富士堂のSCI方証医学による精密な証候分析により、最適な処方を決定いたします。
Q4:漢方薬による喘息治療の効果はいつ頃実感できますか?
A: 急性症状に対しては数時間から数日程度で改善が見られることが多く、根本的な体質改善には通常3-6ヶ月の継続治療が必要なことが多いです。症状の程度と個人の体質により効果の現れ方に差があります。
Q5:喘息の西洋薬と漢方薬の併用は安全ですか?
A: 多くの場合併用可能ですが、薬物相互作用に注意が必要です。特にテオフィリン製剤や抗凝固薬との併用時は慎重な監視が必要となるため、必ず服用中のお薬をお知らせください。
Q6:妊娠中・授乳中の喘息に漢方薬は使用できますか?
A: 妊娠・授乳期に比較的安全とされる漢方薬もありますが、母体と胎児・乳児への影響を十分考慮した慎重な処方選択が必要です。必ず妊娠・授乳の状況をお伝えの上、専門医にご相談ください。
Q7:漢方治療で喘息の再発は防げますか?
A: 喘息は慢性疾患のため完全な根治は困難ですが、適切な漢方による体質改善により発作頻度の減少や長期寛解の維持が期待できます。継続的な体質管理が重要です。
Q8:喘息の漢方治療中に避けるべき食べ物はありますか?
A: 冷たい食べ物や甘いもの、油っこい食事は痰湿を増やし症状を悪化させる可能性があります。また、辛すぎるものや刺激の強い香辛料も気管支を刺激することがあるため、体質に合わせた食事指導も併せて行います。
Q9:季節の変わり目に喘息が悪化しますが、漢方で対策できますか?
A: 季節の変化による喘息悪化は「風邪(ふうじゃ)」の影響と漢方ではとらえることが多いです。季節に応じた予防的な漢方薬の調整や、体の適応力を高める補気薬・補腎薬などの併用により、季節性の悪化を軽減します。
Q10: 喘息の漢方薬は子どもでも安全に服用できますか?
A: 小児喘息に対しても漢方薬を用いることは可能です。ただし、子どもは大人とは体質や発育段階が異なるため、それに合わせた処方選択が必要です。年齢や体重に応じて用量を調整し、服用しやすい剤形を工夫します。また、保護者の方と連携しながら、安全性を確認しつつ治療を進めていきます。
富士堂の漢方が選ばれる理由
オーダーメイドの治療
体質や症状を丁寧に確認し、あなたに合った処方をご提案します。
一般的な中医学や漢方医学に加えて、西洋医学的な見地や最新の研究成果を取り入れた「SCI方証医学」の理論を活用し、一人ひとりの体質をより精密に見極めていきます。
豊富な臨床経験
年間7,000名以上の患者様にご相談いただいている専門家が対応します。
安心の品質管理
信頼できる国内メーカーの生薬のみを使用し、安全性を徹底しています。
オンライン相談対応
富士堂漢方薬局は、東京の飯田橋と渋谷に2店舗を構えるほか、LINEをはじめとするオンライン相談にも対応しています。ご来店が難しい方でも、LINE・WeChat・Teamsを通じて全国どこからでもご相談いただけます。
また、漢方薬は全国へ配送可能ですので、ライフスタイルに合わせて無理なく治療を続けていただけます。
カウンセリングの流れ
ご予約 → ご相談 → 漢方薬の選定 → ご確認・お会計 → 調剤・お渡し(発送)
➤初回相談は予約優先制。お気軽にご相談ください。
■漢方相談予約・お問合せ>>「お問い合わせ(LINE,WeChat,メールフォーム)」
■オンライン相談もご利用ください>>「オンライン漢方相談|来店なしでお薬お届け」
まとめ
喘息は約800万人の日本人が罹患する代表的な呼吸器疾患で、適切な治療により症状の改善と生活の質の向上が期待できます。西洋医学では炎症の抑制と気管支拡張が治療の中心となりますが、漢方医学では体質に応じた根本的な治療アプローチが可能です。
富士堂のSCI方証医学では、従来の漢方治療に現代科学的根拠を統合することで、より確実で効果的な治療を実現しています。個人の体質と症状に応じた精密な処方選択により、西洋薬単独では困難な根本改善を目指すことができます。
喘息でお悩みの方、現在の治療に満足されていない方は、ぜひ一度富士堂にご相談ください。専門医による丁寧な診療と、科学的根拠に基づいた漢方治療で、あなたの症状改善をサポートいたします。
関連記事
Category
Archive
- 2026年2月
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年11月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年10月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年6月
- 2015年3月
- 2014年7月
- 2014年3月
- 2013年12月
- 2013年8月
- 2012年12月
- 2012年10月