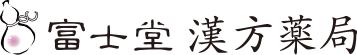Treatment病状別漢方治療

- 泌尿器・腎(尿トラブル、腎臓、性機能など)
- 1.泌尿器・腎(尿トラブル、腎臓、性機能など)
を漢方薬で治療する理由
当店には、頻尿・膀胱炎・腎機能低下・性機能障害など、腎・泌尿器系の不調に関するご相談が数多く寄せられています。ご相談される方の多くは、
「健康診断で腎機能の数値を指摘され、不安を感じている」
「病院の検査では異常がないと言われたが、つらい排尿症状が続いている」
「病院の薬だけでなく、ほかの方法でも体調を整えたい」
といったお悩みを抱えていらっしゃいます。
これらの不調は、加齢による腎機能の低下、慢性的な炎症、ホルモンバランスの変動、ストレスや生活習慣の乱れ、水分代謝の異常、骨盤底筋の衰えなど、さまざまな要因が複雑に絡み合って生じることが少なくありません。
そのため、症状のある部位だけにとらわれず、全身の水分代謝、血流、自律神経のバランス、内分泌機能を整えていくことが大切です。こうした視点からのアプローチとして、漢方治療が効果を発揮するケースも多く見られます。
漢方では、症状の表面だけでなく、その背景にある腎精の不足、水湿の停滞、気血の巡りの悪さ、慢性的な炎症や免疫機能の低下など、体全体のバランスに着目します。こうした全身的な調整を通じて、腎・泌尿器系の機能をサポートし、症状の軽減と体質の安定化を図ります。
よくあるご相談内容
頻尿、夜間頻尿、日中の頻尿、残尿感、尿が近い、尿が出にくい、尿漏れ、過活動膀胱、慢性膀胱炎、膀胱炎を繰り返す、排尿時の痛み、排尿後の違和感、尿のにごり、尿路感染症、腎結石・尿路結石、血尿、乏尿、多尿、尿の泡立ち、前立腺肥大、前立腺の不快感、男性更年期(LOH症候群)、ED(勃起不全)、精力低下、性欲の低下、精子の数や運動率の低下、男性不妊、精索静脈瘤、慢性腎臓病(CKD)、IgA腎症、ネフローゼ症候群、糸球体腎炎、腎炎、腎機能の低下、クレアチニンの上昇、尿蛋白、むくみ(腎性浮腫)、糖尿病性腎症、高血圧性腎障害 など
※女性に多いご相談例:
出産後や加齢による尿漏れ(腹圧性尿失禁)、妊娠中の膀胱炎、冷えに伴う膀胱の不調、性交後に膀胱炎を繰り返す、閉経後の頻尿や排尿痛、膀胱の違和感など
今回はその中でも特にご相談の多い以下の5項目と実際の症例などについて解説いたします。(タップで各項目へ)
- 1. 泌尿器・腎のトラブルを漢方薬で治療する理由
- 2. 泌尿器・腎のお悩みに対する富士堂の漢方治療の特徴
- 3. 症状別:漢方治療アプローチ
- ➤3-1. 頻尿・夜間頻尿
- ➤3-2. 過活動膀胱(尿意切迫感・トイレが近い)
- ➤3-3. 膀胱炎・膀胱炎を繰り返す
- ➤3-4. 男性機能障害(男性更年期障害・ED・性欲低下)
- ➤3-5. 尿漏れ(腹圧性尿失禁や加齢に伴う症状)
- 4. 実際の症例
- 5. 富士堂の漢方が選ばれる理由
- 6. ご相談・カウンセリングの流れ
- 7. 泌尿器・腎のお悩みをお持ちの方へ 〜富士堂からのメッセージ〜
漢方治療では、それぞれの体質や原因にアプローチし、根本的な治療に繋げることができます。様々な体調不良の原因を追究し、治療し、そして病気の予防まで、総合的にケアできることも漢方治療ならではの強みと言えるでしょう
富士堂漢方薬局があなたの助けになればと願っております。
2.腎・泌尿器系のお悩みに対する富士堂の漢方治療の特徴
富士堂では、頻尿・膀胱炎・腎機能低下・性機能障害など、腎・泌尿器系の不調に関するご相談を多数お受けしています。
中高年の方を中心に、女性の尿トラブルや男性更年期、若い世代の膀胱炎・性機能の悩みなど、幅広い年齢層・症状のご相談がある、非常にニーズの高い領域です。
ただ、「人には話しにくい」「病院へ行くのはためらわれる」といった声も多く、お悩みを抱えながら長く我慢されている方が少なくありません。富士堂では、そうしたお気持ちに寄り添い、安心してご相談いただける環境づくりを大切にしています。
漢方相談は完全個室のプライベート空間で行っています。また、オンライン相談にも対応しているため、ご自宅からリラックスした状態でご相談いただけます。
漢方相談では、まず丁寧な問診を通じて、症状の現れ方や生活背景、ストレスの有無、既往歴などを細かくお伺いします。さらに、舌診・脈診・腹診など、漢方医学的な視点から体全体のバランスや腎機能・水分代謝の状態を多角的に把握します。
すでに泌尿器科・腎臓内科などで治療中の方にも、西洋医学的な診断や服薬状況を尊重しながら、併用可能な形で漢方をご提案しています。たとえば、「薬を飲んでいるが排尿症状が残る」「副作用が気になる」「数値は落ち着いているけれど不調が続いている」といったケースにも対応可能です。
富士堂では、症状を一時的に抑えることだけを目的にせず、気血水の巡りを整え、腎精を補い、免疫バランスを調えることで、体質そのものの改善を目指します。
また、食養生や生活習慣のアドバイスも丁寧に行い、無理なく続けられる改善プランをご提案しています。
どうぞ一人で悩まず、気軽にご相談ください。ご自身の体と向き合いながら、少しずつ、根本から整えていきましょう。
今回はその中でも特にご相談の多い以下の5つの症状と実際の症例などについて解説いたします。
3.症状別:漢方治療アプローチ
1. 頻尿・夜間頻尿
頻尿・夜間頻尿は、日中や夜間の排尿回数が正常範囲を超えて増加する症状で、中高年の男女を中心に非常に多くの方が経験されています。一般的に、日中8回以上、夜間2回以上の排尿があると頻尿とされますが、個人差も大きく、「以前と比べて明らかに回数が増えた」「夜中に何度もトイレに起きてしまう」といった自覚症状が重要な判断基準となります。
頻尿の背景には、前立腺肥大症、膀胱炎、過活動膀胱、糖尿病、心不全、腎機能低下、薬剤の副作用、加齢による膀胱機能の変化など、実に多様な原因が存在します。特に夜間頻尿は、睡眠の質を著しく低下させ、日中の疲労感や集中力の低下、転倒リスクの増加など、生活の質(QOL)に深刻な影響を与えることが少なくありません。
また、西洋医学では、α1遮断薬、抗コリン薬、β3受容体作動薬、利尿薬などを用いた薬物療法が中心となりますが、「薬を飲んでも十分な効果を感じられない」「副作用として口の渇きやふらつきが気になる」「より根本的な体調の立て直しを目指したい」といったご相談をいただくことも少なくありません。
漢方では、加齢や冷え、ストレス、ホルモンバランスの変化など、頻尿の背景にある多様な要因を丁寧に見極め、全身の状態とあわせて総合的に判断しながら処方を組み立てていきます。
一人ひとりの体の反応や生活環境に寄り添いながら、負担の少ないかたちで、排尿のリズムや感覚を整えていくことを目指します。
① 漢方医学における頻尿・夜間頻尿の捉え方
漢方医学では、頻尿・夜間頻尿を「膀胱のみの局所的な問題」ではなく、全身の水分代謝、腎機能、自律神経、ホルモンバランス、血流状態などとの関連から包括的に理解します。特に、体の水分調節機能の低下、膀胱の温める力(温煦作用)の不足、慢性的な炎症の存在、精神的ストレスによる自律神経の乱れなどが複合的に関与していると考えられています。
特に以下のような全身症状を併発している場合、頻尿は「体全体の調子の乱れ」の一症状として現れている可能性があります。
・夜間の冷えや下半身の冷感
・慢性的な疲労感や体力の低下
・眠りが浅く、熟睡感がない
・むくみやすい、または水分が溜まりやすい
・胃腸が弱く、消化不良を起こしやすい
・ストレスを感じやすく、緊張しやすい・腰や下腹部の重だるさ
これらの症状も含めて総合的に調整することで、頻尿の根本的な改善を図るのが漢方治療の大きな特徴です。
② 頻尿・夜間頻尿の漢方治療
富士堂では、頻尿・夜間頻尿でお困りの方に対し、詳細な問診に加えて舌の状態、脈の質、腹部の緊張や冷えなどを総合的に診察し、個々の体質と症状の関連性を多角的に把握するように努めています。その上で、膀胱機能の安定化、水分代謝の正常化、腎機能のサポート、自律神経の調整などを総合的に考慮した処方を組み立てます。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■加齢や冷えが関与するタイプ(夜間頻尿、下半身の冷え、体力の低下)
加齢や体を温める力の衰え、全身の巡りの低下などが背景にある頻尿には、代謝を助け、体の深部からあたためていく漢方薬が有効です。特に、夜間に何度もトイレに起きてしまう方や、下半身の冷えを強く感じる方、足腰の力が衰えてきたと感じる方によく用いられます。
処方:八味地黄丸、牛車腎気丸、真武湯、六味地黄丸、補中益気湯 など
■膀胱炎・炎症タイプ(排尿痛、残尿感、尿の濁り)
膀胱や尿道の慢性的な炎症により頻尿が生じている場合には、抗炎症作用と利尿作用を併せ持つ処方を用います。細菌感染を繰り返しやすい方や、残尿感が強い方にも有効です。
処方:猪苓湯、五淋散、竜胆瀉肝湯、清心蓮子飲、小柴胡湯 など
■ストレス・緊張タイプ(精神的緊張、不安感、自律神経の乱れ)
緊張やストレスにより頻尿が悪化する方、自律神経の過敏性が関与している場合には、精神的な安定と膀胱機能の調整を同時に図る処方を選択します。特に外出時や会議前などの心理的プレッシャーで症状が増強する方に適しています。
処方:柴胡加竜骨牡蛎湯、桂枝加竜骨牡蛎湯、抑肝散、甘麦大棗湯 など
■水分代謝異常のタイプ(むくみ、のぼせ、めまい)
体内の水分バランスの乱れにより頻尿が生じている場合には、水分の循環と排泄を正常化する処方を使用します。むくみやのぼせ、めまいなどを伴うことが多く、全身の水分調節機能を整えることが重要です。
処方:苓桂朮甘湯、五苓散、茯苓飲、沢瀉湯、防已黄耆湯 など
■ホルモン変動、月経周期に関連するタイプ(更年期、月経周期との関連)
更年期によるホルモンバランスの変化や、月経周期に関連して頻尿が変動する場合には、ホルモン調節に働きかけながら膀胱機能を安定させる処方を用います。
処方:加味逍遙散、桂枝茯苓丸、当帰芍薬散、女神散、知柏地黄丸 など
2. 過活動膀胱(尿意切迫感・トイレが近い)
「急に強い尿意を感じて我慢できない」「トイレが近くて外出が不安」「夜中に何度も目が覚める」──これらは、過活動膀胱によく見られる症状です。特に中高年の女性に多く、生活の質に大きく影響するにもかかわらず、人に相談しづらく、一人で悩んでいる方も少なくありません。
西洋医学では薬物療法が中心ですが、「効果が実感しにくい」「副作用がつらい」「薬だけに頼りたくない」と感じている方も多くいらっしゃいます。
漢方では、過活動膀胱の背景にある「冷え」「ストレス」「加齢による身体機能の低下」などを丁寧に見極め、全身のバランスを整えることで排尿トラブルの改善をめざします。膀胱そのものだけでなく、自律神経や血流、内臓機能などにも幅広く働きかけられるのが特徴です。
長く続く排尿の不調に対し、ご自身の力を高めながら整えていきたい方にとって、漢方は有力な選択肢となり得ます。
「年のせい」とあきらめず、お気軽にご相談ください。あなたに合った方法がきっと見つかります。
① 漢方医学における過活動膀胱の理解
漢方医学では、過活動膀胱を「膠胱の機能失調」として捉えますが、その背景には全身の気血水のバランスの乱れ、腎機能の不調、肝の疏泄機能の異常、脾胃の運化機能の低下、心神の不安定など、多臓器にわたる機能的な問題が関与していると考えます。
特に、以下のような体質的特徴や随伴症状がある場合、過活動膀胱は「全身の調和の乱れ」として現れている可能性があります。
・精神的ストレスや緊張を感じやすい
・慢性的な疲労感や気力の低下
・下腹部や腰部の冷えや重だるさ
・睡眠の質が悪く、夢をよく見る
・消化機能が弱く、胃腸の不調を感じやすい
・月経不順や更年期症状を併発
これらの症状も含めて統合的に治療することで、過活動膀胱の根本的な改善と再発予防を目指すのが漢方治療のアプローチです。
② 過活動膀胱の漢方治療
富士堂では、過活動膀胱でお悩みの方に対して、症状の詳細な聞き取りはもちろん、舌診・脈診・腹診を通じて体質を総合的に評価し、個々の患者様に最適な治療方針を立てています。膀胱の過敏性の鎮静化、自律神経系の調整、全身の気血の流れの改善、精神的安定などを多面的に考慮した処方設計を心がけています。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■冷え・体力低下が関与するタイプ(下半身の冷え、夜間頻尿、全身の疲れ)
年齢を重ねることで、体を内側から温める力や下半身の血流が弱くなり、夜間の頻尿や急な尿意が起こりやすくなることがあります。特に、足腰の冷えや疲れやすさを感じている方に多く見られる傾向です。
このような場合には、体の内側から温める力を補い、下腹部の冷えや排尿機能の不安定さを整える漢方薬を用います。高齢者や虚弱傾向のある方、冷えを伴うタイプの頻尿に適しています。
処方:八味地黄丸、牛車腎気丸、真武湯、附子理中湯 など
■炎症が関与しているタイプ(尿の熱感、排尿痛、口の渇き)
膀胱や尿道に軽度〜中等度の炎症がくすぶっていることで、膀胱が過敏になり、頻尿や尿意切迫感が現れることがあります。尿に熱っぽさを感じる、排尿時にピリピリするような痛みがある、喉が渇きやすいといった症状が特徴的です。
このタイプは、体にこもった炎症をやわらげながら、尿の通りを整えるような漢方薬を用いることで、膀胱の刺激症状の改善を目指します。とくに、尿路感染を繰り返しやすい方に用いられることが多い処方です。
処方:猪苓湯、竜胆瀉肝湯、五淋散、清心蓮子飲など
■ストレスや感情の影響を受けやすいタイプ(緊張、不安、イライラ、月経不順)
精神的ストレスや緊張が続くと、自律神経のバランスが乱れ、膀胱が過敏になって頻尿や尿意切迫感などの症状が悪化しやすくなります。感情の起伏やイライラ、不安感と症状の変動が連動している方や、女性では月経前後に悪化するケースも少なくありません。
このタイプには、心身を落ち着けて自律神経の興奮を鎮めるとともに、気の巡りを整えてストレスの影響をやわらげる漢方薬が有効です。
処方:柴胡加竜骨牡蛎湯、抑肝散、加味逍遙散、桂枝加竜骨牡蛎湯、四逆散、香蘇散 など
■消化力や代謝の低下が関与するタイプ(むくみ、消化不良、倦怠感)
加齢や体力の低下により、消化吸収の力や水分の代謝機能が落ちてくると、体内の余分な水分がうまく処理できず、膀胱が過敏に反応してしまうことがあります。全身のだるさ、胃腸の不調、むくみなどを伴いやすいのが特徴です。このようなタイプには、胃腸の働きを助けながら、体内の余分な水分を調整し、膀胱の負担をやわらげる漢方薬が用いられます。
処方:補中益気湯、六君子湯、茯苓飲、参苓白朮散、清心蓮子飲 など
これらの処方は、単に過活動膀胱の症状を抑制するだけでなく、「なぜ膀胱が過敏になりやすいのか」という体質的背景を改善することで、症状の軽減と再発防止の両方を目指した治療となります。
「トイレのことが気になって外出できない」「夜中に何度も起きてしまう」「薬を飲んでも思うような効果が得られない」—— そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。お一人お一人の症状や体質に合わせた、きめ細やかな治療をご提案いたします。
3. 膀胱炎・膀胱炎を繰り返す
膀胱炎は、膀胱内に細菌が侵入・増殖することで起こる感染症で、排尿時の痛みや灼熱感、頻尿、残尿感、下腹部の不快感、尿の濁りや血尿などを伴います。特に女性は尿道が短いため、男性よりも感染を起こしやすいとされています。
急性膀胱炎は抗生物質で比較的早く改善しますが、問題となるのは慢性膀胱炎や再発性膀胱炎です。症状が長く続いたり、一度治っても数週間〜数ヶ月で再発を繰り返したりするケースが多く、身体的にも精神的にも大きな負担になります。
再発の背景には、治療の不完全さ、細菌の薬剤耐性、膀胱や免疫機能の低下、排尿習慣、性行為、ストレス、疲労、冷え、ホルモン変化など、さまざまな要因が関与していると考えられます。また、「また再発するのでは」といった不安感がストレスとなり、悪循環を生むことも少なくありません。
こうした背景から、免疫力の回復や再発予防を目的とした漢方治療への関心が高まっています。漢方では、感染への抵抗力を高めつつ、膀胱の炎症を鎮め、再発しにくい体の状態を整えることを目指します。
① 漢方医学における膀胱炎の捉え方
漢方医学では、膀胱炎を単純な「細菌感染」として捉えるだけでなく、「なぜ感染しやすくなっているのか」「なぜ治りにくいのか」という体質的背景に注目します。膀胱炎を繰り返す方には、湿熱の停滞、冷え、気血の不足、免疫機能の低下、ストレスによる気の鬱滞などの体質的問題が潜んでいることが多いと考えます。
特に、以下のような症状や体質的特徴がある場合、膀胱炎が「体全体の調子の乱れ」の一症状として現れている可能性があります。
・慢性的な疲労感や体力不足を感じる
・冷え性で、特に下半身が冷えやすい
・ストレスを感じやすく、精神的に疲れやすい
・胃腸が弱く、下痢や便秘を起こしやすい
・風邪をひきやすく、治りにくい
・月経不順や生理痛がある
これらの要因も含めて総合的に体質を改善することで、膀胱炎の治癒促進と再発防止を図るのが漢方治療の特色です。
② 膀胱炎の漢方治療
富士堂では、膀胱炎にお悩みの方に対して、現在の症状の詳細な把握に加え、舌の色調・苔の状態、脈の強さ・質、腹部の緊張・冷え・圧痛などを丁寧に診察し、個々の体質と炎症パターンを見極めています。その上で、炎症を鎮めることや排尿のスムーズさの改善、体調の安定化や体力回復などを総合的に考慮し、その方に合った処方を選んでいます。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■急性の炎症症状が目立つタイプの膀胱炎(排尿痛、尿の濁り、口の渇き)
排尿時に焼けつくような強い痛みがあり、尿が濁る、尿に熱っぽさを感じる、喉が渇く―こうした症状がみられる場合、膀胱や尿道に急性の炎症反応が起きている可能性があります。
漢方では、こうした状態を体内に「熱」と「余分な水分(老廃物)」がこもっている状態と捉え、熱を冷ましつつ、炎症性の老廃物を排出するような処方を用います。抗菌薬で一時的に症状が落ち着いても、再発を繰り返す方や、膀胱の炎症が長引きやすい方にとっても、有効な選択肢となります。
4. 男性機能障害(男性更年期障害・ED・性欲低下)
男性機能障害は、ED(勃起不全)、性欲の低下、射精障害、男性更年期障害(LOH症候群:Late-Onset Hypogonadism)などを含む包括的な概念で、40歳以降の中高年男性において増加傾向にあります。これらの症状は、テストステロンなどの男性ホルモンの低下、血管機能の劣化、神経系の変化、心理的要因、生活習慣病の影響などが複合的に関与して生じると考えられています。
特にEDは、「満足な性行為を行うのに十分な勃起が得られない、または維持できない状態」と定義され、日本国内では成人男性の約4人に1人が何らかの程度のEDを経験しているとの報告もあります。また、男性更年期障害では、性機能の低下に加えて、疲労感、やる気の低下、イライラ、不眠、筋力低下、記憶力の減退、うつ症状などの多彩な症状が現れることがあります。
これらの症状は、男性の自信や自尊心に深く関わる極めてデリケートな問題であり、「誰にも相談できない」「恥ずかしくて病院に行けない」と一人で悩みを抱え込んでしまう方が非常に多いのが現実です。また、パートナーとの関係性にも影響を及ぼすため、夫婦間のコミュニケーションにも支障をきたすケースも少なくありません。
しかし、男性機能障害は決して珍しい症状ではなく、適切な治療やケアにより改善が期待できる分野でもあります。近年では、このような男性特有の悩みについて理解が深まり、治療選択肢も多様化してきています。
西洋医学的には、PDE5阻害薬(シルデナフィル、タダラフィルなど)、男性ホルモン補充療法、心理カウンセリングなどの治療法がありますが、「薬の効果が不十分」「副作用が心配」「根本的な体力向上を図りたい」といったご希望をお持ちの方も多くいらっしゃいます。
そのような中で、男性機能障害に対する「全身の活力向上」「ホルモンバランスの自然な調整」「心身の総合的な強化」を目指した漢方治療は1つの選択肢となります。漢方薬には、古来より男性機能をサポートしてきた豊富な処方があり、個々の体質や症状に合わせた細やかな調整が可能です。
① 漢方医学における男性機能障害の考え方
漢方医学では、男性機能障害を「腎精の不足」を中心とした全身的なエネルギー低下として理解します。漢方における「腎」は、生殖機能をはじめ、成長・発育・老化などを担う重要な機能とされており、その働きが低下すると、性機能だけでなく、体力・気力・免疫力・記憶力など、全身のさまざまな側面に影響が及ぶと考えられています。
以下のような症状や体質的な傾向がみられる場合、男性機能の不調は、単なる局所的な問題ではなく、全身状態や心身のバランスの乱れの一環としてあらわれていると捉えます。
・慢性的な疲労感や倦怠感
・腰や膝の脱力感、痛み
・夜間頻尿や残尿感
・冷えや寒がりの傾向
・筋力の低下、体力の衰え
・不眠や眠りの浅さ
これらの症状も含めて全身的に調整することで、男性機能の回復と維持を図るのが漢方治療のアプローチです。
② 男性機能障害の漢方治療
富士堂では、男性機能に関するお悩みをお持ちの方に対して、プライバシーに十分配慮しながら、症状の詳細、生活習慣、ストレス状況、既往歴などを丁寧にお伺いします。また、舌診・脈診・腹診により体質を総合的に判断し、個々の方に最適な治療方針を立てています。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■冷えや体力の衰えが目立つタイプ(冷え、体力低下、夜間頻尿、腰痛)
身体を温め、活動を支える力が弱くなっていると、冷えを強く感じたり、夜間の排尿が増えたり、全身の活力が落ちて性機能も低下しやすくなります。
こうした状態では、代謝や血行を促進し、体の内側から温めることで、性機能の衰えを改善し、勃起力や性欲の回復にもつなげていく漢方薬を用います。
処方:八味地黄丸、牛車腎気丸、参馬補腎丸、参茸補血丸、真武湯など
■体の潤い不足や熱感が気になるタイプ(のぼせ、口渇、不眠、イライラ)
心身の疲労やストレスの蓄積などにより、体に必要な潤いが不足し、熱がこもりやすくなっている状態です。のぼせや寝つきの悪さ、口の渇き、イライラ感などがみられる方には、体の内側から熱を鎮め、心身を落ち着ける処方を用います。
処方:六味地黄丸、知柏地黄丸、杞菊地黄丸、温清飲、亀板配合製品など
■体力や活力が全体的に低下しているタイプ(疲労感、食欲不振、貧血傾向、集中力低下)
慢性的な疲れや栄養不足により、体全体の活力や臓器の働きが低下している場合には、体力の回復と栄養状態の改善を同時に図る処方を使用します。虚弱体質や病後の回復期にも有効です。
処方:十全大補湯、人参養栄湯、補中益気湯、帰脾湯など
■ストレスや精神的な緊張が影響しているタイプ(ストレス、イライラ、精神的緊張)
精神的な緊張や感情の抑圧が続くと、自律神経の乱れや血流の停滞などを引き起こし、性機能にも影響が出ることがあります。ストレスが強く、気分がすっきりしない方には、気持ちを整え、精神的安定を促す処方が適しています。
処方:柴胡加竜骨牡蠣湯、桂枝加竜骨牡蠣湯、逍遙散、四逆散、加味逍遙散など
■血流の悪さが関与しているタイプ(血行不良、肩こり、頭痛、下肢の冷え)
血の巡りが滞ることで、陰部への血流が不十分になり、機能の低下を引き起こしているケースです。とくに、冷えやこり、慢性的な頭痛がある方、生活習慣病を抱える方に多くみられます。血流を促進し、全身の循環機能を改善する処方を使用します。
処方:冠心逐瘀丹、血府逐瘀湯、桂枝茯苓丸、桃核承気湯など
富士堂では、男性機能に関するご相談について、完全にプライベートが保たれる個室でのご相談環境を整えており、他の患者様と顔を合わせることなく、安心してお話しいただけます。また、ご自宅からご利用いただけるオンライン相談システムも充実しており、より気軽にご相談いただけるよう配慮しております。
富士堂では、不安な気持ちにも十分に配慮しながら、お一人おひとりの体質や症状に応じた丁寧な対応を心がけています。「話してよかった」と感じていただけるよう、専門知識と豊富な経験をもとに、誠実にサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
5. 尿漏れ(腹圧性尿失禁や加齢に伴う症状)
尿漏れ(尿失禁)は、自分の意思とは関係なく尿が漏れてしまう状態で、特に女性に多く見られる症状です。その中でも最も頻度が高いのが「腹圧性尿失禁」で、咳やくしゃみ、重いものを持ち上げる、走る、笑うなどの際に腹圧が上昇することで尿が漏れてしまうものです。これは、出産や加齢により骨盤底筋群が緩んだり、尿道を支える組織が弱くなったりすることが主な原因とされています。
女性の尿失禁は、出産経験者で約30-40%、未経験者でも約10-20%に認められ、年齢と共に有病率が上昇する傾向があります。また、閉経後にはエストロゲンの低下により尿道や膀胱周囲の組織が萎縮し、症状がさらに悪化することも少なくありません。
尿漏れは身体的な不快感だけでなく、「外出先で漏れてしまったらどうしよう」「運動ができない」「笑うことを控えてしまう」といった行動制限や、「年を取った証拠だ」「女性として恥ずかしい」といった精神的な負担も大きな問題となります。しかし、このような悩みは非常にプライベートな内容であるため、家族や親しい友人にさえ相談できずに一人で抱え込んでしまう方が大変多いのが現状です。
富士堂では、他の方と接触することのない個室での相談や、ご自宅でゆっくりとお話しいただけるオンライン相談をご用意しております。女性スタッフも在籍しており、同じ女性として共感を持ってお話をお聞きできる環境も整えております。
西洋医学では、薬による治療や骨盤底筋のトレーニング、場合によっては手術などが行われますが、「手術は避けたい」「薬だけでは効果が不十分」「もっと自然な方法で改善したい」「体質から見直したい」といったご相談を多くいただきます。
そのようなご希望に対し、骨盤底筋を自然に強化し、全身の巡りやホルモンバランスを整えるための漢方治療は1つの選択肢となります。漢方では、局所的な症状だけでなく、全身の活力や体質を改善することで、尿漏れの根本的な改善を目指していきます。
① 漢方医学における尿漏れの考え方
漢方医学では、尿漏れを「加齢や体力低下にともなう身体機能の衰え」や「内臓の支える力や代謝・巡りのバランスの乱れ」といった体質的な問題が背景にある状態と考えます。特に、排尿をコントロールするための筋力・内臓の働き・自律神経のバランスがうまく保たれていないことが関係しているとされています。
以下のような体質的な特徴がみられる場合、尿漏れは全身の調整機能の低下や体の土台の弱りとしてあらわれている可能性があります。
・慢性的な疲労感や気力の低下
・胃腸が弱く、下痢をしやすい
・腰や下腹部の重だるさ
・手足の冷えや寒がり
・月経量の減少や生理不順
・肌の乾燥や老化
・夜間頻尿や残尿感
これらの症状を含めて体質全体を丁寧に整え、排尿機能を支える力を体の内側から高めていくのが、漢方治療の特徴です。
② 尿漏れの漢方治療
富士堂では、尿漏れでお悩みの方に対して、症状の程度や現れ方、女性には出産歴、月経状況、更年期症状の有無などを詳しくお伺いし、舌診・脈診・腹診を通じて体質を多角的に評価しています。その上で、骨盤底筋の機能向上、全身の気血の充実、ホルモンバランスの調整などを考慮した処方を選択します。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■冷えや体力の低下が背景にあるタイプの尿漏れ(冷え、夜間頻尿、腰痛、体力低下)
体を温める力や筋力・代謝が低下することで、膀胱の働きや尿を我慢する力が弱くなり、尿漏れが起こりやすくなります。特に高齢者や冷えやすい体質の方、体力が落ちている方に多く見られます。
処方:八味地黄丸、牛車腎気丸、真武湯、人参湯、附子理中湯など
■胃腸が弱く、内臓を支える力が低下しているタイプ(疲労感、胃腸虚弱、内臓下垂感)
消化吸収力の低下や体の支える力の弱さによって、骨盤底の筋肉や内臓が下がりやすくなり、尿漏れが起こることがあります。出産後や慢性的に疲れやすい方に多く見られます。
処方:補中益気湯、参苓白朮散、六君子湯、香砂六君子湯など
■ 熱感・乾燥が目立つタイプ(のぼせ、口渇、更年期症状、皮膚乾燥)
女性ホルモンの変化により、体内の潤いが不足し、のぼせ・ほてり・乾燥などの症状が起こると、膀胱の不安定さや尿漏れにつながることがあります。更年期以降の女性に多く見られる傾向です。
処方:六味地黄丸、知柏地黄丸、杞菊地黄丸、亀板配合製品など
■栄養不足や体の基礎的な力が弱っているタイプ(貧血傾向、月経過少、疲れやすい)
体をめぐる栄養やエネルギーが不足していると、全身の機能が低下し、膀胱の働きや尿をコントロールする力が弱まります。産後や病後の回復が遅れている方にもよく見られます。
処方:十全大補湯、人参養栄湯、帰脾湯、婦宝当帰膠、芎帰調血飲第一加減など
■ストレスや自律神経の乱れが関与するタイプ(ストレス、イライラ、月経前症候群)
精神的な緊張やストレスによって自律神経のバランスが乱れると、膀胱の働きにも影響が出やすくなり、尿意のコントロールが難しくなることがあります。仕事や育児などによる精神的負担の大きい方に多く見られます。
処方:加味逍遙散、柴胡加竜骨牡蠣湯、抑肝散、四逆散、香蘇散など
これらの処方は、単に尿漏れの症状を改善するだけでなく、「なぜ尿が漏れやすくなったのか」という根本的な体質を立て直すことで、長期的な症状の安定化を目指した治療となります。
「外出が不安で積極的になれない」「運動を控えるようになった」「このまま悪化するのではないかと心配」—— そのようなお悩みをお持ちの方は、お一人で悩まずにぜひご相談ください。お一人お一人の体質や生活環境を理解した上で、最適な改善策をご提案いたします。
4. 男性機能障害(男性更年期障害・ED・性欲低下)
男性機能障害は、ED(勃起不全)、性欲の低下、射精障害、男性更年期障害(LOH症候群:Late-Onset Hypogonadism)などを含む包括的な概念で、40歳以降の中高年男性において増加傾向にあります。これらの症状は、テストステロンなどの男性ホルモンの低下、血管機能の劣化、神経系の変化、心理的要因、生活習慣病の影響などが複合的に関与して生じると考えられています。
特にEDは、「満足な性行為を行うのに十分な勃起が得られない、または維持できない状態」と定義され、日本国内では成人男性の約4人に1人が何らかの程度のEDを経験しているとの報告もあります。また、男性更年期障害では、性機能の低下に加えて、疲労感、やる気の低下、イライラ、不眠、筋力低下、記憶力の減退、うつ症状などの多彩な症状が現れることがあります。
これらの症状は、男性の自信や自尊心に深く関わる極めてデリケートな問題であり、「誰にも相談できない」「恥ずかしくて病院に行けない」と一人で悩みを抱え込んでしまう方が非常に多いのが現実です。また、パートナーとの関係性にも影響を及ぼすため、夫婦間のコミュニケーションにも支障をきたすケースも少なくありません。
しかし、男性機能障害は決して珍しい症状ではなく、適切な治療やケアにより改善が期待できる分野でもあります。近年では、このような男性特有の悩みについて理解が深まり、治療選択肢も多様化してきています。
西洋医学的には、PDE5阻害薬(シルデナフィル、タダラフィルなど)、男性ホルモン補充療法、心理カウンセリングなどの治療法がありますが、「薬の効果が不十分」「副作用が心配」「根本的な体力向上を図りたい」といったご希望をお持ちの方も多くいらっしゃいます。
そのような中で、男性機能障害に対する「全身の活力向上」「ホルモンバランスの自然な調整」「心身の総合的な強化」を目指した漢方治療は1つの選択肢となります。漢方薬には、古来より男性機能をサポートしてきた豊富な処方があり、個々の体質や症状に合わせた細やかな調整が可能です。
① 漢方医学における男性機能障害の考え方
漢方医学では、男性機能障害を「腎精の不足」を中心とした全身的なエネルギー低下として理解します。漢方における「腎」は、生殖機能をはじめ、成長・発育・老化などを担う重要な機能とされており、その働きが低下すると、性機能だけでなく、体力・気力・免疫力・記憶力など、全身のさまざまな側面に影響が及ぶと考えられています。
以下のような症状や体質的な傾向がみられる場合、男性機能の不調は、単なる局所的な問題ではなく、全身状態や心身のバランスの乱れの一環としてあらわれていると捉えます。
・慢性的な疲労感や倦怠感
・腰や膝の脱力感、痛み
・夜間頻尿や残尿感
・冷えや寒がりの傾向
・筋力の低下、体力の衰え
・不眠や眠りの浅さ
これらの症状も含めて全身的に調整することで、男性機能の回復と維持を図るのが漢方治療のアプローチです。
② 男性機能障害の漢方治療
富士堂では、男性機能に関するお悩みをお持ちの方に対して、プライバシーに十分配慮しながら、症状の詳細、生活習慣、ストレス状況、既往歴などを丁寧にお伺いします。また、舌診・脈診・腹診により体質を総合的に判断し、個々の方に最適な治療方針を立てています。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■冷えや体力の衰えが目立つタイプ(冷え、体力低下、夜間頻尿、腰痛)
身体を温め、活動を支える力が弱くなっていると、冷えを強く感じたり、夜間の排尿が増えたり、全身の活力が落ちて性機能も低下しやすくなります。
こうした状態では、代謝や血行を促進し、体の内側から温めることで、性機能の衰えを改善し、勃起力や性欲の回復にもつなげていく漢方薬を用います。
処方:八味地黄丸、牛車腎気丸、参馬補腎丸、参茸補血丸、真武湯など
■体の潤い不足や熱感が気になるタイプ(のぼせ、口渇、不眠、イライラ)
心身の疲労やストレスの蓄積などにより、体に必要な潤いが不足し、熱がこもりやすくなっている状態です。のぼせや寝つきの悪さ、口の渇き、イライラ感などがみられる方には、体の内側から熱を鎮め、心身を落ち着ける処方を用います。
処方:六味地黄丸、知柏地黄丸、杞菊地黄丸、温清飲、亀板配合製品など
■体力や活力が全体的に低下しているタイプ(疲労感、食欲不振、貧血傾向、集中力低下)
慢性的な疲れや栄養不足により、体全体の活力や臓器の働きが低下している場合には、体力の回復と栄養状態の改善を同時に図る処方を使用します。虚弱体質や病後の回復期にも有効です。
処方:十全大補湯、人参養栄湯、補中益気湯、帰脾湯など
■ストレスや精神的な緊張が影響しているタイプ(ストレス、イライラ、精神的緊張)
精神的な緊張や感情の抑圧が続くと、自律神経の乱れや血流の停滞などを引き起こし、性機能にも影響が出ることがあります。ストレスが強く、気分がすっきりしない方には、気持ちを整え、精神的安定を促す処方が適しています。
処方:柴胡加竜骨牡蠣湯、桂枝加竜骨牡蠣湯、逍遙散、四逆散、加味逍遙散など
■血流の悪さが関与しているタイプ(血行不良、肩こり、頭痛、下肢の冷え)
血の巡りが滞ることで、陰部への血流が不十分になり、機能の低下を引き起こしているケースです。とくに、冷えやこり、慢性的な頭痛がある方、生活習慣病を抱える方に多くみられます。血流を促進し、全身の循環機能を改善する処方を使用します。
処方:冠心逐瘀丹、血府逐瘀湯、桂枝茯苓丸、桃核承気湯など
富士堂では、男性機能に関するご相談について、完全にプライベートが保たれる個室でのご相談環境を整えており、他の患者様と顔を合わせることなく、安心してお話しいただけます。また、ご自宅からご利用いただけるオンライン相談システムも充実しており、より気軽にご相談いただけるよう配慮しております。
富士堂では、不安な気持ちにも十分に配慮しながら、お一人おひとりの体質や症状に応じた丁寧な対応を心がけています。「話してよかった」と感じていただけるよう、専門知識と豊富な経験をもとに、誠実にサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
5. 尿漏れ(腹圧性尿失禁や加齢に伴う症状)
尿漏れ(尿失禁)は、自分の意思とは関係なく尿が漏れてしまう状態で、特に女性に多く見られる症状です。その中でも最も頻度が高いのが「腹圧性尿失禁」で、咳やくしゃみ、重いものを持ち上げる、走る、笑うなどの際に腹圧が上昇することで尿が漏れてしまうものです。これは、出産や加齢により骨盤底筋群が緩んだり、尿道を支える組織が弱くなったりすることが主な原因とされています。
女性の尿失禁は、出産経験者で約30-40%、未経験者でも約10-20%に認められ、年齢と共に有病率が上昇する傾向があります。また、閉経後にはエストロゲンの低下により尿道や膀胱周囲の組織が萎縮し、症状がさらに悪化することも少なくありません。
尿漏れは身体的な不快感だけでなく、「外出先で漏れてしまったらどうしよう」「運動ができない」「笑うことを控えてしまう」といった行動制限や、「年を取った証拠だ」「女性として恥ずかしい」といった精神的な負担も大きな問題となります。しかし、このような悩みは非常にプライベートな内容であるため、家族や親しい友人にさえ相談できずに一人で抱え込んでしまう方が大変多いのが現状です。
富士堂では、他の方と接触することのない個室での相談や、ご自宅でゆっくりとお話しいただけるオンライン相談をご用意しております。女性スタッフも在籍しており、同じ女性として共感を持ってお話をお聞きできる環境も整えております。
西洋医学では、薬による治療や骨盤底筋のトレーニング、場合によっては手術などが行われますが、「手術は避けたい」「薬だけでは効果が不十分」「もっと自然な方法で改善したい」「体質から見直したい」といったご相談を多くいただきます。
そのようなご希望に対し、骨盤底筋を自然に強化し、全身の巡りやホルモンバランスを整えるための漢方治療は1つの選択肢となります。漢方では、局所的な症状だけでなく、全身の活力や体質を改善することで、尿漏れの根本的な改善を目指していきます。
① 漢方医学における尿漏れの考え方
漢方医学では、尿漏れを「加齢や体力低下にともなう身体機能の衰え」や「内臓の支える力や代謝・巡りのバランスの乱れ」といった体質的な問題が背景にある状態と考えます。特に、排尿をコントロールするための筋力・内臓の働き・自律神経のバランスがうまく保たれていないことが関係しているとされています。
以下のような体質的な特徴がみられる場合、尿漏れは全身の調整機能の低下や体の土台の弱りとしてあらわれている可能性があります。
・慢性的な疲労感や気力の低下
・胃腸が弱く、下痢をしやすい
・腰や下腹部の重だるさ
・手足の冷えや寒がり
・月経量の減少や生理不順
・肌の乾燥や老化
・夜間頻尿や残尿感
これらの症状を含めて体質全体を丁寧に整え、排尿機能を支える力を体の内側から高めていくのが、漢方治療の特徴です。
② 尿漏れの漢方治療
富士堂では、尿漏れでお悩みの方に対して、症状の程度や現れ方、女性には出産歴、月経状況、更年期症状の有無などを詳しくお伺いし、舌診・脈診・腹診を通じて体質を多角的に評価しています。その上で、骨盤底筋の機能向上、全身の気血の充実、ホルモンバランスの調整などを考慮した処方を選択します。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■冷えや体力の低下が背景にあるタイプの尿漏れ(冷え、夜間頻尿、腰痛、体力低下)
体を温める力や筋力・代謝が低下することで、膀胱の働きや尿を我慢する力が弱くなり、尿漏れが起こりやすくなります。特に高齢者や冷えやすい体質の方、体力が落ちている方に多く見られます。
処方:八味地黄丸、牛車腎気丸、真武湯、人参湯、附子理中湯など
■胃腸が弱く、内臓を支える力が低下しているタイプ(疲労感、胃腸虚弱、内臓下垂感)
消化吸収力の低下や体の支える力の弱さによって、骨盤底の筋肉や内臓が下がりやすくなり、尿漏れが起こることがあります。出産後や慢性的に疲れやすい方に多く見られます。
処方:補中益気湯、参苓白朮散、六君子湯、香砂六君子湯など
■ 熱感・乾燥が目立つタイプ(のぼせ、口渇、更年期症状、皮膚乾燥)
女性ホルモンの変化により、体内の潤いが不足し、のぼせ・ほてり・乾燥などの症状が起こると、膀胱の不安定さや尿漏れにつながることがあります。更年期以降の女性に多く見られる傾向です。
処方:六味地黄丸、知柏地黄丸、杞菊地黄丸、亀板配合製品など
■栄養不足や体の基礎的な力が弱っているタイプ(貧血傾向、月経過少、疲れやすい)
体をめぐる栄養やエネルギーが不足していると、全身の機能が低下し、膀胱の働きや尿をコントロールする力が弱まります。産後や病後の回復が遅れている方にもよく見られます。
処方:十全大補湯、人参養栄湯、帰脾湯、婦宝当帰膠、芎帰調血飲第一加減など
■ストレスや自律神経の乱れが関与するタイプ(ストレス、イライラ、月経前症候群)
精神的な緊張やストレスによって自律神経のバランスが乱れると、膀胱の働きにも影響が出やすくなり、尿意のコントロールが難しくなることがあります。仕事や育児などによる精神的負担の大きい方に多く見られます。
処方:加味逍遙散、柴胡加竜骨牡蠣湯、抑肝散、四逆散、香蘇散など
これらの処方は、単に尿漏れの症状を改善するだけでなく、「なぜ尿が漏れやすくなったのか」という根本的な体質を立て直すことで、長期的な症状の安定化を目指した治療となります。
「外出が不安で積極的になれない」「運動を控えるようになった」「このまま悪化するのではないかと心配」—— そのようなお悩みをお持ちの方は、お一人で悩まずにぜひご相談ください。お一人お一人の体質や生活環境を理解した上で、最適な改善策をご提案いたします。
4. 男性機能障害(男性更年期障害・ED・性欲低下)
男性機能障害は、ED(勃起不全)、性欲の低下、射精障害、男性更年期障害(LOH症候群:Late-Onset Hypogonadism)などを含む包括的な概念で、40歳以降の中高年男性において増加傾向にあります。これらの症状は、テストステロンなどの男性ホルモンの低下、血管機能の劣化、神経系の変化、心理的要因、生活習慣病の影響などが複合的に関与して生じると考えられています。
特にEDは、「満足な性行為を行うのに十分な勃起が得られない、または維持できない状態」と定義され、日本国内では成人男性の約4人に1人が何らかの程度のEDを経験しているとの報告もあります。また、男性更年期障害では、性機能の低下に加えて、疲労感、やる気の低下、イライラ、不眠、筋力低下、記憶力の減退、うつ症状などの多彩な症状が現れることがあります。
これらの症状は、男性の自信や自尊心に深く関わる極めてデリケートな問題であり、「誰にも相談できない」「恥ずかしくて病院に行けない」と一人で悩みを抱え込んでしまう方が非常に多いのが現実です。また、パートナーとの関係性にも影響を及ぼすため、夫婦間のコミュニケーションにも支障をきたすケースも少なくありません。
しかし、男性機能障害は決して珍しい症状ではなく、適切な治療やケアにより改善が期待できる分野でもあります。近年では、このような男性特有の悩みについて理解が深まり、治療選択肢も多様化してきています。
西洋医学的には、PDE5阻害薬(シルデナフィル、タダラフィルなど)、男性ホルモン補充療法、心理カウンセリングなどの治療法がありますが、「薬の効果が不十分」「副作用が心配」「根本的な体力向上を図りたい」といったご希望をお持ちの方も多くいらっしゃいます。
そのような中で、男性機能障害に対する「全身の活力向上」「ホルモンバランスの自然な調整」「心身の総合的な強化」を目指した漢方治療は1つの選択肢となります。漢方薬には、古来より男性機能をサポートしてきた豊富な処方があり、個々の体質や症状に合わせた細やかな調整が可能です。
① 漢方医学における男性機能障害の考え方
漢方医学では、男性機能障害を「腎精の不足」を中心とした全身的なエネルギー低下として理解します。漢方における「腎」は、生殖機能をはじめ、成長・発育・老化などを担う重要な機能とされており、その働きが低下すると、性機能だけでなく、体力・気力・免疫力・記憶力など、全身のさまざまな側面に影響が及ぶと考えられています。
以下のような症状や体質的な傾向がみられる場合、男性機能の不調は、単なる局所的な問題ではなく、全身状態や心身のバランスの乱れの一環としてあらわれていると捉えます。
・慢性的な疲労感や倦怠感
・腰や膝の脱力感、痛み
・夜間頻尿や残尿感
・冷えや寒がりの傾向
・筋力の低下、体力の衰え
・不眠や眠りの浅さ
これらの症状も含めて全身的に調整することで、男性機能の回復と維持を図るのが漢方治療のアプローチです。
② 男性機能障害の漢方治療
富士堂では、男性機能に関するお悩みをお持ちの方に対して、プライバシーに十分配慮しながら、症状の詳細、生活習慣、ストレス状況、既往歴などを丁寧にお伺いします。また、舌診・脈診・腹診により体質を総合的に判断し、個々の方に最適な治療方針を立てています。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■冷えや体力の衰えが目立つタイプ(冷え、体力低下、夜間頻尿、腰痛)
身体を温め、活動を支える力が弱くなっていると、冷えを強く感じたり、夜間の排尿が増えたり、全身の活力が落ちて性機能も低下しやすくなります。
こうした状態では、代謝や血行を促進し、体の内側から温めることで、性機能の衰えを改善し、勃起力や性欲の回復にもつなげていく漢方薬を用います。
処方:八味地黄丸、牛車腎気丸、参馬補腎丸、参茸補血丸、真武湯など
■体の潤い不足や熱感が気になるタイプ(のぼせ、口渇、不眠、イライラ)
心身の疲労やストレスの蓄積などにより、体に必要な潤いが不足し、熱がこもりやすくなっている状態です。のぼせや寝つきの悪さ、口の渇き、イライラ感などがみられる方には、体の内側から熱を鎮め、心身を落ち着ける処方を用います。
処方:六味地黄丸、知柏地黄丸、杞菊地黄丸、温清飲、亀板配合製品など
■体力や活力が全体的に低下しているタイプ(疲労感、食欲不振、貧血傾向、集中力低下)
慢性的な疲れや栄養不足により、体全体の活力や臓器の働きが低下している場合には、体力の回復と栄養状態の改善を同時に図る処方を使用します。虚弱体質や病後の回復期にも有効です。
処方:十全大補湯、人参養栄湯、補中益気湯、帰脾湯など
■ストレスや精神的な緊張が影響しているタイプ(ストレス、イライラ、精神的緊張)
精神的な緊張や感情の抑圧が続くと、自律神経の乱れや血流の停滞などを引き起こし、性機能にも影響が出ることがあります。ストレスが強く、気分がすっきりしない方には、気持ちを整え、精神的安定を促す処方が適しています。
処方:柴胡加竜骨牡蠣湯、桂枝加竜骨牡蠣湯、逍遙散、四逆散、加味逍遙散など
■血流の悪さが関与しているタイプ(血行不良、肩こり、頭痛、下肢の冷え)
血の巡りが滞ることで、陰部への血流が不十分になり、機能の低下を引き起こしているケースです。とくに、冷えやこり、慢性的な頭痛がある方、生活習慣病を抱える方に多くみられます。血流を促進し、全身の循環機能を改善する処方を使用します。
処方:冠心逐瘀丹、血府逐瘀湯、桂枝茯苓丸、桃核承気湯など
富士堂では、男性機能に関するご相談について、完全にプライベートが保たれる個室でのご相談環境を整えており、他の患者様と顔を合わせることなく、安心してお話しいただけます。また、ご自宅からご利用いただけるオンライン相談システムも充実しており、より気軽にご相談いただけるよう配慮しております。
富士堂では、不安な気持ちにも十分に配慮しながら、お一人おひとりの体質や症状に応じた丁寧な対応を心がけています。「話してよかった」と感じていただけるよう、専門知識と豊富な経験をもとに、誠実にサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
5. 尿漏れ(腹圧性尿失禁や加齢に伴う症状)
尿漏れ(尿失禁)は、自分の意思とは関係なく尿が漏れてしまう状態で、特に女性に多く見られる症状です。その中でも最も頻度が高いのが「腹圧性尿失禁」で、咳やくしゃみ、重いものを持ち上げる、走る、笑うなどの際に腹圧が上昇することで尿が漏れてしまうものです。これは、出産や加齢により骨盤底筋群が緩んだり、尿道を支える組織が弱くなったりすることが主な原因とされています。
女性の尿失禁は、出産経験者で約30-40%、未経験者でも約10-20%に認められ、年齢と共に有病率が上昇する傾向があります。また、閉経後にはエストロゲンの低下により尿道や膀胱周囲の組織が萎縮し、症状がさらに悪化することも少なくありません。
尿漏れは身体的な不快感だけでなく、「外出先で漏れてしまったらどうしよう」「運動ができない」「笑うことを控えてしまう」といった行動制限や、「年を取った証拠だ」「女性として恥ずかしい」といった精神的な負担も大きな問題となります。しかし、このような悩みは非常にプライベートな内容であるため、家族や親しい友人にさえ相談できずに一人で抱え込んでしまう方が大変多いのが現状です。
富士堂では、他の方と接触することのない個室での相談や、ご自宅でゆっくりとお話しいただけるオンライン相談をご用意しております。女性スタッフも在籍しており、同じ女性として共感を持ってお話をお聞きできる環境も整えております。
西洋医学では、薬による治療や骨盤底筋のトレーニング、場合によっては手術などが行われますが、「手術は避けたい」「薬だけでは効果が不十分」「もっと自然な方法で改善したい」「体質から見直したい」といったご相談を多くいただきます。
そのようなご希望に対し、骨盤底筋を自然に強化し、全身の巡りやホルモンバランスを整えるための漢方治療は1つの選択肢となります。漢方では、局所的な症状だけでなく、全身の活力や体質を改善することで、尿漏れの根本的な改善を目指していきます。
① 漢方医学における尿漏れの考え方
漢方医学では、尿漏れを「加齢や体力低下にともなう身体機能の衰え」や「内臓の支える力や代謝・巡りのバランスの乱れ」といった体質的な問題が背景にある状態と考えます。特に、排尿をコントロールするための筋力・内臓の働き・自律神経のバランスがうまく保たれていないことが関係しているとされています。
以下のような体質的な特徴がみられる場合、尿漏れは全身の調整機能の低下や体の土台の弱りとしてあらわれている可能性があります。
・慢性的な疲労感や気力の低下
・胃腸が弱く、下痢をしやすい
・腰や下腹部の重だるさ
・手足の冷えや寒がり
・月経量の減少や生理不順
・肌の乾燥や老化
・夜間頻尿や残尿感
これらの症状を含めて体質全体を丁寧に整え、排尿機能を支える力を体の内側から高めていくのが、漢方治療の特徴です。
② 尿漏れの漢方治療
富士堂では、尿漏れでお悩みの方に対して、症状の程度や現れ方、女性には出産歴、月経状況、更年期症状の有無などを詳しくお伺いし、舌診・脈診・腹診を通じて体質を多角的に評価しています。その上で、骨盤底筋の機能向上、全身の気血の充実、ホルモンバランスの調整などを考慮した処方を選択します。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■冷えや体力の低下が背景にあるタイプの尿漏れ(冷え、夜間頻尿、腰痛、体力低下)
体を温める力や筋力・代謝が低下することで、膀胱の働きや尿を我慢する力が弱くなり、尿漏れが起こりやすくなります。特に高齢者や冷えやすい体質の方、体力が落ちている方に多く見られます。
処方:八味地黄丸、牛車腎気丸、真武湯、人参湯、附子理中湯など
■胃腸が弱く、内臓を支える力が低下しているタイプ(疲労感、胃腸虚弱、内臓下垂感)
消化吸収力の低下や体の支える力の弱さによって、骨盤底の筋肉や内臓が下がりやすくなり、尿漏れが起こることがあります。出産後や慢性的に疲れやすい方に多く見られます。
処方:補中益気湯、参苓白朮散、六君子湯、香砂六君子湯など
■ 熱感・乾燥が目立つタイプ(のぼせ、口渇、更年期症状、皮膚乾燥)
女性ホルモンの変化により、体内の潤いが不足し、のぼせ・ほてり・乾燥などの症状が起こると、膀胱の不安定さや尿漏れにつながることがあります。更年期以降の女性に多く見られる傾向です。
処方:六味地黄丸、知柏地黄丸、杞菊地黄丸、亀板配合製品など
■栄養不足や体の基礎的な力が弱っているタイプ(貧血傾向、月経過少、疲れやすい)
体をめぐる栄養やエネルギーが不足していると、全身の機能が低下し、膀胱の働きや尿をコントロールする力が弱まります。産後や病後の回復が遅れている方にもよく見られます。
処方:十全大補湯、人参養栄湯、帰脾湯、婦宝当帰膠、芎帰調血飲第一加減など
■ストレスや自律神経の乱れが関与するタイプ(ストレス、イライラ、月経前症候群)
精神的な緊張やストレスによって自律神経のバランスが乱れると、膀胱の働きにも影響が出やすくなり、尿意のコントロールが難しくなることがあります。仕事や育児などによる精神的負担の大きい方に多く見られます。
処方:加味逍遙散、柴胡加竜骨牡蠣湯、抑肝散、四逆散、香蘇散など
これらの処方は、単に尿漏れの症状を改善するだけでなく、「なぜ尿が漏れやすくなったのか」という根本的な体質を立て直すことで、長期的な症状の安定化を目指した治療となります。
「外出が不安で積極的になれない」「運動を控えるようになった」「このまま悪化するのではないかと心配」—— そのようなお悩みをお持ちの方は、お一人で悩まずにぜひご相談ください。お一人お一人の体質や生活環境を理解した上で、最適な改善策をご提案いたします。
4. 男性機能障害(男性更年期障害・ED・性欲低下)
男性機能障害は、ED(勃起不全)、性欲の低下、射精障害、男性更年期障害(LOH症候群:Late-Onset Hypogonadism)などを含む包括的な概念で、40歳以降の中高年男性において増加傾向にあります。これらの症状は、テストステロンなどの男性ホルモンの低下、血管機能の劣化、神経系の変化、心理的要因、生活習慣病の影響などが複合的に関与して生じると考えられています。
特にEDは、「満足な性行為を行うのに十分な勃起が得られない、または維持できない状態」と定義され、日本国内では成人男性の約4人に1人が何らかの程度のEDを経験しているとの報告もあります。また、男性更年期障害では、性機能の低下に加えて、疲労感、やる気の低下、イライラ、不眠、筋力低下、記憶力の減退、うつ症状などの多彩な症状が現れることがあります。
これらの症状は、男性の自信や自尊心に深く関わる極めてデリケートな問題であり、「誰にも相談できない」「恥ずかしくて病院に行けない」と一人で悩みを抱え込んでしまう方が非常に多いのが現実です。また、パートナーとの関係性にも影響を及ぼすため、夫婦間のコミュニケーションにも支障をきたすケースも少なくありません。
しかし、男性機能障害は決して珍しい症状ではなく、適切な治療やケアにより改善が期待できる分野でもあります。近年では、このような男性特有の悩みについて理解が深まり、治療選択肢も多様化してきています。
西洋医学的には、PDE5阻害薬(シルデナフィル、タダラフィルなど)、男性ホルモン補充療法、心理カウンセリングなどの治療法がありますが、「薬の効果が不十分」「副作用が心配」「根本的な体力向上を図りたい」といったご希望をお持ちの方も多くいらっしゃいます。
そのような中で、男性機能障害に対する「全身の活力向上」「ホルモンバランスの自然な調整」「心身の総合的な強化」を目指した漢方治療は1つの選択肢となります。漢方薬には、古来より男性機能をサポートしてきた豊富な処方があり、個々の体質や症状に合わせた細やかな調整が可能です。
① 漢方医学における男性機能障害の考え方
漢方医学では、男性機能障害を「腎精の不足」を中心とした全身的なエネルギー低下として理解します。漢方における「腎」は、生殖機能をはじめ、成長・発育・老化などを担う重要な機能とされており、その働きが低下すると、性機能だけでなく、体力・気力・免疫力・記憶力など、全身のさまざまな側面に影響が及ぶと考えられています。
以下のような症状や体質的な傾向がみられる場合、男性機能の不調は、単なる局所的な問題ではなく、全身状態や心身のバランスの乱れの一環としてあらわれていると捉えます。
・慢性的な疲労感や倦怠感
・腰や膝の脱力感、痛み
・夜間頻尿や残尿感
・冷えや寒がりの傾向
・筋力の低下、体力の衰え
・不眠や眠りの浅さ
これらの症状も含めて全身的に調整することで、男性機能の回復と維持を図るのが漢方治療のアプローチです。
② 男性機能障害の漢方治療
富士堂では、男性機能に関するお悩みをお持ちの方に対して、プライバシーに十分配慮しながら、症状の詳細、生活習慣、ストレス状況、既往歴などを丁寧にお伺いします。また、舌診・脈診・腹診により体質を総合的に判断し、個々の方に最適な治療方針を立てています。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■冷えや体力の衰えが目立つタイプ(冷え、体力低下、夜間頻尿、腰痛)
身体を温め、活動を支える力が弱くなっていると、冷えを強く感じたり、夜間の排尿が増えたり、全身の活力が落ちて性機能も低下しやすくなります。
こうした状態では、代謝や血行を促進し、体の内側から温めることで、性機能の衰えを改善し、勃起力や性欲の回復にもつなげていく漢方薬を用います。
処方:八味地黄丸、牛車腎気丸、参馬補腎丸、参茸補血丸、真武湯など
■体の潤い不足や熱感が気になるタイプ(のぼせ、口渇、不眠、イライラ)
心身の疲労やストレスの蓄積などにより、体に必要な潤いが不足し、熱がこもりやすくなっている状態です。のぼせや寝つきの悪さ、口の渇き、イライラ感などがみられる方には、体の内側から熱を鎮め、心身を落ち着ける処方を用います。
処方:六味地黄丸、知柏地黄丸、杞菊地黄丸、温清飲、亀板配合製品など
■体力や活力が全体的に低下しているタイプ(疲労感、食欲不振、貧血傾向、集中力低下)
慢性的な疲れや栄養不足により、体全体の活力や臓器の働きが低下している場合には、体力の回復と栄養状態の改善を同時に図る処方を使用します。虚弱体質や病後の回復期にも有効です。
処方:十全大補湯、人参養栄湯、補中益気湯、帰脾湯など
■ストレスや精神的な緊張が影響しているタイプ(ストレス、イライラ、精神的緊張)
精神的な緊張や感情の抑圧が続くと、自律神経の乱れや血流の停滞などを引き起こし、性機能にも影響が出ることがあります。ストレスが強く、気分がすっきりしない方には、気持ちを整え、精神的安定を促す処方が適しています。
処方:柴胡加竜骨牡蠣湯、桂枝加竜骨牡蠣湯、逍遙散、四逆散、加味逍遙散など
■血流の悪さが関与しているタイプ(血行不良、肩こり、頭痛、下肢の冷え)
血の巡りが滞ることで、陰部への血流が不十分になり、機能の低下を引き起こしているケースです。とくに、冷えやこり、慢性的な頭痛がある方、生活習慣病を抱える方に多くみられます。血流を促進し、全身の循環機能を改善する処方を使用します。
処方:冠心逐瘀丹、血府逐瘀湯、桂枝茯苓丸、桃核承気湯など
富士堂では、男性機能に関するご相談について、完全にプライベートが保たれる個室でのご相談環境を整えており、他の患者様と顔を合わせることなく、安心してお話しいただけます。また、ご自宅からご利用いただけるオンライン相談システムも充実しており、より気軽にご相談いただけるよう配慮しております。
富士堂では、不安な気持ちにも十分に配慮しながら、お一人おひとりの体質や症状に応じた丁寧な対応を心がけています。「話してよかった」と感じていただけるよう、専門知識と豊富な経験をもとに、誠実にサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
5. 尿漏れ(腹圧性尿失禁や加齢に伴う症状)
尿漏れ(尿失禁)は、自分の意思とは関係なく尿が漏れてしまう状態で、特に女性に多く見られる症状です。その中でも最も頻度が高いのが「腹圧性尿失禁」で、咳やくしゃみ、重いものを持ち上げる、走る、笑うなどの際に腹圧が上昇することで尿が漏れてしまうものです。これは、出産や加齢により骨盤底筋群が緩んだり、尿道を支える組織が弱くなったりすることが主な原因とされています。
女性の尿失禁は、出産経験者で約30-40%、未経験者でも約10-20%に認められ、年齢と共に有病率が上昇する傾向があります。また、閉経後にはエストロゲンの低下により尿道や膀胱周囲の組織が萎縮し、症状がさらに悪化することも少なくありません。
尿漏れは身体的な不快感だけでなく、「外出先で漏れてしまったらどうしよう」「運動ができない」「笑うことを控えてしまう」といった行動制限や、「年を取った証拠だ」「女性として恥ずかしい」といった精神的な負担も大きな問題となります。しかし、このような悩みは非常にプライベートな内容であるため、家族や親しい友人にさえ相談できずに一人で抱え込んでしまう方が大変多いのが現状です。
富士堂では、他の方と接触することのない個室での相談や、ご自宅でゆっくりとお話しいただけるオンライン相談をご用意しております。女性スタッフも在籍しており、同じ女性として共感を持ってお話をお聞きできる環境も整えております。
西洋医学では、薬による治療や骨盤底筋のトレーニング、場合によっては手術などが行われますが、「手術は避けたい」「薬だけでは効果が不十分」「もっと自然な方法で改善したい」「体質から見直したい」といったご相談を多くいただきます。
そのようなご希望に対し、骨盤底筋を自然に強化し、全身の巡りやホルモンバランスを整えるための漢方治療は1つの選択肢となります。漢方では、局所的な症状だけでなく、全身の活力や体質を改善することで、尿漏れの根本的な改善を目指していきます。
① 漢方医学における尿漏れの考え方
漢方医学では、尿漏れを「加齢や体力低下にともなう身体機能の衰え」や「内臓の支える力や代謝・巡りのバランスの乱れ」といった体質的な問題が背景にある状態と考えます。特に、排尿をコントロールするための筋力・内臓の働き・自律神経のバランスがうまく保たれていないことが関係しているとされています。
以下のような体質的な特徴がみられる場合、尿漏れは全身の調整機能の低下や体の土台の弱りとしてあらわれている可能性があります。
・慢性的な疲労感や気力の低下
・胃腸が弱く、下痢をしやすい
・腰や下腹部の重だるさ
・手足の冷えや寒がり
・月経量の減少や生理不順
・肌の乾燥や老化
・夜間頻尿や残尿感
これらの症状を含めて体質全体を丁寧に整え、排尿機能を支える力を体の内側から高めていくのが、漢方治療の特徴です。
② 尿漏れの漢方治療
富士堂では、尿漏れでお悩みの方に対して、症状の程度や現れ方、女性には出産歴、月経状況、更年期症状の有無などを詳しくお伺いし、舌診・脈診・腹診を通じて体質を多角的に評価しています。その上で、骨盤底筋の機能向上、全身の気血の充実、ホルモンバランスの調整などを考慮した処方を選択します。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■冷えや体力の低下が背景にあるタイプの尿漏れ(冷え、夜間頻尿、腰痛、体力低下)
体を温める力や筋力・代謝が低下することで、膀胱の働きや尿を我慢する力が弱くなり、尿漏れが起こりやすくなります。特に高齢者や冷えやすい体質の方、体力が落ちている方に多く見られます。
処方:八味地黄丸、牛車腎気丸、真武湯、人参湯、附子理中湯など
■胃腸が弱く、内臓を支える力が低下しているタイプ(疲労感、胃腸虚弱、内臓下垂感)
消化吸収力の低下や体の支える力の弱さによって、骨盤底の筋肉や内臓が下がりやすくなり、尿漏れが起こることがあります。出産後や慢性的に疲れやすい方に多く見られます。
処方:補中益気湯、参苓白朮散、六君子湯、香砂六君子湯など
■ 熱感・乾燥が目立つタイプ(のぼせ、口渇、更年期症状、皮膚乾燥)
女性ホルモンの変化により、体内の潤いが不足し、のぼせ・ほてり・乾燥などの症状が起こると、膀胱の不安定さや尿漏れにつながることがあります。更年期以降の女性に多く見られる傾向です。
処方:六味地黄丸、知柏地黄丸、杞菊地黄丸、亀板配合製品など
■栄養不足や体の基礎的な力が弱っているタイプ(貧血傾向、月経過少、疲れやすい)
体をめぐる栄養やエネルギーが不足していると、全身の機能が低下し、膀胱の働きや尿をコントロールする力が弱まります。産後や病後の回復が遅れている方にもよく見られます。
処方:十全大補湯、人参養栄湯、帰脾湯、婦宝当帰膠、芎帰調血飲第一加減など
■ストレスや自律神経の乱れが関与するタイプ(ストレス、イライラ、月経前症候群)
精神的な緊張やストレスによって自律神経のバランスが乱れると、膀胱の働きにも影響が出やすくなり、尿意のコントロールが難しくなることがあります。仕事や育児などによる精神的負担の大きい方に多く見られます。
処方:加味逍遙散、柴胡加竜骨牡蠣湯、抑肝散、四逆散、香蘇散など
これらの処方は、単に尿漏れの症状を改善するだけでなく、「なぜ尿が漏れやすくなったのか」という根本的な体質を立て直すことで、長期的な症状の安定化を目指した治療となります。
「外出が不安で積極的になれない」「運動を控えるようになった」「このまま悪化するのではないかと心配」—— そのようなお悩みをお持ちの方は、お一人で悩まずにぜひご相談ください。お一人お一人の体質や生活環境を理解した上で、最適な改善策をご提案いたします。
処方:猪苓湯、猪苓湯合四物湯、五淋散、竜胆瀉肝湯、清心蓮子飲など
■冷え・虚弱体質に伴う膀胱炎(寒がり、易疲労、感染を繰り返す)
体が冷えやすく、体力や回復力が落ちている状態では、膀胱の抵抗力が弱まり、膀胱炎を繰り返しやすくなります。こうした場合には、体を内側から温め、膀胱の働きを助ける処方を用います。このタイプでは、体を深部から温めて免疫機能を支え、膀胱周囲の血流や機能を回復させるような漢方薬を用います。抗菌薬で改善しきれない残尿感や違和感、夜間頻尿の訴えに対しても、体質に応じた処方調整が有効です。
処方:八味地黄丸、真武湯、牛車腎気丸、附子理中湯など
■疲労や体力低下が背景にあるタイプ(疲労感、治りにくい、再発しやすい)
慢性的な疲労や栄養不足、ストレスの蓄積などにより体力や免疫力が低下すると、膀胱炎をくり返しやすくなったり、一度かかると治りにくくなったりすることがあります。こうした状態では、局所の炎症だけでなく、体全体の回復力の底上げが必要になります。
このタイプでは、体力や血の巡りを補い、体の内側から抵抗力を高めることを目的とした漢方薬を用います。再発を防ぐだけでなく、日常的な疲れや冷え、眠りの質の改善なども期待できます。
処方:補中益気湯、十全大補湯、人参養栄湯、帰脾湯、加味帰脾湯など
■ストレス・情緒不安定による膀胱炎(ストレス、感情の変動、月経前の悪化)
精神的なストレスや感情の波が原因で体内の気の巡りが滞り、膀胱炎の症状が現れたり悪化したりするタイプです。特に女性では、月経周期と症状が連動していることが多く見られます。
この場合は、気の流れを促し心身のバランスを整える漢方処方を用います。精神的な緊張や不安を和らげ、体調の安定を目指します。
処方:加味逍遙散、柴胡疏肝散、逍遙散、四逆散、甘麦大棗湯など
■消化機能低下・水分代謝異常タイプの膀胱炎(消化不良、むくみ、軟便傾向)
胃腸の働きが弱く、栄養の吸収や水分の調整がうまくいかないことで、体内のバランスが乱れ、膀胱炎を起こしやすくなっている場合に用います。胃腸の調子を整え、全身の代謝を改善する処方が効果的です。
処方:六君子湯、参苓白朮散、茯苓飲、補中益気湯、香砂六君子湯など
4. 男性機能障害(男性更年期障害・ED・性欲低下)
男性機能障害は、ED(勃起不全)、性欲の低下、射精障害、男性更年期障害(LOH症候群:Late-Onset Hypogonadism)などを含む包括的な概念で、40歳以降の中高年男性において増加傾向にあります。これらの症状は、テストステロンなどの男性ホルモンの低下、血管機能の劣化、神経系の変化、心理的要因、生活習慣病の影響などが複合的に関与して生じると考えられています。
特にEDは、「満足な性行為を行うのに十分な勃起が得られない、または維持できない状態」と定義され、日本国内では成人男性の約4人に1人が何らかの程度のEDを経験しているとの報告もあります。また、男性更年期障害では、性機能の低下に加えて、疲労感、やる気の低下、イライラ、不眠、筋力低下、記憶力の減退、うつ症状などの多彩な症状が現れることがあります。
これらの症状は、男性の自信や自尊心に深く関わる極めてデリケートな問題であり、「誰にも相談できない」「恥ずかしくて病院に行けない」と一人で悩みを抱え込んでしまう方が非常に多いのが現実です。また、パートナーとの関係性にも影響を及ぼすため、夫婦間のコミュニケーションにも支障をきたすケースも少なくありません。
しかし、男性機能障害は決して珍しい症状ではなく、適切な治療やケアにより改善が期待できる分野でもあります。近年では、このような男性特有の悩みについて理解が深まり、治療選択肢も多様化してきています。
西洋医学的には、PDE5阻害薬(シルデナフィル、タダラフィルなど)、男性ホルモン補充療法、心理カウンセリングなどの治療法がありますが、「薬の効果が不十分」「副作用が心配」「根本的な体力向上を図りたい」といったご希望をお持ちの方も多くいらっしゃいます。
そのような中で、男性機能障害に対する「全身の活力向上」「ホルモンバランスの自然な調整」「心身の総合的な強化」を目指した漢方治療は1つの選択肢となります。漢方薬には、古来より男性機能をサポートしてきた豊富な処方があり、個々の体質や症状に合わせた細やかな調整が可能です。
① 漢方医学における男性機能障害の考え方
漢方医学では、男性機能障害を「腎精の不足」を中心とした全身的なエネルギー低下として理解します。漢方における「腎」は、生殖機能をはじめ、成長・発育・老化などを担う重要な機能とされており、その働きが低下すると、性機能だけでなく、体力・気力・免疫力・記憶力など、全身のさまざまな側面に影響が及ぶと考えられています。
以下のような症状や体質的な傾向がみられる場合、男性機能の不調は、単なる局所的な問題ではなく、全身状態や心身のバランスの乱れの一環としてあらわれていると捉えます。
・慢性的な疲労感や倦怠感
・腰や膝の脱力感、痛み
・夜間頻尿や残尿感
・冷えや寒がりの傾向
・筋力の低下、体力の衰え
・不眠や眠りの浅さ
これらの症状も含めて全身的に調整することで、男性機能の回復と維持を図るのが漢方治療のアプローチです。
② 男性機能障害の漢方治療
富士堂では、男性機能に関するお悩みをお持ちの方に対して、プライバシーに十分配慮しながら、症状の詳細、生活習慣、ストレス状況、既往歴などを丁寧にお伺いします。また、舌診・脈診・腹診により体質を総合的に判断し、個々の方に最適な治療方針を立てています。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■冷えや体力の衰えが目立つタイプ(冷え、体力低下、夜間頻尿、腰痛)
身体を温め、活動を支える力が弱くなっていると、冷えを強く感じたり、夜間の排尿が増えたり、全身の活力が落ちて性機能も低下しやすくなります。
こうした状態では、代謝や血行を促進し、体の内側から温めることで、性機能の衰えを改善し、勃起力や性欲の回復にもつなげていく漢方薬を用います。
処方:八味地黄丸、牛車腎気丸、参馬補腎丸、参茸補血丸、真武湯など
■体の潤い不足や熱感が気になるタイプ(のぼせ、口渇、不眠、イライラ)
心身の疲労やストレスの蓄積などにより、体に必要な潤いが不足し、熱がこもりやすくなっている状態です。のぼせや寝つきの悪さ、口の渇き、イライラ感などがみられる方には、体の内側から熱を鎮め、心身を落ち着ける処方を用います。
処方:六味地黄丸、知柏地黄丸、杞菊地黄丸、温清飲、亀板配合製品など
■体力や活力が全体的に低下しているタイプ(疲労感、食欲不振、貧血傾向、集中力低下)
慢性的な疲れや栄養不足により、体全体の活力や臓器の働きが低下している場合には、体力の回復と栄養状態の改善を同時に図る処方を使用します。虚弱体質や病後の回復期にも有効です。
処方:十全大補湯、人参養栄湯、補中益気湯、帰脾湯など
■ストレスや精神的な緊張が影響しているタイプ(ストレス、イライラ、精神的緊張)
精神的な緊張や感情の抑圧が続くと、自律神経の乱れや血流の停滞などを引き起こし、性機能にも影響が出ることがあります。ストレスが強く、気分がすっきりしない方には、気持ちを整え、精神的安定を促す処方が適しています。
処方:柴胡加竜骨牡蠣湯、桂枝加竜骨牡蠣湯、逍遙散、四逆散、加味逍遙散など
■血流の悪さが関与しているタイプ(血行不良、肩こり、頭痛、下肢の冷え)
血の巡りが滞ることで、陰部への血流が不十分になり、機能の低下を引き起こしているケースです。とくに、冷えやこり、慢性的な頭痛がある方、生活習慣病を抱える方に多くみられます。血流を促進し、全身の循環機能を改善する処方を使用します。
処方:冠心逐瘀丹、血府逐瘀湯、桂枝茯苓丸、桃核承気湯など
富士堂では、男性機能に関するご相談について、完全にプライベートが保たれる個室でのご相談環境を整えており、他の患者様と顔を合わせることなく、安心してお話しいただけます。また、ご自宅からご利用いただけるオンライン相談システムも充実しており、より気軽にご相談いただけるよう配慮しております。
富士堂では、不安な気持ちにも十分に配慮しながら、お一人おひとりの体質や症状に応じた丁寧な対応を心がけています。「話してよかった」と感じていただけるよう、専門知識と豊富な経験をもとに、誠実にサポートいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
5. 尿漏れ(腹圧性尿失禁や加齢に伴う症状)
尿漏れ(尿失禁)は、自分の意思とは関係なく尿が漏れてしまう状態で、特に女性に多く見られる症状です。その中でも最も頻度が高いのが「腹圧性尿失禁」で、咳やくしゃみ、重いものを持ち上げる、走る、笑うなどの際に腹圧が上昇することで尿が漏れてしまうものです。これは、出産や加齢により骨盤底筋群が緩んだり、尿道を支える組織が弱くなったりすることが主な原因とされています。
女性の尿失禁は、出産経験者で約30-40%、未経験者でも約10-20%に認められ、年齢と共に有病率が上昇する傾向があります。また、閉経後にはエストロゲンの低下により尿道や膀胱周囲の組織が萎縮し、症状がさらに悪化することも少なくありません。
尿漏れは身体的な不快感だけでなく、「外出先で漏れてしまったらどうしよう」「運動ができない」「笑うことを控えてしまう」といった行動制限や、「年を取った証拠だ」「女性として恥ずかしい」といった精神的な負担も大きな問題となります。しかし、このような悩みは非常にプライベートな内容であるため、家族や親しい友人にさえ相談できずに一人で抱え込んでしまう方が大変多いのが現状です。
富士堂では、他の方と接触することのない個室での相談や、ご自宅でゆっくりとお話しいただけるオンライン相談をご用意しております。女性スタッフも在籍しており、同じ女性として共感を持ってお話をお聞きできる環境も整えております。
西洋医学では、薬による治療や骨盤底筋のトレーニング、場合によっては手術などが行われますが、「手術は避けたい」「薬だけでは効果が不十分」「もっと自然な方法で改善したい」「体質から見直したい」といったご相談を多くいただきます。
そのようなご希望に対し、骨盤底筋を自然に強化し、全身の巡りやホルモンバランスを整えるための漢方治療は1つの選択肢となります。漢方では、局所的な症状だけでなく、全身の活力や体質を改善することで、尿漏れの根本的な改善を目指していきます。
① 漢方医学における尿漏れの考え方
漢方医学では、尿漏れを「加齢や体力低下にともなう身体機能の衰え」や「内臓の支える力や代謝・巡りのバランスの乱れ」といった体質的な問題が背景にある状態と考えます。特に、排尿をコントロールするための筋力・内臓の働き・自律神経のバランスがうまく保たれていないことが関係しているとされています。
以下のような体質的な特徴がみられる場合、尿漏れは全身の調整機能の低下や体の土台の弱りとしてあらわれている可能性があります。
・慢性的な疲労感や気力の低下
・胃腸が弱く、下痢をしやすい
・腰や下腹部の重だるさ
・手足の冷えや寒がり
・月経量の減少や生理不順
・肌の乾燥や老化
・夜間頻尿や残尿感
これらの症状を含めて体質全体を丁寧に整え、排尿機能を支える力を体の内側から高めていくのが、漢方治療の特徴です。
② 尿漏れの漢方治療
富士堂では、尿漏れでお悩みの方に対して、症状の程度や現れ方、女性には出産歴、月経状況、更年期症状の有無などを詳しくお伺いし、舌診・脈診・腹診を通じて体質を多角的に評価しています。その上で、骨盤底筋の機能向上、全身の気血の充実、ホルモンバランスの調整などを考慮した処方を選択します。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■冷えや体力の低下が背景にあるタイプの尿漏れ(冷え、夜間頻尿、腰痛、体力低下)
体を温める力や筋力・代謝が低下することで、膀胱の働きや尿を我慢する力が弱くなり、尿漏れが起こりやすくなります。特に高齢者や冷えやすい体質の方、体力が落ちている方に多く見られます。
処方:八味地黄丸、牛車腎気丸、真武湯、人参湯、附子理中湯など
■胃腸が弱く、内臓を支える力が低下しているタイプ(疲労感、胃腸虚弱、内臓下垂感)
消化吸収力の低下や体の支える力の弱さによって、骨盤底の筋肉や内臓が下がりやすくなり、尿漏れが起こることがあります。出産後や慢性的に疲れやすい方に多く見られます。
処方:補中益気湯、参苓白朮散、六君子湯、香砂六君子湯など
■ 熱感・乾燥が目立つタイプ(のぼせ、口渇、更年期症状、皮膚乾燥)
女性ホルモンの変化により、体内の潤いが不足し、のぼせ・ほてり・乾燥などの症状が起こると、膀胱の不安定さや尿漏れにつながることがあります。更年期以降の女性に多く見られる傾向です。
処方:六味地黄丸、知柏地黄丸、杞菊地黄丸、亀板配合製品など
■栄養不足や体の基礎的な力が弱っているタイプ(貧血傾向、月経過少、疲れやすい)
体をめぐる栄養やエネルギーが不足していると、全身の機能が低下し、膀胱の働きや尿をコントロールする力が弱まります。産後や病後の回復が遅れている方にもよく見られます。
処方:十全大補湯、人参養栄湯、帰脾湯、婦宝当帰膠、芎帰調血飲第一加減など
■ストレスや自律神経の乱れが関与するタイプ(ストレス、イライラ、月経前症候群)
精神的な緊張やストレスによって自律神経のバランスが乱れると、膀胱の働きにも影響が出やすくなり、尿意のコントロールが難しくなることがあります。仕事や育児などによる精神的負担の大きい方に多く見られます。
処方:加味逍遙散、柴胡加竜骨牡蠣湯、抑肝散、四逆散、香蘇散など
これらの処方は、単に尿漏れの症状を改善するだけでなく、「なぜ尿が漏れやすくなったのか」という根本的な体質を立て直すことで、長期的な症状の安定化を目指した治療となります。
「外出が不安で積極的になれない」「運動を控えるようになった」「このまま悪化するのではないかと心配」—— そのようなお悩みをお持ちの方は、お一人で悩まずにぜひご相談ください。お一人お一人の体質や生活環境を理解した上で、最適な改善策をご提案いたします。
4. 実際の症例
**詳しい症状別の記事や実際にあった症例などについてはページ最下部のリンクからご覧いただけます**
○ IgA腎症(40代・男性)
尿潜血および蛋白尿を指摘され、詳しい検査の結果、IgA腎症と診断されました。ステロイド治療を受けながら、漢方による体質改善も併用したいとのご希望で来店されました。
体格は中肉中背で、扁桃腺が腫れやすく、手足の冷えや疲労感を訴えておられました。漢方治療では、まず腎臓の炎症を抑え、血流の改善と免疫バランスの調整を目的に、煎じ薬を処方いたしました。
治療の途中、ステロイド薬の副作用によりニキビの症状が出現したため、皮膚症状に配慮した処方にも調整を行いました。
約1年間の継続的な治療により、蛋白尿・血尿はいずれも陰性となり、ステロイド薬も無事に終了することができました。その後は、手軽なエキス剤に切り替え、再発予防を目的に継続服用いただいています。
○男性不妊(40代男性)
精液検査にて、精子の正常形態率および運動率の低下を指摘され、病院で処方されたサプリメントを継続していたものの改善が見られず、漢方による体質改善を希望されてご来店されました。
体格はやや小太りで、食生活の乱れがみられるほか、自営業によるストレスも多く、睡眠の質が悪いといった自律神経の乱れに関連する症状も見受けられました。こうした体質や生活背景を踏まえ、自律神経のバランスを整える煎じ薬と、体の基礎力を高める滋養強壮薬を処方し、併せて生活習慣や食事内容に関する具体的なアドバイスも行いました。
治療を開始してから、精子の質は徐々に改善され、約10か月後に奥様が自然妊娠されました。その後、2年を経て、ご家族3人で撮影されたお写真とともに、丁寧な御礼の言葉をいただきました。
■併せて読みたい完治した患者様からの口コミと解説記事
>>ご夫婦で稽留流産・精子運動率低下など乗越え妊娠 | 漢方体験談
>>【男性不妊】36歳、精子運動率10%台が83%に改善
>>【33歳、自然妊娠成功&ご主人様のIgA腎症改善】漢方体験談
5. 富士堂の漢方が選ばれる理由
1. オーダーメイドの漢方治療
「煎じ薬を試したいけど自分で煎じられるの?」
「忙しいから手軽に飲める顆粒剤がいい」
「日常生活でも気を付けることってある?」
ご来店いただく患者様は様々な悩みや不安を抱えています。富士堂の漢方相談では、病状や体質を丁寧に確認し、あなたに合った「証(しょう、=漢方を選ぶ根拠)」を見極めます。
初回相談は約1時間。体調のことだけでなく、経済面や精神的な不安も遠慮なくご相談ください。経験豊富な中医師・薬剤師が、生活アドバイスも含めた総合的なサポートを行います。
2. 豊富な臨床経験
富士堂に在籍するスタッフは中医師から薬剤師まで漢方の専門家でありながら、西洋医学の知識も豊富にもつスペシャリストで、毎年7,000名以上の患者様にご相談いただいています。
毎月の社内勉強会や毎週の症例ディスカッションを通じて、常に知識・技術を磨き、皆様の健康に最適な治療をご提供できるよう努めています。
3. 安全性を重視
皆様が安心・安全に漢方をご利用いただけるように以下のことを特に重視しております。
1.方証医学に基づいた、根拠のある漢方相談を徹底
時間を惜しまずに漢方相談を行い、服用後のフォローにも努め、副作用の予防や、効果の確認などに努めます。
2.信頼できるメーカーからのみの仕入れ
使用する生薬はすべて国内の大手漢方メーカー(ウチダ和漢薬・栃本天海堂・高砂薬業・イスクラ産業・クラシエ薬品)から仕入れています。海外からの直輸入は行いません。
3.厳格な品質管理
生薬はすべて原植物の確認、理化学試験、重金属・ヒ素・残留イオウの管理・経験的鑑別、残留農薬管理、微生物検査をクリアした安全なものです。
4. オンライン相談・宅配対応
富士堂では、LINE・WeChat・Teamsなどのビデオ通話ツールによるオンライン相談も可能です。漢方薬は店頭受け取りのほか、ご自宅への発送も承っています。忙しい方や遠方・海外にお住まいの方でも、安心してご利用いただけます。
オンライン相談について詳しくはこちら
6. ご相談・カウンセリングの流れ
漢方薬を受け取るまでの流れは以下のようになります。
ご予約➤ご相談➤漢方薬の選定➤ご確認・お会計➤調剤・お渡し(発送)
詳しくはこちらをご覧くださいませ。
漢方薬は、一人ひとりの体質や体調、生活環境、そしてその方をとりまく背景によって、必要な処方が大きく異なります。そのため富士堂漢方薬局では、最初に丁寧なカウンセリングを行い、現在のお困りの症状だけでなく、これまでの経過や生活習慣、ストレス要因なども含めて総合的に把握することを大切にしています。
ご相談は予約優先制で、個室にてプライバシーに配慮した落ち着いた環境の中、ゆっくりとお話を伺います。初回のカウンセリングでは、漢方医学に基づく「四診(望診・聞診・問診・切診)」をもとに、舌の状態、脈、腹部の緊張や冷えの有無なども丁寧に確認します。
また、西洋医学的な視点も大切にしており、血液検査や画像検査の結果がある場合には、それらも参考にしながら総合的に判断します。まずはお気軽にご相談ください。
■漢方相談予約・お問合せ>>「お問い合わせ(LINE,WeChat,メールフォーム)」
■オンライン相談について詳しくはこちら>>「オンライン漢方相談|来店なしでお薬お届け」
■頭痛・自律神経・精神疾患関連記事一覧
7.泌尿器・腎のお悩みをお持ちの方へ 〜富士堂からのメッセージ〜
頻尿や夜間頻尿、過活動膀胱による強い尿意、繰り返す膀胱炎──。こうした泌尿器の不調は、生活の質を大きく下げるだけでなく、将来的な腎機能低下や感染症リスクにつながることもあり、不安を抱えている方は少なくありません。さらに、男性では更年期障害やED、性欲の低下といった機能面の悩み、女性では尿漏れや加齢に伴う変化が現れ、「誰にも相談できない」と感じてしまうケースもあります。
富士堂漢方薬局には、こうした尿トラブルや性機能に関するご相談で多くの方が来局されています。病院での治療に加えて体質から整えたい方、薬の副作用や長期服用に不安を感じる方もいらっしゃいます。同じ「頻尿」や「尿漏れ」でも、その背景には冷え、ストレス、ホルモンの変動、生活習慣の違いなど、さまざまな要因が隠れているため、丁寧なカウンセリングを通じて原因を見極め、現在の体調や生活に合わせた処方をご提案しています。
また、腎の働きや自律神経のバランス、加齢による変化なども視野に入れ、日常生活で取り入れやすい養生法やセルフケアの工夫もお伝えしています。
「ずっとこのまま続くのか不安」「治療と併せてできることを知りたい」と感じている方へ。富士堂は、あなたの体と心に寄り添い、安心できる選択肢のひとつとなれるよう願っています。