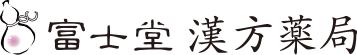Treatment病状別漢方治療

- 頭痛・自律神経・メンタルの不調に悩む方へ|漢方が支える体と心のケア
- 1.頭痛・自律神経・精神疾患に漢方で向き合う理由
富士堂には、頭痛・不眠・気分の落ち込み・動悸・ふらつきなど、脳や神経の不調、自律神経の乱れ、精神的なストレスや不安などを背景としたご相談が数多く寄せられています。これらの症状は、「検査では異常がないけれどつらい」「病院で薬をもらっているが改善しない」「体に合った方法で根本的に整えたい」といったお悩みを持つ方が多いのが特徴です。
また、「精神疾患と診断されるのが怖い」「自律神経失調症やうつ病と周囲に知られるのが恥ずかしい」──そんな不安を抱えながら、誰にも相談できずに苦しんでいる方は少なくありません。ですが、頭痛・不眠・気分の落ち込み・動悸などの“メンタル不調”は、決して特別なことではなく、誰にでも起こりうる心と体のサインです。適切な治療やサポートを受けたり、どんな選択肢を知ったりすることが大事です。
そして、これらの不調は、自律神経のバランスの乱れやホルモン変動、ストレス、生活リズムの崩れ、体力・抵抗力の低下など、さまざまな要因が重なって起こることが多くあります。そのため、症状のある部位だけでなく、全身の状態を見ながら整えていく漢方治療が効果的なケースも少なくありません。漢方では、症状を引き起こしている背景にある「体質の傾向」や「回復力の低下」「体内バランスの偏り」などに着目し、全身の巡りや安定性を高めることで自然な改善を目指します。
■よくあるご相談内容
頭痛、不眠、うつ病、パニック障害、起立性調節障害、自律神経失調症、不安神経症、めまい、慢性疲労、気分の落ち込み、緊張型頭痛、片頭痛、朝起きられない、眠りが浅い、過換気症候群、イライラ、情緒不安定、動悸、息苦しさ、ストレスによる胃腸症状など
2.富士堂における頭痛・自律神経・精神疾患に対する漢方相談の特徴
富士堂では、頭痛や不眠、精神的な不調や自律神経の乱れに対する漢方相談を多く行っており、思春期から高齢者まで、幅広い世代の方にご利用いただいています。
まずは丁寧な問診を通じて、症状の現れ方や背景、生活状況、ストレスの有無などを詳しくお伺いします。さらに漢方医学の視点を取り入れ、舌診・脈診・腹診などにより体全体のバランスを多角的に把握し、現在の体調を評価します。
既に精神科や心療内科、脳神経内科などで治療を受けておられる場合は、西洋医学的な診断や服薬状況を尊重しつつ、併用可能な形での漢方治療をご提案します。
特に、薬の副作用が気になる方や、症状の波が大きい方、長期間改善しない慢性症状のある方には、体質に合わせたオーダーメイドの処方が有効です。
富士堂では、「症状を抑える」ことだけを目的とせず、自律神経の安定、睡眠の質の向上、気力・体力の回復などを通じて、根本からの改善を目指していきます。生活習慣の見直しや食養生についても丁寧にサポートいたします。
今回はその中でも特にご相談の多い以下の5症状と実際の症例などについて解説いたします。(タップで各項目へ)
- 1. 頭痛・自律神経・精神疾患に漢方で向き合う理由
- 2. 富士堂が取り組む「頭痛・自律神経・メンタル不調」への漢方相談の特徴
- 3. 症状別:漢方治療アプローチ
- ➤3-1. 頭痛
- ➤3-2. 不眠症
- ➤3-3. うつ病
- ➤3-4. パニック障害
- ➤3-5. 起立性調節障害
- 4. 実際の症例
- 5. 富士堂の漢方が選ばれる理由
- 6. ご相談・カウンセリングの流れ
- 7. 頭痛・自律神経・メンタル不調でお悩みの方へ 〜富士堂からのメッセージ〜
3.症状別:漢方治療アプローチ
1.頭痛
頭痛は、日常的に多くの人が経験する症状のひとつであり、その背景には緊張型頭痛、片頭痛、群発頭痛など多様な病態が含まれます。特に慢性的に繰り返す頭痛は、生活の質を大きく損なう要因となり、仕事や家事、学業などにも支障をきたします。
西洋医学では、鎮痛薬やトリプタン製剤、抗てんかん薬、降圧薬などの薬物治療が中心となりますが、薬の効果が不十分であったり、頻回な服用による薬物乱用頭痛に悩まされるケースも少なくありません。
このような背景から、頭痛に対しては「体質の改善」や「再発予防」を重視した漢方治療を希望される方が増えています。頭痛に適した漢方薬は多岐にわたり、患者様それぞれの症状や体質に合わせて処方を選択することが可能です。全身のバランスや血流、自律神経の調整を図ることで、慢性頭痛の根本的な改善を目指していきます。
① 漢方医学における頭痛の考え方
漢方では、頭痛を「頭だけの問題」と捉えるのではなく、全身状態との関連から総合的に評価します。例えば、ストレスや過労による自律神経の緊張、ホルモンの変動、血流の停滞、冷え、消化機能の低下、気圧の影響などが頭痛の誘因・悪化因子として関係していると考えます。
特に以下のような背景がみられるケースでは、頭痛は「体の不調の一部」として現れている可能性があります。
- ・疲れやすく、肩や首がこる
- ・生理周期に伴って悪化する
- ・胃腸が弱く、気圧の変化で不調を感じやすい
- ・イライラしやすく、眠りが浅い
- ・めまいや耳鳴りを伴う
このような症状を含めて全体を調整することで、根本的な改善につなげていくのが漢方治療の特徴です。
② 頭痛の漢方治療
富士堂では、頭痛にお悩みの方に対して、問診だけでなく舌・脈・腹の状態を丁寧に観察し、個々の体質と頭痛の関連性を立体的に捉えるよう心がけています。
そのうえで、頭部の血流調整、自律神経系の安定、消化吸収の改善、ホルモンバランスの調整などを視野に入れた処方設計を行っています。
▼主なタイプ別の処方例 ※一例であり、症状・体質により使い分けます
■ストレス・緊張性の頭痛(イライラ、肩こり、不眠傾向)
ストレスが強く、気分の波や不眠、肩こりなどを伴う緊張型の頭痛には、自律神経の過緊張を鎮め、心身の緊張を和らげる処方が有効です。気分の抑うつや不安感が強い場合には、感情のコントロールに働きかける生薬を含む処方を選びます。
処方: 加味逍遙散、抑肝散、柴胡加竜骨牡蠣湯、柴胡桂枝湯、女神散、釣藤散 など
■ 瘀血(血行不良)タイプの頭痛(慢性的・固定的な痛み)
頭の同じ部位が慢性的に痛む、刺すような痛みが続く、肩こりや首のこわばりを強く感じるといった特徴がある頭痛には、血流の滞りを改善し、局所の循環を促す処方を用います。特に、生理前後に悪化する女性の慢性頭痛には、全身の血流を整えることで痛みの根本改善をめざします。
処方:桂枝茯苓丸、桃核承気湯、血府逐瘀丸、冠心逐瘀丹など
■水分代謝の乱れによる頭痛(頭が重い、気圧や湿度で悪化、むくみを伴う)
頭が重だるい、湿気の多い日に悪化しやすい、あるいはむくみ・めまいなどを伴う頭痛には、体内の水分バランスを調整し、余分な水分の停滞を取り除く処方を使用します。胃腸が弱く、内側からの湿気が原因になっていることも少なくありません。
処方:苓桂朮甘湯、五苓散、半夏白朮天麻湯など
■冷えや胃腸の虚弱を伴う片頭痛(拍動性、嘔気、空腹時に悪化)
冷え性や胃腸の弱さを背景に、空腹時や早朝にズキズキと拍動するような頭痛が出るタイプには、身体を内側から温めながら、胃腸機能と循環を整える処方を用います。嘔気や食欲不振を伴うことも多く、頭痛と消化器症状の両面からの対応が重要です。
処方:呉茱萸湯、桂枝人参湯、黄連湯 など
■ 炎症・熱証タイプ(目の充血、顔のほてり)
頭部に熱がこもったような痛みや、目の充血・のぼせなどを伴うタイプです。ストレスや睡眠不足、過食などによって体に「熱」がこもりやすい方に多く、清熱作用のある処方で頭部の炎症や緊張を和らげます。
処方:清上蠲痛湯、黄連解毒湯、三黄瀉心湯など
※補足:変動性・初期予防タイプ(気候変化に弱い、慢性化しやすい)
季節の変わり目や軽いストレスで頭が重く痛くなりやすい方に。軽度〜中等度の頭痛に対して、対症療法から慢性化の予防まで、幅広い目的で用いられる処方です。
処方:川芎茶調散、清上蠲痛湯 、釣藤散、抑肝散加陳皮半夏など
これらの処方は、単に頭痛の痛みを一時的に抑えるのではなく、「なぜ頭痛が起こりやすいのか」という背景を整えることで、再発の予防や全身の安定にもつながる治療を目指しています。
「薬に頼らず頭痛を改善したい」「生理周期や気圧の変化で悪化する頭痛に悩んでいる」「年々薬が効かなくなってきた」——
そのような方こそ、ぜひ一度ご相談ください。症状の奥にある“体質の歪み”を見抜き、改善の糸口をご提案いたします。
2.不眠症
不眠症は、入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠感の欠如など、多様なかたちで現れる睡眠障害です。現代社会ではストレスや生活習慣の乱れにより、不眠を訴える人が増加しており、特に中高年層、女性、心身に負担を抱える方では慢性化しやすい傾向があります。
西洋医学では、睡眠薬や抗不安薬、メラトニン作動薬などによる薬物治療が中心ですが、薬に頼りすぎることで耐性や依存、日中の眠気、ふらつきといった副作用に悩む方も少なくありません。
漢方治療では、単なる「眠れない」という症状に対処するのではなく、「なぜ眠れないのか」という体質や背景を丁寧に見極め、根本的な改善と再発予防を目指します。眠りの質を高めながら、心身の回復力を取り戻していくことが目的です。
① 漢方医学における不眠症の考え方
漢方では、不眠症を「脳や神経の問題」だけでなく、全身のバランスの乱れが表面化した症状ととらえます。特に、ストレスによる自律神経の乱れ、疲労の蓄積、加齢によるホルモンや神経伝達の変調、消化吸収力の低下などが関与していることが多くあります。
以下のような特徴がある場合、漢方的な視点からの調整が有効です。
- ・寝つきが悪く、考え事が止まらない
- ・夜中に何度も目が覚める
- ・眠りが浅く、夢が多い
- ・朝起きたときに疲労感が強く、すっきりしない
- ・日中にイライラしたり不安になりやすい
- ・更年期や月経周期に関連して眠れなくなる
これらの症状は「心と体の働きがうまく噛み合っていない」サインとも言え、体質を含めた全体の調整が不眠改善のカギとなります。
② 不眠症の漢方治療
富士堂では、不眠に対して単に「眠れるようにする」ことだけを目的にせず、「なぜ眠れないのか」「どうすれば自然に眠れるようになるのか」を一人ひとりの生活背景や体質と照らし合わせながら丁寧に分析します。
問診に加えて、舌診・脈診・腹診を活用し、神経系・消化系・循環系・内分泌系など全身の状態を多角的に把握した上で、適切な処方を提案します。
▼主なタイプ別の処方例 ※あくまでも一例です
■ストレス・神経過敏型(寝つきが悪い、イライラ、不安感)
→ 神経の興奮を鎮め、気分の安定を図る処方を中心に用います。
処方: 抑肝散、加味帰脾湯、柴胡加竜骨牡蠣湯、酸棗仁湯、温胆湯など
■消耗・疲労型(眠りが浅い、何度も目が覚める、夢が多い)
→ 神経の回復や滋養、疲労回復を意識した処方が有効です。
処方:酸棗仁湯、帰脾湯、人参養栄湯、桂枝加竜骨牡蠣湯 など
■ 血流・体温調節型(手足が冷える、寝つきが悪い、緊張しやすい)
→ 血流や温度調節機能を整えることで、深い眠りを促します。
処方:温経湯、桂枝加竜骨牡蠣湯、当帰芍薬散、帰脾湯など
■更年期・ホルモン変動型(のぼせ・発汗・動悸を伴う)
→ ホルモンバランスと自律神経を調整し、体内の安定化を図ります。
処方: 知柏地黄丸、加味逍遙散、柴胡加竜骨牡蠣湯、女神散など
■熱・煩躁型(体がほてる、寝汗、イライラ、不安感)
→ 神経の過敏状態や体のこもった熱を鎮め、心身をクールダウンさせる処方を用います。
処方:黄連解毒湯、黄連阿膠湯、酸棗仁湯、清心蓮子飲など
これらの処方は、眠気を無理やり誘導するものではなく、自然に眠れる体の状態をつくることを目的としています。その結果、睡眠の質を根本から徐々に改善し、日中の集中力や気分、体調も向上していくことが期待できます。
不眠は「体質」とも深く関わっており、一人ひとりの生活スタイルや心理状態、身体の状態によってアプローチは変わります。富士堂では、これまで多数の不眠のご相談に対応してきた経験を活かし、単なる薬の代替にとどまらない、全身からの根本改善をサポートしています。
「何を試しても眠れない」「薬にはできるだけ頼りたくない」「眠ってもすっきりしない」とお悩みの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
3.うつ病
うつ病は、気分の落ち込みや意欲の低下、疲労感、眠れない、食欲がわかないといった症状が続く精神疾患です。軽度なものから日常生活が困難になるほどの重度なものまで幅広く、再発しやすいという特徴もあります。
西洋医学では、抗うつ薬や抗不安薬、カウンセリングなどによる治療が中心ですが、「薬が合わない」「副作用がつらい」「薬を減らしたい」というご相談も少なくありません。そうした中で、体質を整え、心と体のバランスを回復させていく漢方治療は、うつ病に対する補完的かつ根本的なアプローチとして注目されています。
① 漢方医学におけるうつ病の考え方
漢方では、うつ病を「心の病」だけではなく、「心と体の機能低下が表裏一体となってあらわれた状態」と捉えます。感情や思考の不調は、消化・循環・自律神経・ホルモンなどの全身的な不調と深く関係していると考えるため、精神的なサポートと同時に、身体的な回復にも重点を置いた治療を行います。
たとえば以下のような傾向がみられる場合、漢方による全体調整が効果的です。
- ・気分が沈みやすく、やる気が出ない
- ・ふと涙が出てしまう、落ち込みが続く
- ・朝が特にしんどく、起き上がれない
- ・イライラしやすく、感情のコントロールがきかない
- ・そわそわして落ち着かず、集中できない
- ・喉や胸が詰まるような違和感が続いている
- ・動悸・息苦しさ・焦り・不安が強い
うつ病の背景には、ストレスによる自律神経の乱れ、エネルギーの消耗、血流の滞り、内臓機能の低下などが複雑に関わっています。漢方ではそれらを一つひとつ丁寧に整えていきます。
② うつ病の漢方治療
富士堂では、うつ病の治療に際して、特に初回カウンセリングにじっくり時間をかけ、生活状況・性格傾向・発症時期・体調の変化などを詳しくうかがいます。さらに、舌・脈・腹部の状態など漢方的な診察も加え、心身の状態を立体的に把握した上で処方設計を行います。
▼主なタイプ別の処方例 ※あくまで一例であり、状態に応じて調整します
ストレス性・神経過敏型(イライラ、不安、不眠)
→ 気の巡りを整え、心の緊張をゆるめる処方が中心になります。
処方:加味逍遙散、柴胡加竜骨牡蠣湯、抑肝散、釣藤散など
エネルギー不足型(無気力、倦怠感、朝つらい)
→ 気力や体力の回復を図る処方を使用します。
処方:補中益気湯、人参養栄湯、十全大補湯、帰脾湯、婦宝当帰膠など
血流の滞り型(思考がまとまらない、イライラ、頭重感)
→ 脳の血流・代謝改善を意識した処方で症状の安定を目指します。
処方:桂枝茯苓丸、桃核承気湯、血府逐瘀丸など
消化機能低下型(胃もたれ、食欲低下、気分の波)
→ 胃腸を立て直し、心と体の“土台”を整える処方を選びます。
処方:六君子湯、香蘇散、半夏厚朴湯、小建中湯など
更年期・月経関連のうつ状態(のぼせ、不安、気分の浮き沈み)
→ ホルモンバランスを意識した処方で全身の安定を図ります。
処方:加味逍遙散、知柏地黄丸、女神散、温経湯、芎帰調血飲第一加減など
これらの処方は、「心の問題」にアプローチしながらも、「体質の偏り」を見逃さず、全身を整えることで気分や意欲を引き上げていくのが特徴です。うつ病は、心だけでなく体の状態とも深く結びついており、「気分が上がらない」の背景には、食事・睡眠・疲労・ホルモンなど多くの要素が関与しています。富士堂では、心と体を一つとしてとらえる視点から、今のあなたに本当に必要な漢方・養生をご提案いたします。
4.パニック障害
パニック障害は、突然の激しい動悸や息切れ、めまい、発汗、胸部の圧迫感などを伴う「パニック発作」が繰り返し起こる病気です。発作自体は数分〜1時間程度でおさまることが多いものの、「また起きるのではないか」という予期不安が強くなり、外出や人混み、乗り物などを避けるようになることがあります。
西洋医学では、抗不安薬や抗うつ薬、認知行動療法などが主な治療法として用いられますが、薬の副作用や長期的な服用への不安、根本的な回復を望む声も多く寄せられています。
漢方治療では、発作そのものだけでなく、その背景にある体の弱りや自律神経の不調を丁寧に見極め、心身全体を安定させることを目的とします。症状を抑えるだけでなく、再発を防ぐ“体質改善”の視点が特徴です。
① 漢方医学におけるパニック障害の考え方
漢方では、パニック障害を「心の不安定さ」だけでなく、「体のエネルギーの不均衡」や「神経の過緊張」「内臓機能の乱れ」といった全身的な問題としてとらえます。特に、過労や睡眠不足、ストレスの蓄積、消化機能の低下、ホルモンバランスの乱れなどが発作の背景に関与していると考えられています。
例えば以下のような特徴がみられる方には、漢方による総合的な調整が効果的です。
- ・息苦しさや動悸、胸の圧迫感が繰り返し起こる
- ・人混みや狭い空間が苦手になった
- ・パニック発作が怖くて電車や車に乗れない
- ・発作がない日も、常に不安がある
これらは、単なる精神症状ではなく「心身のバランスの乱れ」が引き起こすサインと考え、内側からその根を整えるアプローチが求められます。
② パニック障害の漢方治療
富士堂では、パニック障害のご相談に際し、発作の頻度やきっかけ、不安の程度、日常生活への影響、生活習慣や既往歴を詳細にお聞きします。また、舌診・脈診・腹診を通じて、自律神経の状態や消化器系・循環系のバランスなども総合的に評価し、その方に最も適した処方を組み立てていきます。
▼主なタイプ別の処方例 ※あくまでも一例です
神経の過緊張型(動悸、不安、胸苦しさ)
→ 自律神経の興奮を鎮め、心と体の緊張を緩める処方を中心にします。
処方:柴胡加竜骨牡蠣湯、桂枝加竜骨牡蠣湯、甘麦大棗湯、抑肝散、感応丸など
消化機能の低下を伴うタイプ(胃の不快感、吐き気、食欲不振)
→ 胃腸の働きを整えることで自律神経の安定をはかります。
処方:半夏厚朴湯、六君子湯、香蘇散など
エネルギー不足・虚弱体質型(疲労感、冷え、朝がつらい)
→ 体力や気力を補い、発作の根本的な予防を目指します。
処方:補中益気湯、人参養栄湯、帰脾湯、炙甘草湯など
女性ホルモンの変動が関与するタイプ(更年期・月経前に悪化)
→ ホルモンバランスと自律神経を整える処方を選びます。
処方:加味逍遙散、温経湯、知柏地黄丸、女神散など
これらの処方は、その場しのぎの「発作止め」ではなく、発作の起こりにくい体質づくりを目指す点が特徴です。症状だけを追いかけるのではなく、「なぜそれが起こるのか」に丁寧に向き合うことが、再発予防や生活の質の回復につながります。
富士堂では、心と体のバランスを丁寧に見極めながら、自分らしい生活を取り戻すためのサポートを多数行ってまいりました。
「いつまた発作が起きるか不安で仕方ない」
「薬を減らしたいけれど、どうしたらいいかわからない」
「症状の背景にある“根本原因”を見つけて改善したい」
そう感じていらっしゃる方は、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの不安に寄り添い、体の内側で起きている変化に目を向けながら、最適な漢方や養生をご提案いたします。
5.起立性調節障害(OD)
起立性調節障害は、自律神経の働きがうまく調整できなくなることで、立ち上がったときに血圧が下がり、脳への血流が一時的に不足しやすくなる状態です。
特に思春期の子どもに多く見られ、朝起きられない・立ちくらみ・頭痛・動悸・倦怠感などの症状が日常的に起こり、学校生活や社会活動に支障をきたすことがあります。
西洋医学では、生活指導や昇圧薬、自律神経調整薬などによる治療が行われますが、
「薬を飲んでもなかなか改善しない」
「毎朝つらく、学校に行くのが苦痛」
「心の問題ではないかと誤解されてつらい」
といった声を多くいただきます。
漢方では、起立性調節障害を「自律神経の不調」だけでなく、「体力の不足」「血流の偏り」「水分代謝の乱れ」なども含めて全身のバランスの問題と捉えます。
そのため、漢方治療では、症状だけでなく体質や生活状況にも目を向け、からだ全体の調整を図ることで、根本からの回復をめざしていきます。
① 漢方医学における起立性調節障害の考え方
漢方では、起立性調節障害を「気の巡り」「血流の調整」「水分代謝」「神経の安定性」といった、体全体の機能連携がうまくいっていない状態ととらえます。特に成長期に多いこの症状は、心と体のアンバランスが大きく影響しており、個々の体質に応じた細やかな対応が求められます。
たとえば以下のような特徴がある場合、漢方的な視点での調整が効果的です。
- ・朝起きるのが極端に苦手で、午前中は動けない
- ・少し動くと動悸や立ちくらみ、吐き気がある
- ・学校に行きたい気持ちはあるが、体がついていかない
- ・頭痛、めまい、冷え、食欲不振、腹痛などが繰り返し起こる
- ・周囲から理解されにくく、精神的にも落ち込んでいる
こうした症状は、本人の「気の持ちよう」ではなく、体の調整機能がうまく働かない状態であるため、丁寧な体質評価と全身のバランス調整が必要です。
② 起立性調節障害の漢方治療
富士堂では、起立性調節障害のご相談に対し、まずご本人の状態を丁寧にヒアリングし、必要に応じて保護者の方のご同席もいただきながら、生活状況・体調の変化・心理的背景などを総合的に確認します。
そのうえで、舌診・脈診・腹診といった漢方的所見を用いて、自律神経の状態、循環、消化吸収、冷えや水分バランスの乱れなどを立体的に評価し、最適な処方をご提案いたします。
▼主なタイプ別の処方例 ※あくまでも一例です
水分代謝・めまい型(ふらつき、動悸、気象変化に弱い)
→ 体内の水分バランスを整え、めまいやふらつき・耳鳴り・動悸を改善します。
処方:苓桂朮甘湯、五苓散、半夏白朮天麻湯、真武湯など
体力低下型(朝がつらく、全身のだるさが強い)
→ エネルギーを補い、体力・気力の土台を整えます。
処方:補中益気湯、人参養栄湯、十全大補湯、帰脾湯など
血流不良・末端冷え型(立ちくらみ・めまい・手足の冷え)
→ 末梢の血流を改善し、脳への循環を高める処方を選びます。
処方:当帰芍薬散、桂枝茯苓丸、温経湯、女神散、婦宝当帰膠など
自律神経過敏型(不安感・過緊張・動悸)
→ 神経の緊張を和らげ、自律神経のバランスを調整します。
処方:柴胡加竜骨牡蠣湯、甘麦大棗湯、加味逍遙散、抑肝散など
消化機能低下型(食欲不振・胃もたれ・腹痛)
→ 胃腸を整え、気血の生成を助けながら体調を支えます。
処方:六君子湯、香蘇散、半夏厚朴湯、小建中湯など
これらの処方は、「起立時の血圧変化」だけを対象にするのではなく、体の調節機能そのものを回復させることを重視します。 体質の改善を通じて、発作の頻度を減らし、学校や家庭での生活を支える土台をつくっていきます。
起立性調節障害は、見た目にはわかりにくく、誤解や無理解によって心理的負担がさらに増すことも少なくありません。
「朝起きられないことで学校に行けずに悩んでいる」
「検査で異常がないと言われたけれど、つらさが続いている」
「家族としてできることがわからず不安を感じている」
――そんなときは、一度ご相談ください。富士堂では、一人ひとりの状態に合わせて、無理なく改善を目指せるサポートをご提案いたします。
4. 実際の症例
**詳しい症状別の記事などについてはページ最下部のリンクからご覧いただけます**
●やる気が出ない・疲れやすい・眠れない(50代男性)
50代の男性。数か月前から仕事への意欲が出ず、日中も疲れやすい状態が続いていたとのこと。
夜は眠りが浅く、朝まで熟睡できないことも多く、最近では肩こりや頭痛、ふわふわとしためまいも出てきたため、病院への受診も検討されたそうですが、西洋薬の副作用が気になり、自然な方法での改善を希望して来店されました。
初回は個室でゆっくりとお話を伺いながら、食欲や汗の状態、脈・舌・腹部の反応を確認し、体質に合った漢方薬をご提案。外出が多いお仕事とのことで、持ち運びやすい顆粒タイプを選択しました。 また、職場の環境がストレス要因と考えられたため、上司と話し合って残業を減らすためのアドバイスもさせていただきました。
結果、2〜3か月で睡眠の質が改善し、疲れにくくなったとの報告をいただきました。以後も、体調に波が出た際は電話や来店で継続的にフォローを行いました。
●急な食欲不振と意欲低下(70代女性/ご家族からのご相談)
70代の女性。数か月前から食欲がなくなり、外出や家事をまったくしなくなったとのことで、ご家族よりご相談いただきました。以前は活発に過ごされていた方だったため、急な変化にご家族も驚かれたようです。
ご本人が来店できない状況だったため、ご家族から詳しい生活状況や体調の変化を伺い、まずは栄養と体力を補う煎じ薬をご提案。LINEや電話を通じて継続的に体調を確認しながら、必要に応じてご家族経由でご本人の様子を詳しく把握していきました。
服用開始後、徐々に食欲が回復。体力がついてきたことで気分も前向きになり、少しずつ外出できるようになったとのことです。継続したご家族のサポートが功を奏し、現在も安定した生活を送られています。
脳や神経が疲れてしまっているときは、まずはしっかりと休息をとることが何よりも大切です。
学校や仕事、将来のことなどで気持ちが追いつめられてしまったときは、焦らず自分のペースで回復を目指しましょう。
富士堂では、お一人おひとりの体と心の声に耳を傾けながら、必要な養生や漢方をご提案しています。
「これって体の問題?それとも心?」と迷ったときこそ、お気軽にご相談ください。
■併せて読みたい治療に成功した患者様たちからの口コミ
>>三叉神経痛が1ヶ月の漢方で改善|10年来の痛みに五苓散
>>原因不明の疲労・頭痛・食欲不振が1ヶ月の漢方で完治
>>漢方で肩こり・むくみや疲労感など改善&精神的なフォローで前向きになれました|体験談
>>耳鳴り・自律神経失調症が漢方で改善!|漢方体験談
>>1年以上の中途覚醒が完治|漢方薬で不眠を克服
5. 富士堂の漢方が選ばれる理由
1. オーダーメイドの漢方治療
「煎じ薬を試したいけど自分で煎じられるの?」
「忙しいから手軽に飲める顆粒剤がいい」
「日常生活でも気を付けることってある?」
ご来店いただく患者様は様々な悩みや不安を抱えています。富士堂の漢方相談では、病状や体質を丁寧に確認し、あなたに合った「証(しょう、=漢方を選ぶ根拠)」を見極めます。
初回相談は約1時間。体調のことだけでなく、経済面や精神的な不安も遠慮なくご相談ください。経験豊富な中医師・薬剤師が、生活アドバイスも含めた総合的なサポートを行います。
2. 豊富な臨床経験
富士堂に在籍するスタッフは中医師から薬剤師まで漢方の専門家でありながら、西洋医学の知識も豊富にもつスペシャリストで、毎年7,000名以上の患者様にご相談いただいています。
毎月の社内勉強会や毎週の症例ディスカッションを通じて、常に知識・技術を磨き、皆様の健康に最適な治療をご提供できるよう努めています。
3. 安全性を重視
皆様が安心・安全に漢方をご利用いただけるように以下のことを特に重視しております。
1.方証医学に基づいた、根拠のある漢方相談を徹底
時間を惜しまずに漢方相談を行い、服用後のフォローにも努め、副作用の予防や、効果の確認などに努めます。
2.信頼できるメーカーからのみの仕入れ
使用する生薬はすべて国内の大手漢方メーカー(ウチダ和漢薬・栃本天海堂・高砂薬業・イスクラ産業・クラシエ薬品)から仕入れています。海外からの直輸入は行いません。
3.厳格な品質管理
生薬はすべて原植物の確認、理化学試験、重金属・ヒ素・残留イオウの管理・経験的鑑別、残留農薬管理、微生物検査をクリアした安全なものです。
4. オンライン相談・宅配対応
富士堂では、LINE・WeChat・Teamsなどのビデオ通話ツールによるオンライン相談も可能です。漢方薬は店頭受け取りのほか、ご自宅への発送も承っています。忙しい方や遠方・海外にお住まいの方でも、安心してご利用いただけます。
オンライン相談について詳しくはこちら
6. ご相談・カウンセリングの流れ
漢方薬を受け取るまでの流れは以下のようになります。
ご予約➤ご相談➤漢方薬の選定➤ご確認・お会計➤調剤・お渡し(発送)
詳しくはこちらをご覧くださいませ。
漢方薬は、一人ひとりの体質や体調、生活環境、そしてその方をとりまく背景によって、必要な処方が大きく異なります。そのため富士堂漢方薬局では、最初に丁寧なカウンセリングを行い、現在のお困りの症状だけでなく、これまでの経過や生活習慣、ストレス要因なども含めて総合的に把握することを大切にしています。
ご相談は予約優先制で、個室にてプライバシーに配慮した落ち着いた環境の中、ゆっくりとお話を伺います。初回のカウンセリングでは、漢方医学に基づく「四診(望診・聞診・問診・切診)」をもとに、舌の状態、脈、腹部の緊張や冷えの有無なども丁寧に確認します。
また、西洋医学的な視点も大切にしており、血液検査や画像検査の結果がある場合には、それらも参考にしながら総合的に判断します。まずはお気軽にご相談ください。
■漢方相談予約・お問合せ>>「お問い合わせ(LINE,WeChat,メールフォーム)」
■オンライン相談について詳しくはこちら>>「オンライン漢方相談|来店なしでお薬お届け」
■頭痛・自律神経・精神疾患関連記事一覧
7. 頭痛・自律神経・メンタル不調でお悩みの方へ 〜富士堂からのメッセージ〜
繰り返す頭痛、眠れない夜、ふとしたときに感じる不安や落ち込み、動悸や息苦しさ、気力が湧かない日々──。
こうした心と体の不調は、周囲に理解されにくい上に、生活の質や人間関係、自信にも大きく影響を及ぼします。
「検査では異常なしと言われたけれど、やっぱりつらい」「薬を飲んでいるのに良くならない」「このままずっと続くのではないか」と感じている方も少なくありません。
富士堂では、こうした脳・神経・こころの症状を、体質や自律神経、ホルモンのバランスの乱れ、過去の体調変化や生活環境との関連性まで含めて丁寧に捉えています。
そして、表面的な症状を抑えるだけでなく、心身が本来のバランスを取り戻せるよう、一人ひとりに合った漢方処方をご提案しています。
特に、原因がわかりにくく慢性化しやすい不調こそ、漢方の得意分野です。
「どうしてもつらさが抜けない」「もう我慢するしかない」と感じている方も、どうか一度、漢方という選択肢を思い出してください。
富士堂が、あなたの心と体に本来備わっている回復力を引き出すお手伝いをいたします。
漢方治療症例・症状解説・体験談など|ブログリンク