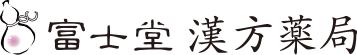Treatment病状別漢方治療

- 胃腸炎・下痢便秘・痔などの消化器系疾患の特徴と漢方での治療方法を解説
- 1.胃腸炎・下痢便秘・痔などの消化器系疾患に漢方薬を使用する理由
富士堂には、胃腸炎・胸やけ・腹痛・下痢・便秘・食欲不振・胃炎・食道炎・痔など、消化器に関するさまざまなお悩みが寄せられています。
中でも多いのは、「胃カメラでは異常が見つからないのに症状がつらい」「病院で薬をもらっているがなかなか改善しない」「できるだけ薬に頼らず、自分の体に合った方法で根本的に整えたい」といったご相談です。
こうした消化器症状は、ストレス、不規則な食生活、暴飲暴食、冷え、自律神経の乱れ、免疫力の低下、慢性的な疲労など、さまざまな要因が重なって現れることが少なくありません。そのため、症状のある部位だけを対処するのではなく、全身のバランスを整えていく漢方治療が効果的なケースも多く見られます。
実は、胃腸の不調に対応する漢方薬は種類が非常に豊富で、比較的早く効果を実感しやすいことも特徴のひとつです。さらに、症状を引き起こしている背景にある「体質の傾向」や「消化機能の低下」「体内バランスの乱れ」などに着目しながら、全身の巡りと胃腸の働きを高めていくことで、体質そのものの改善を目指すことができます。
胃腸の不調でお悩みの方には、ぜひ漢方という選択肢があることを知っていただきたいと思います。
■よくあるご相談内容
胃炎、胃痛、逆流性食道炎、機能性ディスペプシア、過敏性腸症候群、急性胃腸炎、胃もたれ、胸やけ、腹痛、下痢、便秘、食欲不振、吐き気、お腹の張り、ゲップ、呑酸、みぞおちの痛み、潰瘍性大腸炎、クローン病、胃切除後症候群、ダンピング症候群、膵炎、胆石症、胆嚢炎、胃アトニー、胃下垂、薬剤性胃腸障害、憩室炎、慢性腸炎、直腸炎、肛門周囲炎、痔核(内痔核、外痔核)、裂肛(切れ痔)、痔瘻、肛門周囲膿瘍、虚血性腸炎、食道裂孔ヘルニア、胃食道逆流症など
今回はその中でも特にご相談の多い以下の5症状と実際の症例などについて解説いたします。(タップで各項目へ)
- 1. 胃腸炎・下痢便秘・痔などの消化器系疾患に漢方薬を使用する理由
- 2. 胃腸炎・食道炎・消化器疾患に対する富士堂の漢方治療の特徴
- 3. 症状別:漢方治療アプローチ
- ➤3-1. 胃もたれ・食後の不快感(機能性ディスペプシア)
- ➤3-2. 便秘
- ➤3-3. 過敏性腸症候群(下痢や便秘をくり返すお腹の不調)
- ➤3-4. 潰瘍性大腸炎
- ➤3-5. 痔の痛み・出血(いぼ痔、切れ痔、痔瘻)
- 4. 実際の症例
- 5. 富士堂の漢方が選ばれる理由
- 6. ご相談・カウンセリングの流れ
- 7. 消化器系疾患でお悩みの方へ 〜富士堂からのメッセージ〜
2.胃腸炎・食道炎・消化器疾患に対する富士堂の漢方治療の特徴
富士堂では、胃腸炎や食道炎、下痢便秘をはじめとする消化器疾患に対する漢方相談を多く行っており、乳幼児から高齢者まで、幅広い世代の方にご利用いただいています。まずは丁寧な問診を通じて、症状の現れ方や経過、食生活の状況、ストレスの有無、排便の状態などを詳しくお伺いします。さらに漢方医学の視点を取り入れ、舌診・脈診・腹診などにより体全体のバランスを多角的に把握し、現在の消化器機能を評価します。
既に消化器内科や胃腸科などで治療を受けておられる場合は、西洋医学的な診断や服薬状況を尊重しつつ、併用可能な形での漢方治療をご提案します。特に、胃薬の副作用が気になる方や、症状の波が大きい方、長期間改善しない慢性症状のある方には、体質に合わせたオーダーメイドの処方が有効です。
富士堂では、「症状を抑える」ことだけを目的とせず、消化機能の回復、胃腸の粘膜修復、腸内環境の改善、自律神経の安定などを通じて、根本からの改善を目指していきます。食事療法や生活習慣の見直しについても丁寧にサポートいたします。
3.症状別:漢方治療アプローチ
1.胃もたれ・食後の不快感(機能性ディスペプシア)
胃もたれ・食後の不快感(機能性ディスペプシア)は、胃カメラなどの検査で明らかな異常が見つからないにも関わらず、食後の胃の重苦しさ、早期満腹感、みぞおちの痛み、胸やけなどの症状が続く疾患です。
現代社会では、ストレス、不規則な食生活、運動不足などの影響により、20代から50代の働き盛りの方に特に多く見られる傾向があります。西洋医学では、胃酸分泌抑制薬、胃運動機能改善薬、消化酵素薬などによる対症療法が基本ですが、それでも症状が改善しないケースや、薬の効果が一時的で根本的な解決に至らないケースも存在します。
そうした中で、消化機能全体のバランスを整え、胃腸の自然な働きを回復させる漢方治療は、機能性ディスペプシアの根本的な改善に対して有効なアプローチとなります。
① 漢方医学における機能性ディスペプシアの考え方
漢方では、胃もたれや食後の不快感を「胃だけの問題」とは捉えず、消化機能の低下が全身の状態とどう関わっているかを重視して考えます。特に、消化機能の低下、自律神経の乱れ、体内の水分代謝の停滞、ストレスによる気の巡りの悪化などが影響すると考えられます。また、疲れやすい・体が重だるい・精神的に不安定・冷え性・肩こり・頭痛といった全身症状が伴っている場合、単なる胃の不調というより「体全体の働きの不調」が背景にある可能性が高く、これらを含めて改善を図ることが大切です。
② 機能性ディスペプシアの漢方治療
富士堂では、まず詳細な問診に加えて、舌診・脈診・腹診などの漢方的な診察を通して、全身の状態と消化機能との関連性を多角的かつ精密に評価します。そのうえで、胃腸の運動機能改善、消化吸収力の向上、自律神経の調整などを目的とし、体質と病態に合った処方を一人ひとり丁寧に設計していきます。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■消化機能の低下が強く、食欲不振・疲労感を伴うタイプ
→ 消化機能を根本から改善し、気力・体力の回復を図ることを目的に以下の処方を検討します。
処方:補中益気湯、六君子湯、人参湯、香砂六君子湯、参蘇飲
■ストレスなどによる自律神経の乱れ、精神的緊張があるタイプ
→ 気の巡りを整え、ストレス性の胃腸症状を緩和する目的で以下の処方を用います。
処方:半夏厚朴湯、柴胡疏肝湯、柴胡加竜骨牡蛎湯、安中散、小柴胡湯、香蘇散
■胃もたれ・腹部膨満感が強く、水分代謝の停滞があるタイプ
→ 体内の水分代謝を整え、胃腸の重苦しさを軽減する処方が中心となります。
処方:平胃散、胃苓湯、二陳湯、茯苓飲、茯苓飲合半夏厚朴湯、茯苓飲加生姜半夏
■冷えによる消化機能低下、慢性的な胃の不調があるタイプ
→ 消化器系を温め、慢性的な機能低下を改善する目的で以下の処方を検討します。
処方:人参湯、附子理中湯、安中散、大建中湯、桂枝人参湯、延年半夏湯
■みぞおちのつかえ感や胃痛、炎症傾向があるタイプ
→ 胃内の熱や炎症を鎮めつつ、つかえ感や痛みを改善する処方が中心となります。
処方:半夏瀉心湯、黄連湯、甘草瀉心湯、三黄瀉心湯、大柴胡湯
これらの処方は、単に胃の症状を一時的に抑えるのではなく、体の内側から消化機能のバランスを整え、長期的な症状改善と生活の質の向上を目指す漢方治療として、機能性ディスペプシアに対して有用な選択肢となり得ます。
「食事のたびに胃が重い」「検査で異常がないのに症状が続く」「薬に頼らず根本的に改善したい」と感じている方も、どうぞご相談ください。あなたの消化機能と快適な食生活を取り戻すために、丁寧に寄り添いながら最適な漢方治療を一緒に考えてまいります。
2.便秘症
便秘症は、排便回数の減少、排便困難、便の硬化、残便感などを特徴とする疾患で、現代人の約4人に1人が悩んでいるとされる身近な症状です。
特に女性や高齢者に多く見られ、運動不足や水分・食物繊維の不足、食生活の乱れ、ホルモンバランスの変化、ストレス、加齢による腸の動きの低下、薬の影響など、さまざまな要因が関係しています。一般的な治療では下剤や整腸剤が用いられますが、薬への依存性や効果の減弱、腹痛などの副作用に悩まされるケースが少なくありません。また、一時的に排便があっても根本的な解決に至らず、慢性化してしまう方も多くいらっしゃいます。
このような状況において、腸の働きを整え、自然な排便リズムの回復を目指す漢方治療は、便秘症の改善に向けたひとつの有効な選択肢となり得ます。
① 漢方医学における便秘症の考え方
漢方医学では、便秘を単なる「腸の動きの低下」や「排便困難」といった局所的な現象としてではなく、全身のバランスの乱れとしてとらえます。
たとえば、体力や消化機能が低下し、腸の蠕動が弱くなっている場合(気虚)、体内の潤いが不足して便が硬くなり排出しにくい状態(血虚・陰虚)、ストレスなどによって気の流れが滞り、排便のリズムが乱れている状態(気滞)、冷えや加齢により体の代謝が落ち、排便の力が弱まっている状態(陽虚)などが見られます。
一方で、体内に余分な熱がこもり、腸が過剰に乾燥して硬い便が排出されにくくなる場合(実熱)、食べ過ぎや油っこいものの摂りすぎによって腸内に未消化物が停滞し、腹部膨満や不快感をともなうタイプ(食積・痰湿)など、体力がありながら過剰な状態が原因となる「実証」の便秘も少なくありません。
このように、便秘は一つの症状であっても背景にある体質や生活習慣、心身の状態によって原因や対処法が大きく異なります。また、便秘にともなって現れる肌荒れやイライラ、頭痛、肩こり、腹部の張り、食欲不振、口の渇きなどの随伴症状にも注目し、それらを手がかりに体全体の状態を見立てていくことで、より的確な処方選択や治療方針の決定につながります。
② 便秘症の漢方治療
富士堂では、まず詳細な問診に加えて、舌診・脈診・腹診などの漢方的な診察を通して、便秘の根本的な原因と体質的背景を総合的に分析いたします。その結果に基づき、腸の働きの調整、全身の気血循環の改善、自律神経の安定化などを目標とした、個別性の高い漢方処方を慎重に選択してまいります。
▼ 体質・症状別の主な処方例 ※あくまでも一例です
■便秘が強く、比較的体力が保たれているタイプ
→ 腸内に熱や滞りがこもっている、あるいは腸の蠕動が停滞していると考え、瀉下力の高い処方を用いて排便を促します。比較的体力のある成人に用いられることが多く、急性の便秘にも対応可能です。
処方:大承気湯、調胃承気湯、大黄甘草湯、桃核承気湯、三黄瀉心湯など
■腸内の潤い不足により、便が乾燥し排出しにくいタイプ
→ 体液の消耗や腸内の乾燥が背景にあると考え、腸に潤いを与えて自然な排便を促す処方を検討します。中高年層や産後、更年期にもよく見られる傾向です。
処方:麻子仁丸、潤腸湯、当帰飲子、六味地黄丸、桂枝茯苓丸など
■腸の動きが鈍く、全身の疲労感や気力の低下を伴う虚弱体質タイプ
→ 腸の蠕動運動を助けるとともに、胃腸のエネルギー不足や体全体の機能低下を補うことを目的に、以下のような補剤や温中剤を検討します。
処方:補中益気湯、大建中湯、小建中湯、人参湯、六君子湯など
■ストレスや緊張の影響で、腹部の張りや便通異常を伴うタイプ
→ 精神的ストレスや自律神経の不調が腸の運動に影響していると考えられるため、気の巡りを整え、腸の緊張を和らげる処方を中心に用います。
処方:大柴胡湯、加味逍遙散、柴胡疏肝湯、柴胡加竜骨牡蛎湯、四逆散など
■冷えや血流の滞りが関与しているタイプ
→ 腸の冷えや血行不良により排便力が低下していると考え、体を温めながら巡りを整える処方を選択します。とくに高齢者や冷え性の方に多い傾向です。
処方:当帰建中湯、桂枝加芍薬湯、桂枝茯苓丸、潤腸湯、温脾湯など
これらの治療方針は、下剤による一時的な排便促進のみならず、腸本来の機能を回復させ、自然で健康的な排便習慣の確立を目指す根本治療としても位置づけられます。
便秘症の改善には食事内容や生活リズムの見直しも不可欠であり、漢方薬による治療と並行して適切な生活指導も行っております。富士堂では長年にわたり、様々なタイプの便秘症患者さまの治療に携わり、他の医療機関での治療に満足できなかった方々にも、確かな実績と経験でお応えしてまいりました。(治療経験の詳細はブログ記事でご紹介しております)
「下剤に頼りたくない」「自然な排便リズムを取り戻したい」「便秘に伴う不快症状も改善したい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。あなたの腸の健康と快適な日常生活の実現に向けて、経験豊富な漢方治療でしっかりとサポートさせていただきます。
3.過敏性腸症候群(下痢や便秘をくり返すお腹の不調)
過敏性腸症候群は、明確な腸の異常が見つからないにもかかわらず、慢性的な下痢・便秘・腹痛・膨満感などを繰り返す疾患です。特に「ストレスを感じるとお腹が痛くなる」「緊張で下痢になる」「便秘と下痢が交互に起こる」といった症状が特徴的で、日常生活や仕事に支障をきたすほど悩まされている方も少なくありません。一方で、検査をしても異常が見つからないため、対応に困ったまま長年放置されているケースも多くあります。
富士堂漢方薬局では、このような「下痢や便秘をくり返す慢性的なお腹の不調」を、単なる腸のトラブルとしてではなく、自律神経系の乱れや消化機能の不安定さ、冷え・血流の滞りなど、全身の状態との関係性を重視してとらえています。実際に、富士堂には過敏性腸症候群で長年悩み、病院の治療ではなかなか改善しなかったという患者さまが多くご相談にいらっしゃっており、漢方的な見立てと治療によって体調の安定を得たケースも豊富にございます。
① 漢方医学における過敏性腸症候群の考え方
漢方医学の視点では、過敏性腸症候群は「気の巡りの乱れ」「胃腸の働きの弱さ」「体内の余分な湿の停滞」「冷えと熱のアンバランス」など、さまざまな要因が複雑に関与していると考えます。例えば、精神的な緊張が強いと腹痛や下痢を起こしやすい方は、神経の興奮が腸に影響している状態。
一方で、ガスが多くお腹が張る、食後に調子を崩すといった方は、消化吸収のリズムや腸内環境に乱れがある場合もあります。また、便秘と下痢をくり返す方は、自律神経のリズムが崩れて腸の運動が過敏になったり、不規則になったりしている可能性があります。
このように、同じ「過敏性腸症候群」といっても、症状のタイプや出現のパターンには個人差が大きく、それぞれに応じた丁寧な分析と対応が必要となります。
② 過敏性腸症候群の漢方治療
富士堂では、患者さま一人ひとりの体質・生活習慣・ストレスなどの状況などを詳しく伺い、さらに舌・脈・腹部の緊張などから全身状態を把握したうえで、症状の背景にある本質的なアンバランスを整える漢方処方を組み立てていきます。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■下痢型(ストレスや食後に下痢しやすい、お腹がゴロゴロ鳴る)
→ 腸の過敏な動きを抑え、水分バランスを整える処方を使います。ストレスの影響が強い場合も多く、自律神経の調整を助ける処方も含みます。
処方例:半夏瀉心湯、黄連湯、真武湯、人参湯、香砂六君子湯、参苓白朮散
■便秘型(排便回数が少なく残便感や腹部の張りを伴う)
→ 腸の動きを促進し、便を柔らかくし、滞りを改善する処方を選びます。冷えや乾燥がある場合も多いです。
処方例:桂枝加芍薬大黄湯、通導散、麻子仁丸、大建中湯、当帰建中湯、四逆散
■混合型・膨満型(下痢と便秘を繰り返し、ガスや腹部膨満感が強い)
→ 腸の調整やガスの排出を助け、腸内のバランスを整えます。ストレスや不規則な生活、冷えなど複合的な要因が関わることが多いです。
処方例:小建中湯、桂枝加芍薬湯、香砂六君子湯、柴胡加竜骨牡蛎湯、四逆散、抑肝散加陳皮半夏、平胃散、大建中湯、半夏瀉心湯
■胃腸虚弱型(慢性的に胃腸が弱く、体力も低下しやすい)
→ 胃腸の機能を補い、消化吸収力や体力を高める処方を使います。虚弱体質や疲れやすい方に適しています。
処方例:六君子湯、香砂六君子湯、補中益気湯、人参湯、安中散、参苓白朮散
過敏性腸症候群は、単なる消化器症状ではなく、心と体の連動が反映された慢性疾患ともいえます。富士堂では、再発を防ぎ、日常生活の質を向上させることを目標に、漢方を用いた根本的な体質改善をサポートしてまいります。
「通勤中にお腹が心配で外出が億劫」「いつもお腹が張っていてつらい」「検査で異常がないのに良くならない」――そんな思いを抱えている方は、ぜひ一度ご相談ください。お腹の不調が改善されることで、気持ちにもゆとりが生まれ、生活全体が大きく変わっていく可能性があります。経験豊富なスタッフが、あなたに合った治療を丁寧にご提案いたします。
4.潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に慢性的な炎症が起こり、下痢や血便、腹痛を繰り返す疾患です。症状には波があり、調子の良い時期(寛解期)と悪化する時期(再燃期)をくり返すのが特徴です。重症度には個人差があり、「少し調子が悪い日がある程度」という方から、「通勤・通学が困難なほど頻繁な便意と腹痛に悩まされている」という方まで、状態はさまざまです。
よく似た病気としてクローン病がありますが、潰瘍性大腸炎は大腸のみに炎症が起こる疾患で、粘膜に限局したびらんや潰瘍が連続的に広がるのが特徴です。一方、クローン病は口から肛門まで消化管全体に炎症が起こりうる病気で、深い潰瘍や腸の狭窄が起きやすく、病変が飛び飛びに分布する(非連続性)点が特徴です。潰瘍性大腸炎は難病指定されており、西洋医学では主に免疫を調整する薬剤や炎症を抑える治療が行われます。
しかし一方で、体質や日常の不調を含めた「全体のバランス」を整えることまでは難しいこともあり、「寛解期でもお腹の調子が安定しない」「再燃を防ぎたい」「薬を続けているが、胃腸が弱く疲れやすい」といったご相談が、富士堂漢方薬局にも多く寄せられています。
① 漢方医学における潰瘍性大腸炎の考え方
漢方では、潰瘍性大腸炎を腸だけの炎症性疾患とは捉えず、全身状態との関連性に注目します。特に、長引く下痢や血便の背景には、腸粘膜の修復力の低下、微小循環の障害、ストレスによる自律神経の不安定、冷えや疲労の蓄積などが複雑に関与していると考えます。実際の治療では、これらの要因を細かく見極め、症状の急性期・寛解期に応じて、炎症の沈静化だけでなく、再燃しにくい体の状態を整えることを重視します。
実際に富士堂では、これまで多数の潰瘍性大腸炎の方をサポートしてきました。中には、病院の治療だけでは症状が安定しなかった方が、漢方を取り入れることで「腹痛が減った」「体力が戻ってきた」「再燃しにくくなった」といった体調の変化を実感されたケースも少なくありません。
こうした症状の個人差をふまえながら、富士堂では一人ひとりの体質や生活背景を細やかに読み取り、全身状態の回復を促す漢方的アプローチを行っています。
② 潰瘍性大腸炎の漢方治療
富士堂では、まずは詳しい問診とともに、舌の状態・お腹の張り・体の冷えや緊張の有無などを通して体全体の状態を把握します。炎症や出血、免疫の過剰な働きがどのように起こっているかを読み取り、根本的なアンバランスに対処する処方を選定していきます。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■下痢・血便が続いている急性期タイプ
→ 腸の炎症を和らげ、出血や粘液を減らす処方を中心に用います。過剰な免疫反応を鎮めることも大切です。
処方例:半夏瀉心湯、柴苓湯、葛根黄連黄芩湯、黄芩湯、黄連湯
■腹痛や便意の不安定さが残る寛解期タイプ
→ 腸の働きを穏やかに整え、体力や粘膜の回復力を高める処方を使用します。冷えやストレスに左右されやすい方にも対応します。
処方例: 柴胡桂枝湯、柴苓湯、桂枝加芍薬湯、真武湯、四逆散
■体力低下・慢性疲労・胃腸虚弱を伴うタイプ
→ 長期の服薬や再燃の影響で消化力・体力が落ちている方に対し、胃腸機能の回復と免疫バランスの安定を図ります。
処方例: 補中益気湯、参苓白朮散、六君子湯、香砂六君子湯、人参養栄湯
潰瘍性大腸炎は、単に腸の炎症を抑えるだけではなく、「再燃を防ぎながら、体全体の回復力を底上げしていく」視点が重要です。富士堂では、病院での治療と併用しながら、生活の質を高めていくための体質改善をサポートしております。
「寛解期なのに調子が安定しない」「季節の変わり目やストレスでぶり返す」「お腹の調子が気になって外出が不安」――そんなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。経験豊富な薬剤師が、漢方の力で腸と全身のバランスを取り戻すお手伝いをいたします。
5.痔の痛み・出血(いぼ痔、切れ痔、痔瘻)
痔(じ)は、日本人の多くが悩まされている身近な疾患でありながら、人に相談しづらく、我慢して過ごしている方も少なくありません。
痔には主に「痔核(いぼ痔)」「裂肛(切れ痔)」「痔瘻(あな痔)」の3つのタイプがあり、痛み・出血・排便時の不快感・肛門周囲の腫れなど、日常生活に支障をきたす症状が現れます。
現代西洋医学では、炎症や出血に対して軟膏・座薬などによる局所治療が行われ、進行した痔瘻や重度の痔核には手術が選択されることもあります。しかし、体質や生活習慣に起因する再発や慢性化に悩む方も多く、「治療を受けてもすぐ再発してしまう」「冷えや疲労で悪化する」「出血がなかなか引かない」といった声が富士堂に多く寄せられます。また、最初は市販薬で対処していたものの、そのうち悪化し手術が必要だと診断されて困るケースも。
こうした症状に対して、漢方では単なる局所の異常としてではなく、全身の循環の乱れや代謝機能の低下、体の冷え、便通異常といった背景を重視し、体質そのものにアプローチすることで、痔の根本的な改善と再発防止を目指します。
① 漢方医学における「痔」の考え方
漢方では、痔の原因を「血流の滞り」「熱や湿の偏り」「排便習慣の乱れ」など、体全体のバランスの乱れと関連づけて考えます。
たとえば、便秘で強くいきむ習慣や冷えによる血行不良、辛い物・アルコールの摂りすぎによる体内の“熱”の蓄積、また慢性的な下痢によって肛門周辺が傷つきやすくなることも、痔の悪化につながる要因となります。
さらに、ストレスや疲労の蓄積によって体の回復力や免疫力が落ちると、出血や炎症が長引きやすくなります。
そのため、痔の症状に対しては、単に炎症を抑えるのではなく、便通の改善、血流促進、炎症コントロール、冷え対策など、多方面からの調整が必要となります。
② 痔に対する漢方治療
富士堂では、症状の種類(痔核・裂肛・痔瘻)や発生頻度、便通の状態、出血や腫れの有無、冷え・のぼせの傾向などを詳細にうかがったうえで、舌や腹部の緊張状態などを含めた全身評価を行います。
そのうえで、お一人おひとりの体質と症状に適した処方を、丁寧に設計・ご提案しており、「手術しないで治す治療法」として漢方薬は良いオプションと言えるでしょう。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■便秘を伴う痔核で、出血や腫れ、排便時の痛みが強いタイプ
→ 便通をスムーズにし、腸内の熱を鎮めることで、出血・炎症を和らげます。便秘と熱の両面からアプローチする処方が中心です。
処方例: 乙字湯、桃核承気湯、桂枝加芍薬大黄湯、大黄牡丹皮湯、麻子仁丸、潤腸湯
■裂肛(切れ痔)で出血が続き、排便時に激しい痛みがあるタイプ
→ 肛門周囲の乾燥や硬便を改善し、粘膜の修復を促しながら痛みを和らげます。血流を改善しつつ、腸内の潤いを整える処方が効果的です。
処方例:乙字湯、麻子仁丸、 当帰建中湯、芎帰膠艾湯、潤腸湯
■慢性的な痔で、炎症や膿、腫れを繰り返しているタイプ
→ 長引く炎症や膿を繰り返す場合は、体内にこもった熱や毒素の排出(清熱解毒・排膿)を促すとともに、血流の滞りを改善して組織の修復を助けます。
処方例: 排膿散及湯、黄連解毒湯、十味敗毒湯、桂枝茯苓丸、大黄牡丹皮湯、乙字湯
■体力低下・冷え・疲労とともに症状が悪化しやすい虚弱体質タイプ
→ 消化吸収力や血流を助け、全身状態を整えながら痔の出血や炎症を抑えることを目指します。補気補血・温陽・健脾を基本とした処方を選択します。
処方例: 補中益気湯、乙字湯、当帰建中湯、十全大補湯、芎帰膠艾湯、帰脾湯
痔は、一時的に症状を抑えるだけでは再発しやすく、生活習慣や体質に根ざした原因を見極めることが重要です。
富士堂漢方薬局では、西洋医学との併用も視野に入れつつ、漢方によって「繰り返さない体づくり」を目指します。また、他人に聞かれたら恥ずかしいと思う方も多くいらっしゃいますが、富士堂ではプライバシーに配慮した予約制かつ個室相談を採用しているため安心して先生とお話いただけます。
「ずっと座っていると痛くなる」「毎回出血があって不安」「肛門周囲の違和感が治らない」など、どんな些細な症状でもお気軽にご相談ください。経験豊富な薬剤師が、あなたの状態に合わせて丁寧に対応させていただきます。
4.実際の症例
**詳しい症状別の記事や実際にあった症例などについてはページ最下部のリンクからご覧いただけます**
①急性胃腸炎(50代男性)
1週間ほど前から腹痛と下痢が続き、ときどき吐き気も感じるようになり、体調の不安を抱えて来店されました。みぞおちには痞え(つかえ)感があり、口内炎もできていて、食欲も大きく落ちているとのことでした。
お仕事柄、煎じ薬を携帯するのは難しいとのご相談を受け、ライフスタイルに無理のない範囲で続けていただけるよう、顆粒剤の漢方薬を1日2回(朝・夕)の服用でご提案しました。お話を丁寧に伺いながら、体質や現在の状態に合った処方を選定しています。
また、薬だけでなく生活面の見直しも重要と考え、冷え対策や食事内容(生もの・刺激物の制限)についても具体的なアドバイスを行いました。症状の改善だけでなく、体調をくずしにくい身体づくりに向けて、再発予防までを含めたケアをご提案しています。
②過敏性腸症候群(30代女性)
中学生の頃からガスがたまりやすく、特に電車内など人が多い場所では、「ガスが漏れたらどうしよう」という不安に襲われ、その後に腹痛とガスの膨満感が現れるとのことでした。強いストレスがかかると下痢になることもあり、普段の便はコロコロ便から軟便の間を行き来し、常に残便感があると訴えられていました。
一方で、休日に一人で過ごしているときには症状が出にくいという特徴もあり、精神的な影響が大きいことがうかがえました。
初回のご来店時には、「他の人に相談内容を聞かれたくない」とのご希望があり、個室にてゆっくりとお話を伺いました。腹診を行ったところ、下腹部にガスがたまっており、全体的にやわらかく、冷えも感じられたため、「お腹を温めながら腸の動きを整える漢方」と「緊張をほぐす漢方」の2種類を組み合わせて処方しました。
2週間後の再診では、「症状が10→1まで改善し、電車に乗れるようになった」とのお声をいただきました。その後は、症状が気になるタイミングで頓服できるよう、顆粒剤の漢方をお守り代わりに携帯されています。
■併せて読みたい治療に成功した患者様たちからの口コミ
>>漢方2週間で3か月続いた胃痛と食欲不振が改善!ニキビも出なくなりました|漢方体験談
>>2年続いた胃腸の不調が1ヶ月半の漢方で改善|漢方体験談
5. 富士堂の漢方が選ばれる理由
1. オーダーメイドの漢方治療
「煎じ薬を試したいけど自分で煎じられるの?」
「忙しいから手軽に飲める顆粒剤がいい」
「日常生活でも気を付けることってある?」
ご来店いただく患者様は様々な悩みや不安を抱えています。富士堂の漢方相談では、病状や体質を丁寧に確認し、あなたに合った「証(しょう、=漢方を選ぶ根拠)」を見極めます。
初回相談は約1時間。体調のことだけでなく、経済面や精神的な不安も遠慮なくご相談ください。経験豊富な中医師・薬剤師が、生活アドバイスも含めた総合的なサポートを行います。
2. 豊富な臨床経験
富士堂に在籍するスタッフは中医師から薬剤師まで漢方の専門家でありながら、西洋医学の知識も豊富にもつスペシャリストで、毎年7,000名以上の患者様にご相談いただいています。
毎月の社内勉強会や毎週の症例ディスカッションを通じて、常に知識・技術を磨き、皆様の健康に最適な治療をご提供できるよう努めています。
3. 安全性を重視
皆様が安心・安全に漢方をご利用いただけるように以下のことを特に重視しております。
1.方証医学に基づいた、根拠のある漢方相談を徹底
時間を惜しまずに漢方相談を行い、服用後のフォローにも努め、副作用の予防や、効果の確認などに努めます。
2.信頼できるメーカーからのみの仕入れ
使用する生薬はすべて国内の大手漢方メーカー(ウチダ和漢薬・栃本天海堂・高砂薬業・イスクラ産業・クラシエ薬品)から仕入れています。海外からの直輸入は行いません。
3.厳格な品質管理
生薬はすべて原植物の確認、理化学試験、重金属・ヒ素・残留イオウの管理・経験的鑑別、残留農薬管理、微生物検査をクリアした安全なものです。
4. オンライン相談・宅配対応
富士堂では、LINE・WeChat・Teamsなどのビデオ通話ツールによるオンライン相談も可能です。漢方薬は店頭受け取りのほか、ご自宅への発送も承っています。忙しい方や遠方・海外にお住まいの方でも、安心してご利用いただけます。
オンライン相談について詳しくはこちら
6. ご相談・カウンセリングの流れ
漢方薬を受け取るまでの流れは以下のようになります。
ご予約➤ご相談➤漢方薬の選定➤ご確認・お会計➤調剤・お渡し(発送)
詳しくはこちらをご覧くださいませ。
漢方薬は、一人ひとりの体質や体調、生活環境、そしてその方をとりまく背景によって、必要な処方が大きく異なります。そのため富士堂漢方薬局では、最初に丁寧なカウンセリングを行い、現在のお困りの症状だけでなく、これまでの経過や生活習慣、ストレス要因なども含めて総合的に把握することを大切にしています。
ご相談は予約優先制で、個室にてプライバシーに配慮した落ち着いた環境の中、ゆっくりとお話を伺います。初回のカウンセリングでは、漢方医学に基づく「四診(望診・聞診・問診・切診)」をもとに、舌の状態、脈、腹部の緊張や冷えの有無なども丁寧に確認します。
また、西洋医学的な視点も大切にしており、血液検査や画像検査の結果がある場合には、それらも参考にしながら総合的に判断します。まずはお気軽にご相談ください。
■漢方相談予約・お問合せ>>「お問い合わせ(LINE,WeChat,メールフォーム)」
■オンライン相談について詳しくはこちら>>「オンライン漢方相談|来店なしでお薬お届け」
■頭痛・自律神経・精神疾患関連記事一覧
7.胃腸炎やお腹の不調などの消化器系疾患でお悩みの方へ 〜富士堂からのメッセージ〜
胃もたれや食後の不快感、慢性的な便秘や下痢、お腹の張り、痔による痛みや出血──。消化器系の不調は日々の食事や排便と深く関わるだけに、わずかな違和感でも生活の質を大きく左右します。
しかし、検査では「異常なし」とされることも多く、原因がはっきりしないまま悩み続けている方も少なくありません。
富士堂では、こうした消化器の不調を「胃腸の弱り」や「気・血・水の巡りの停滞」「ストレスや自律神経の乱れ」など、体全体のバランスの乱れから生じるものと考え、漢方的な視点から根本的な改善を目指しています。
体質や生活習慣に応じたオーダーメイドの処方により、「長年悩んでいた症状が軽くなった」「便通が整って毎日が楽になった」といった声を多数いただいています。
とくに富士堂漢方薬局では、慢性化した消化器症状や病院の治療だけでは改善が難しいケースに対するご相談を数多く承ってきました。
お腹の症状がつらいときこそ、自分の体と丁寧に向き合うチャンスかもしれません。「どこに行っても良くならなかった」「ずっとこのままかもしれない」と感じている方にこそ、漢方という選択肢を思い出していただきたいと願っています。
漢方治療症例・症状解説・体験談など|ブログリンク