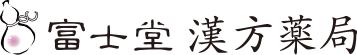Treatment病状別漢方治療

- 心血管・動悸・高血圧・低血圧・むくみなどの漢方治療
- 1.動悸・高血圧・低血圧・むくみなどを漢方薬で治療する理由
当店には、動悸・高血圧・低血圧・むくみなど、心血管系の不調に関するご相談が数多く寄せられています。
ご相談される方の多くは、
「健康診断で数値を指摘され、不安を感じている」
「病院の検査では異常がないと言われたが、つらい症状が続いている」
「病院の薬だけでなく、ほかの方法でも体調を整えたい」
といったお悩みを抱えていらっしゃいます。
これらの不調は、加齢による血管の変化、ストレスや生活習慣の乱れ、ホルモンバランスの変動、運動不足、塩分の過剰摂取など、さまざまな要因が複雑に絡み合って生じることが少なくありません。
そのため、症状のある部位だけにとらわれず、全身の血流や水分代謝、自律神経のバランスを整えていくことが大切です。こうした視点からのアプローチとして、漢方治療が効果を発揮するケースも多く見られます。
漢方では、症状の表面だけでなく、その背景にある血行不良や水分代謝の停滞、自律神経の乱れ、慢性的な炎症や内臓機能の低下など、体全体のバランスに着目します。こうした全身的な調整を通じて、心血管系の機能をサポートし、症状の軽減と体質の安定化を図ります。
■よくあるご相談内容
動悸、息切れ、胸の違和感、不整脈、期外収縮、心房細動、高血圧、血圧の変動が激しい、起立性低血圧、ふらつき、立ちくらみ、脳梗塞や心筋梗塞の後遺症ケア・再発予防、手足の麻痺、言葉が出にくい、集中力の低下、記憶力の低下、むくみ、下肢静脈瘤、間欠性跛行、心不全に伴うむくみや息切れ、更年期以降の動悸・高血圧・のぼせ、慢性疲労や体の冷えに伴う循環不良など
今回はその中でも特にご相談の多い以下の4項目と実際の症例などについて解説いたします。(タップで各項目へ)
- 1. 動悸・高血圧・低血圧・むくみなどを漢方薬で治療する理由
- 2. 心血管系のお悩みに対する富士堂の漢方治療の特徴
- 3. 症状別:漢方治療アプローチ
- ➤3-1. 動悸
- ➤3-2. 高血圧
- ➤3-3. 低血圧(朝がつらい・立ちくらみ・冷えやすい)
- ➤3-4. むくみ(浮腫)
- 4. 実際の症例
- 5. 富士堂の漢方が選ばれる理由
- 6. ご相談・カウンセリングの流れ
- 7. 心血管系のお悩みをお持ちの方へ 〜富士堂からのメッセージ〜
2.心血管系のお悩みに対する富士堂の漢方治療の特徴
富士堂では、動悸・高血圧・むくみ・ほか心血管系の不調に対する漢方相談を多く行っており、中高年の方を中心に、幅広い世代の方にご利用いただいています。まずは丁寧な問診を通じて、症状の現れ方や背景、生活状況、ストレスの有無、既往歴などを詳しくお伺いします。さらに漢方医学の視点を取り入れ、舌診・脈診・腹診などにより体全体のバランスを多角的に把握し、現在の循環機能や代謝状態を評価します。
既に循環器内科や内科などで治療を受けておられる場合は、西洋医学的な診断や服薬状況を尊重しつつ、併用可能な形での漢方治療をご提案します。例えば、血圧の薬の副作用が気になる方や、数値は安定しているが体調が優れない方、慢性的なむくみや冷えにお悩みの方には、体質に合わせたオーダーメイドの処方が有効です。
富士堂では、「数値を下げる」ことだけを目的とせず、血流の改善、水分代謝の向上、自律神経のバランス調整などを通じて、根本からの体質改善を目指していきます。食養生や生活習慣の見直しについても丁寧にサポートいたします。
3.症状別:漢方治療アプローチ
1. 動悸
動悸は、心拍数の増加や不規則な脈拍、胸のドキドキ感として現れる症状で、多くの方が日常的に経験されています。その背景には、ストレス、疲労、自律神経の乱れ、ホルモンバランスの変化、カフェインの摂取、不整脈、更年期障害など多様な要因が関与しています。特に慢性的に繰り返す動悸は、不安感や恐怖感を伴い、日常生活に大きな支障をきたすことが少なくありません。
西洋医学では、抗不整脈薬、β遮断薬、抗不安薬などの薬物治療が中心となりますが、「検査では異常がないと言われた」「薬を飲んでも根本的な改善を感じない」「副作用が心配で長期間の服用に不安がある」といったお悩みを抱える方も多くいらっしゃいます。
このような背景から、動悸に対しては「体質の改善」や「自律神経の安定」を重視した漢方治療を希望される方が増えています。動悸に適した漢方薬は多岐にわたり、患者様それぞれの症状の現れ方や体質に合わせて処方を選択することが可能です。全身のバランスや血流、自律神経の調整を図ることで、動悸の根本的な改善を目指していきます。
① 漢方医学における動悸の考え方
漢方では、動悸を「心臓だけの問題」と捉えるのではなく、全身状態との関連から総合的に評価します。例えば、精神的ストレスや過労による自律神経の過緊張、ホルモンの変動、血流の停滞、体力や抵抗力の低下、消化機能の不調、睡眠不足などが動悸の誘因・悪化因子として関係していると考えます。
特に以下のような背景がみられるケースでは、動悸は「体の不調の一部」として現れている可能性があります。
・疲れやすく、息切れしやすい
・不安感やイライラを感じやすい
・眠りが浅く、夜中に目が覚める
・胃腸が弱く、食欲にムラがある
・冷えやのぼせを感じやすい
・生理不順や更年期症状を伴う
・めまいや立ちくらみを併発する
このような症状を含めて全体を調整することで、根本的な改善につなげていくのが漢方治療の特徴です。
② 動悸の漢方治療
富士堂では、動悸にお悩みの方に対して、問診だけでなく舌・脈・腹の状態を丁寧に観察し、個々の体質と動悸の関連性を立体的に捉えるよう心がけています。そのうえで、心機能の安定、自律神経系の調整、血流の改善、精神的な安定などを視野に入れた処方設計を行っています。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■ストレス・不安性の動悸(緊張、イライラ、不眠傾向)
精神的ストレスが強く、不安感やイライラ、不眠などを伴う動悸には、自律神経の過緊張を鎮め、心身の緊張を和らげる処方が有効です。パニック発作や予期不安が強い場合には、精神安定に働きかける生薬を含む処方を選びます。
処方:半夏厚朴湯、柴胡加竜骨牡蛎湯、桂枝加竜骨牡蛎湯、抑肝散、感応丸など
■体力低下・虚弱タイプの動悸(息切れ、疲労感、食欲不振)
疲れやすく体力が低下している方に現れる動悸には、全身の気力・体力を補いながら心機能を安定させる処方を用います。特に高齢者や病後の回復期、慢性疲労を伴う方には、滋養強壮作用のある処方で根本から体質を立て直していきます。
処方:炙甘草湯、人参養栄湯、補中益気湯、帰脾湯、桂枝加竜骨牡蛎湯、生脈散など
■血流停滞タイプの動悸(胸苦しさ、肩こり、冷え)
胸の圧迫感や苦しさを伴う動悸、慢性的な肩こりや首の張りを感じる方には、血流の滞りを改善し、胸部の循環を促す処方を用います。特に女性の生理周期に関連した動悸や、冷えを伴う循環不良による動悸に効果的です。
処方:冠心逐瘀丹、桂枝茯苓丸、血府逐瘀湯、桃核承気湯など
■水分代謝の乱れによる動悸(むくみ、めまい、のぼせ)
水分代謝の異常により、心臓への負担が増加して起こる動悸には、体内の水分バランスを調整し、余分な水分の停滞を取り除く処方を使用します。むくみやめまい、立ちくらみを伴うことが多く、腎機能や循環機能の改善も重要です。
処方:苓桂朮甘湯、真武湯、五苓散、半夏白朮天麻湯など
■更年期・ホルモン性の動悸(のぼせ、発汗、イライラ)
更年期障害に伴う動悸や、ホルモンバランスの変動による症状には、女性ホルモンの調整に働きかける処方を用います。のぼせや発汗、イライラ、不眠などの更年期症状全体を改善することで、動悸の軽減を図ります。
処方:加味逍遙散、女神散、桂枝茯苓丸、柴胡加竜骨牡蠣湯、柴胡桂枝乾姜湯など
これらの処方は、単に動悸の症状を一時的に抑えるのではなく、「なぜ動悸が起こりやすいのか」という背景を整えることで、再発の予防や全身の安定にもつながる治療を目指しています。
「病院で異常なしと言われたが動悸が続く」「不安になると余計にドキドキしてしまう」「更年期に入ってから動悸が気になるようになった」—— そのような方こそ、ぜひ一度ご相談ください。症状の奥にある"体質の歪み"を見抜き、改善の糸口をご提案いたします。
2. 高血圧
高血圧は、生活習慣病の代表的な疾患として広く知られており、日本人の約3人に1人が該当するとされています。一般的に高血圧の基準は、上の血圧(収縮期血圧)が140mmHg以上、または下の血圧(拡張期血圧)が90mmHg以上とされており、近年では、家庭で測定した場合の目安として、135/85mmHg以上を高血圧と診断することもあります。血圧の慢性的な上昇は、脳血管疾患、心疾患、腎疾患などの重篤な合併症のリスクを高めるため、継続的な管理が不可欠です。しかし、「血圧の薬は一生飲み続けなければならない」「薬を飲んでいても体調がすっきりしない」「できれば薬に頼らない方法で改善したい」といった思いを抱える方が数多くいらっしゃいます。
現代医学における高血圧治療は、ACE阻害薬、ARB、カルシウム拮抗薬、利尿薬、β遮断薬などを用いた降圧療法が主体となりますが、これらは血圧をコントロールすることに重点が置かれ、根本的な体質改善までは期待できないのが現状です。
一方、漢方医学では高血圧を「血圧の数値異常」として捉えるだけでなく、その人の全体的な体調や体質的な特徴を踏まえた治療を行います。血管の柔軟性の回復、血液循環の改善、ストレス耐性の向上、水分代謝の正常化など、多角的なアプローチによって自然な血圧の安定を図ることが可能です。
① 漢方医学における高血圧の考え方
漢方では、高血圧を単純な「数値の異常」ではなく、その方の体質や生活背景と密接に関連した「全身の調和の乱れ」として理解します。血圧上昇の要因として、精神的ストレスや過労、食生活の偏り、運動不足、加齢による血管の変化、肥満、睡眠不足、体質的な水分代謝の異常などが複合的に関与していると考えられます。
たとえば、高血圧の方によく見られる随伴症状として、以下のようなものがあります:
・頭痛や頭重感、めまい
・肩こりや首筋の張り
・のぼせやほてり感
・イライラしやすく、怒りっぽい
・眠りが浅い、夢を多く見る
・動悸や胸苦しさ
・手足のむくみやしびれ
・疲労感や倦怠感
これらの症状は血圧の上昇と相互に影響し合うことがあり、漢方治療ではこうした症状全体を改善することで、結果として血圧の安定化を目指していきます。
② 高血圧の漢方治療
富士堂では、高血圧でお困りの方に対し、詳細な問診と漢方医学的な診察(舌診・脈診・腹診)を通じて、その方特有の体質パターンを見極めることから治療を開始します。血圧の数値だけでなく、随伴症状、生活習慣、ストレス状況、既往歴などを総合的に判断し、最適な処方を組み立てていきます。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■ストレス過多・イライラタイプ(怒りやすい、頭痛、肩こり)
精神的な緊張やストレスが高血圧の主要因となっているケースでは、自律神経の興奮を鎮静し、精神的な安定を図る治療を中心に行います。特に怒りやすい、イライラが強い、頭痛や肩こりを伴う方に適用されます。
主な処方:釣藤散、柴胡加竜骨牡蛎湯、大柴胡湯、加味逍遙散、黄連解毒湯など
■実証・のぼせタイプ(顔面紅潮、便秘傾向、体格良好)
比較的体力があり、のぼせや顔面の紅潮を伴う高血圧の方には、体内にこもった熱を冷まし、血管の緊張を緩和する処方を用います。便秘がちで腹部の張りを感じやすい方にも効果的です。
主な処方:大柴胡湯、三黄瀉心湯、黄連解毒湯、防風通聖散など
■水分停滞・むくみタイプ(浮腫、めまい、頭重感)
体内の水分代謝が低下し、むくみや頭重感、めまいなどを伴う高血圧には、余分な水分を排出し、循環機能を改善する処方を選択します。腎機能の低下や心不全傾向がある方にも応用されます。
主な処方:半夏白朮天麻湯、苓桂朮甘湯、五苓散、真武湯、猪苓湯など
■血行不良・瘀血タイプ(頭痛、肩こり、手足の冷え)
血液の流れが滞り、頭痛や肩こり、手足の冷えなどを伴う高血圧には、血流を改善し血管の柔軟性を回復させる処方を使用します。動脈硬化の進行予防にも期待が持てます。
主な処方:血府逐瘀湯、冠心逐瘀丹、桃核承気湯、桂枝茯苓丸など
■虚証・疲労タイプ(倦怠感、息切れ、めまい)
高齢者や慢性疾患後の方に多く見られる、体力低下を伴う高血圧には、全身の機能を補強しながら血圧の安定を図る処方を選びます。過度な降圧は避け、体全体の調和を重視した治療を行います。
主な処方:七物降下湯、人参養栄湯、八味地黄丸、牛車腎気丸など
■日内変動タイプ(朝高血圧、夜間高血圧、血圧の波が大きい)
血圧が朝だけ高い、夜間に上がる、測定のたびに数値が不安定といったタイプは、自律神経の乱れが背景にあることが多く、漢方では昼夜のリズムを整え、血圧変動を穏やかにする治療を行います。睡眠の質やストレス耐性を高め、体内時計の調整も重視します。
主な処方:柴胡加竜骨牡蛎湯、血府逐瘀湯、釣藤散、加味逍遙散など
これらの漢方治療は、血圧を機械的に下げることを目的とするのではなく、「血圧が上がりやすい体質そのもの」を改善することで、持続的で安定した血圧管理を実現します。
「薬をやめられるなら止めたい」「数値は下がったが体調は改善しない」「家族に高血圧が多く、将来が心配」「自然な方法で血圧をコントロールしたい」—— このようなお悩みを抱えていらっしゃる方は、ぜひ当薬局までご相談ください。長年の治療経験を基に、お一人おひとりに最も適した改善策をご提案させていただきます。
3.低血圧(朝がつらい・立ちくらみ・冷えやすい)
低血圧は、「血圧が低いだけだから大丈夫」と軽く考えられがちですが、慢性的な疲労感や立ちくらみ、朝のだるさ、冷え、頭痛、集中力の低下など、日常生活に大きな支障をきたすことが少なくありません。
特に、体質的に血圧が低めの方や、自律神経の乱れが関与しているタイプでは、長年にわたって不調を抱えながらも、「原因がはっきりしない」として見過ごされやすい傾向があります。
西洋医学では、明確な器質的異常がない限り積極的な治療が行われにくく、「様子を見ましょう」と言われるケースも多くあります。しかし、症状がつらく、日常生活の質が低下している方にとっては、それ自体が大きな問題です。
こうした背景から、「朝がつらい」「立ち上がるとめまいがする」「疲れやすいのに検査では異常なし」といった訴えに対し、体質や循環機能の改善を目的とした漢方治療を希望される方が増えています。
① 漢方医学における低血圧の考え方
漢方では、低血圧そのものを病名とはとらえず、体の中の巡りやエネルギー不足のサインとして捉えます。背景には、血流の不足や血行不良による末端の冷えや筋肉のこわばり、自律神経の不安定による起立性低血圧や睡眠の質の低下、さらには消化吸収力の低下や代謝・循環の低下による朝のだるさや疲労感などが関与していると考えられます。また、ホルモンバランスや体温調節機能の乱れも、体調に影響を及ぼす要因のひとつです。
特に以下のような傾向がみられる方は、低血圧による不調が出やすい体質と考えます。
・朝なかなか起きられず、午前中はぼんやりしてしまう
・立ち上がるとめまいやふらつきが起きやすい
・手足が冷えやすく、顔色が青白い
・少し動くだけで疲れやすく、回復に時間がかかる
・食後に眠気が強くなる、または食欲があまりない
・生理中や生理後に特に体調が悪化する
これらの症状は、単なる「血圧の低さ」だけではなく、体全体の巡りや調整機能の乱れが関与していることが多く、漢方ではその背景にアプローチすることを重視します。
② 低血圧の漢方治療
富士堂では、低血圧にともなう不調を改善するために、体質の全体像を重視した漢方治療を行っています。問診だけでなく、舌の色・脈の状態・腹部の反応などを確認し、自律神経、血流、胃腸機能、ホルモンの状態などを多角的に評価します。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■気虚・エネルギー不足タイプ(朝が弱い、疲れやすい、息切れ)
体のエネルギー(気)が不足しているために血圧が上がらず、朝が弱い、倦怠感、動悸、息切れなどが見られるタイプです。消化機能を助けながら全身の活力を補う治療を行います。
主な処方:補中益気湯、人参養栄湯、十全大補湯、黄耆建中湯、炙甘草湯など
■血虚タイプ(顔色が悪い、めまい、立ちくらみ)
血の不足により、めまい、ふらつき、手足の冷え、集中力低下などを伴うタイプです。漢方では「補血」によって体内を滋養し、血流や巡りを整えることで症状の改善を図ります。
主な処方:四物湯、当帰芍薬散、人参養栄湯、婦宝当帰膠、加味帰脾湯など
■自律神経機能の調整が不十分なタイプ(起立性低血圧、不安、不眠)
自律神経の調節機能が乱れており、立ちくらみや血圧変動、不安感、不眠などが見られるタイプです。心身のバランスを整える治療を行います。
主な処方:苓桂朮甘湯、加味帰脾湯、甘麦大棗湯、酸棗仁湯、半夏厚朴湯など
■冷え・水分代謝低下タイプ(手足の冷え、むくみ、胃腸虚弱)
体が冷えて水分代謝が滞ることで、血圧が上がらず、冷え、むくみ、下痢傾向、食欲不振などを伴うタイプです。体を温め、水の巡りを整える処方が用いられます。
主な処方:真武湯、六君子湯、人参湯、附子理中湯、五積散、当帰四逆加呉茱萸生姜湯など
■ストレス・気滞タイプ(抑うつ感、胸のつかえ、疲労感)
ストレスや感情の停滞によって「気」の流れが滞り、元気が出ず、血圧が安定しないタイプです。情緒の巡りを改善し、心身の調和を図ります。
主な処方:加味逍遙散、柴胡疎肝散、半夏厚朴湯、抑肝散加陳皮半夏、香蘇散など
これらの処方は、単に一時的な症状を抑えるのではなく、「なぜ低血圧の不調が出やすいのか」という体質的な原因に対して働きかけ、再発の予防や体調全体の安定につなげていくことを目的としています。
「いつも朝がつらくて、日中もだるさが抜けない」
「病院では異常がないと言われたけど、ずっと体調が悪い」
「薬には頼らず、自分の力で整えていきたい」
そのようなお悩みをお持ちの方こそ、ぜひ一度ご相談ください。富士堂では、一人ひとりの背景にある“体質の傾向”を丁寧に見極め、根本改善につながる治療方針をご提案いたします。
4. むくみ(浮腫)
朝起きたら顔が腫れぼったい、夕方になると足がパンパン、指輪がきつくなる――。このような「むくみ(浮腫)」は、特に女性に多く見られる、身近で悩ましい症状の一つです。顔のむくみ、まぶたの腫れ、手足のだるさ、足首の違和感、下肢静脈瘤のように現れ方はさまざまですが、共通するのは「一時的ではなく、繰り返す・慢性化する」ことにより、生活の質が大きく損なわれるという点です。
漢方では、むくみを単なる水分の滞りとしてではなく、「体質からのサイン」として捉え、体全体の巡りや代謝、バランスを整えることによって根本的な改善を目指します。
その背景には、以下のような要因が関与していることが多くあります:
・長時間の立ち仕事や座り仕事による下肢のうっ血
・塩分や冷たい飲食物の摂りすぎ
・冷えや代謝低下による水分循環の不良
・女性ホルモンの変化(月経・妊娠・更年期など)
・自律神経の乱れや睡眠不足
・胃腸機能の低下による水分代謝の滞り
・血行不良・下肢静脈瘤などの血液循環障害
特に女性は、生理周期やホルモンの影響によりむくみやすく、冷え・便秘・肩こりなど他の不調とセットで現れることが多いため、個々の体質に応じたアプローチが重要となります。
①漢方医学におけるむくみの考え方
漢方では、むくみは単に余分な水分が溜まっている状態ではなく、「水分を吸収・運搬・排出する力」が乱れていると考えます。さらに、「水」の巡りは単独では成り立たず、気(エネルギー)や血(血流)の働きと密接に関係しています。
そのため、むくみに対する漢方治療は以下のような背景を重視し、「なぜ水がたまるのか」という原因にアプローチします:
・胃腸の虚弱(吸収力の低下)
・血流の滞り(特に下半身)
・冷え・代謝低下(体内循環の低下)
・気の巡りの停滞(自律神経・感情面の影響)
・ホルモン変動(月経、更年期)
以下に、よく見られるタイプ別に、症状の特徴と漢方での考え方を紹介します。
②むくみの漢方治療
富士堂では、むくみ(浮腫)を改善するために、体質の全体像を重視した漢方治療を行っています。問診だけでなく、舌の色・脈の状態・腹部の反応などを確認し、自律神経、血流、胃腸機能、ホルモンの状態などを多角的に評価します。
▼体質・症状別の 主な処方例 ※あくまでも一例です
■水分代謝の低下タイプ(全身・顔・足のむくみ/胃腸虚弱)
特徴:朝起きると顔がむくむ/全身が重だるい/お腹が張る/トイレが少ない
背景:消化吸収力の低下により水分代謝がうまくいかず、体に余分な水が溜まる
処方例:五苓散、苓桂朮甘湯、半夏白朮天麻湯、防己黄耆湯、当帰芍薬散など
■血流・うっ血タイプ(足のむくみ/下肢静脈瘤)
特徴:夕方に足がパンパン/ふくらはぎの静脈が浮き出ている/足がだるい・冷える
背景:重力によって下半身の血流が滞り、血と水がうまく戻らずにむくみを生じる
処方例:桂枝茯苓丸、血府逐瘀丸、桃核承気湯、通導散、当帰四逆加呉茱萸生姜湯など
■冷え・代謝低下タイプ(慢性的なむくみ/寒がり/疲れやすい)
特徴:冷え性/疲れやすい/食欲不振/むくみが長引く
背景:身体の「温める力」が低下し、代謝や水分の巡りが滞る。全身のエネルギー不足タイプ。
処方例:真武湯、人参湯、八味丸、牛車腎気丸、桂枝人参湯など
■気滞・自律神経タイプ(ストレス性のむくみ/波がある)
特徴:むくみの出方に波がある/ストレスや疲れで悪化/胸がつかえる/眠りが浅い
背景:ストレスや緊張で気の巡りが滞ると、水分の巡りも悪くなり、むくみを引き起こす
処方例:加味逍遙散、柴胡加竜骨牡蠣湯、抑肝散、半夏厚朴湯など
■ホルモンバランス変動タイプ(月経前・更年期)
特徴:PMS(月経前症候群)でむくむ/生理前後に足が重い/更年期のむくみと冷え
背景:女性ホルモンの変化により血流と水分の調整が乱れ、むくみが生じやすくなる
処方例:温経湯、芎帰調血飲第一加減、加味逍遙散、当帰芍薬散など
むくみは、単なる一時的な症状ではなく、身体の巡りや代謝、体質の歪みが反映された「サイン」です。 漢方では、その背後にある“なぜむくむのか”という原因を見つけ出し、体質から整えていくことを目指します。
慢性的なむくみにお悩みの方こそ、「根本改善」という視点で体を見直してみませんか?顔・足・手・お腹など、どの部位のむくみでもご相談可能です。丁寧な問診と体質分析をもとに、あなたに合った処方をご提案いたします。
4. 実際の症例
**詳しい症状別の記事や実際にあった症例などについてはページ最下部のリンクからご覧いただけます**
○高血圧(50代男性)
高血圧があり、できるだけ西洋薬に頼らない生活を希望されてご来店。
やや肥満体型で不眠も合併しており、まずは体質に合った食事指導と運動指導をさせていただきました。
また、問診や舌診などから、血流が滞っている傾向がみられたため、活血化瘀薬を中心に漢方をチョイス。
その後、3ヵ月に1回通われて体質の維持と生活習慣のチェックを兼ねてフォローを続けています。血圧改善の他にも、風邪にかかりにくくなったなどと+αの効果にもご満足いただいております。
○動悸(50代男性)
以前から緊張しやすい性格で、満員電車や会議などの場面で動悸が出やすいとのことでご相談に来られました。運動時には症状が出ない一方で、「動悸が出るのでは」という不安感も強く、悪循環になっている様子がうかがえました。
その他にも、顔のほてりや逆上せ、手汗、肩こり、イライラ・気分の波、不眠傾向、性欲の低下など、ストレスや自律神経の乱れが背景にあると考えられる症状が複数みられました。
腹診では顕著な鼓音があり、緊張しやすい体質が影響していると判断。気の巡りを整える漢方を中心に、煎じ薬をご提案しました。
服用を続ける中で徐々に動悸の頻度が減り、最終的には服用回数を1日3回から1回へ、そして無服薬でも不安や動悸が起きにくい状態へと改善しました。
■併せて読みたい完治した患者様からの口コミと解説記事
>>漢方で肩こり・むくみや疲労感など改善&精神的なフォローで前向きになれました|体験談
>>高血圧症および漢方医学治療
5. 富士堂の漢方が選ばれる理由
1. オーダーメイドの漢方治療
「煎じ薬を試したいけど自分で煎じられるの?」
「忙しいから手軽に飲める顆粒剤がいい」
「日常生活でも気を付けることってある?」
ご来店いただく患者様は様々な悩みや不安を抱えています。富士堂の漢方相談では、病状や体質を丁寧に確認し、あなたに合った「証(しょう、=漢方を選ぶ根拠)」を見極めます。
初回相談は約1時間。体調のことだけでなく、経済面や精神的な不安も遠慮なくご相談ください。経験豊富な中医師・薬剤師が、生活アドバイスも含めた総合的なサポートを行います。
2. 豊富な臨床経験
富士堂に在籍するスタッフは中医師から薬剤師まで漢方の専門家でありながら、西洋医学の知識も豊富にもつスペシャリストで、毎年7,000名以上の患者様にご相談いただいています。
毎月の社内勉強会や毎週の症例ディスカッションを通じて、常に知識・技術を磨き、皆様の健康に最適な治療をご提供できるよう努めています。
3. 安全性を重視
皆様が安心・安全に漢方をご利用いただけるように以下のことを特に重視しております。
1.方証医学に基づいた、根拠のある漢方相談を徹底
時間を惜しまずに漢方相談を行い、服用後のフォローにも努め、副作用の予防や、効果の確認などに努めます。
2.信頼できるメーカーからのみの仕入れ
使用する生薬はすべて国内の大手漢方メーカー(ウチダ和漢薬・栃本天海堂・高砂薬業・イスクラ産業・クラシエ薬品)から仕入れています。海外からの直輸入は行いません。
3.厳格な品質管理
生薬はすべて原植物の確認、理化学試験、重金属・ヒ素・残留イオウの管理・経験的鑑別、残留農薬管理、微生物検査をクリアした安全なものです。
4. オンライン相談・宅配対応
富士堂では、LINE・WeChat・Teamsなどのビデオ通話ツールによるオンライン相談も可能です。漢方薬は店頭受け取りのほか、ご自宅への発送も承っています。忙しい方や遠方・海外にお住まいの方でも、安心してご利用いただけます。
オンライン相談について詳しくはこちら
6. ご相談・カウンセリングの流れ
漢方薬を受け取るまでの流れは以下のようになります。
ご予約➤ご相談➤漢方薬の選定➤ご確認・お会計➤調剤・お渡し(発送)
詳しくはこちらをご覧くださいませ。
漢方薬は、一人ひとりの体質や体調、生活環境、そしてその方をとりまく背景によって、必要な処方が大きく異なります。そのため富士堂漢方薬局では、最初に丁寧なカウンセリングを行い、現在のお困りの症状だけでなく、これまでの経過や生活習慣、ストレス要因なども含めて総合的に把握することを大切にしています。
ご相談は予約優先制で、個室にてプライバシーに配慮した落ち着いた環境の中、ゆっくりとお話を伺います。初回のカウンセリングでは、漢方医学に基づく「四診(望診・聞診・問診・切診)」をもとに、舌の状態、脈、腹部の緊張や冷えの有無なども丁寧に確認します。
また、西洋医学的な視点も大切にしており、血液検査や画像検査の結果がある場合には、それらも参考にしながら総合的に判断します。まずはお気軽にご相談ください。
■漢方相談予約・お問合せ>>「お問い合わせ(LINE,WeChat,メールフォーム)」
■オンライン相談について詳しくはこちら>>「オンライン漢方相談|来店なしでお薬お届け」
7.心血管系のお悩みをお持ちの方へ 〜富士堂からのメッセージ〜
動悸や息切れ、高血圧・低血圧、手足や顔のむくみ──。こうした心血管系の不調は、日常生活に支障をきたすだけでなく、放置することで将来的な病気のリスクにもつながるため、不安を抱えている方も多くいらっしゃいます。「原因がわからないまま薬を続けていて不安」「検査では異常がないけれど、つらさがある」といったご相談も少なくありません。
富士堂漢方薬局には、病院での治療に加えて体質から整えたいと考える方、薬の副作用や長期使用に不安を感じる方など、さまざまな方が来局されています。同じ「動悸」や「むくみ」でも、その原因や背景は人それぞれ異なるため、丁寧なカウンセリングを通して、現在の体調や生活習慣に合わせた処方をご提案しています。また、血圧の変動や季節の影響、自律神経の乱れなども視野に入れ、日常生活で気をつけるポイントや養生のアドバイスもお伝えしています。
「いつまでこの状態が続くのか不安」「今の治療に加えてできることが知りたい」と感じている方へ、あなたの心と体にそっと寄り添い、安心できる選択肢のひとつとして、富士堂が力になれたらと願っています。
漢方治療症例・症状解説・体験談など|ブログリンク